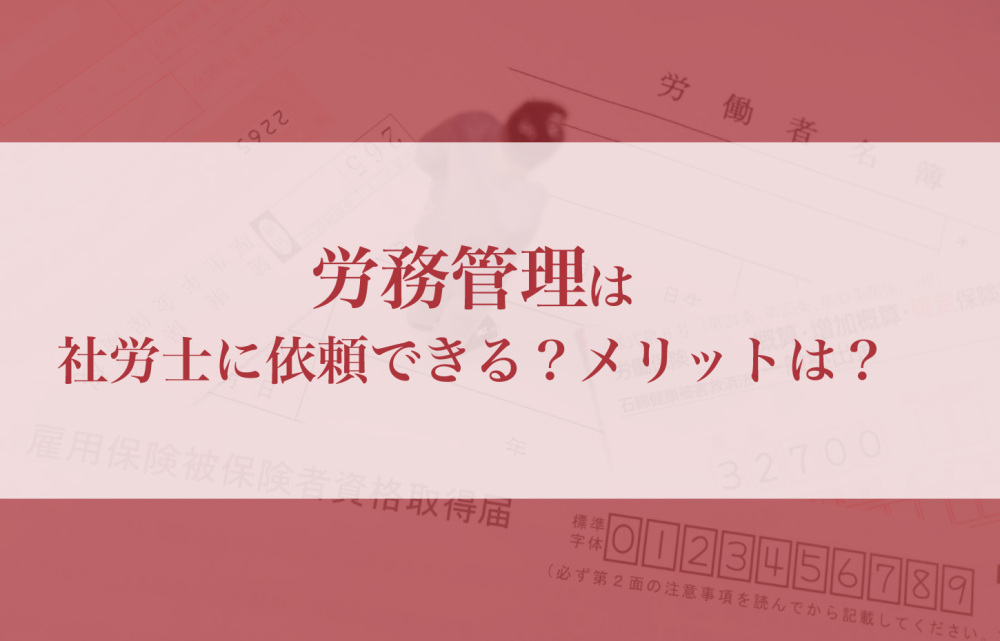INFORMAITION
お知らせ
2025年10月14日
労務管理は社労士に依頼することはできる?メリットは?
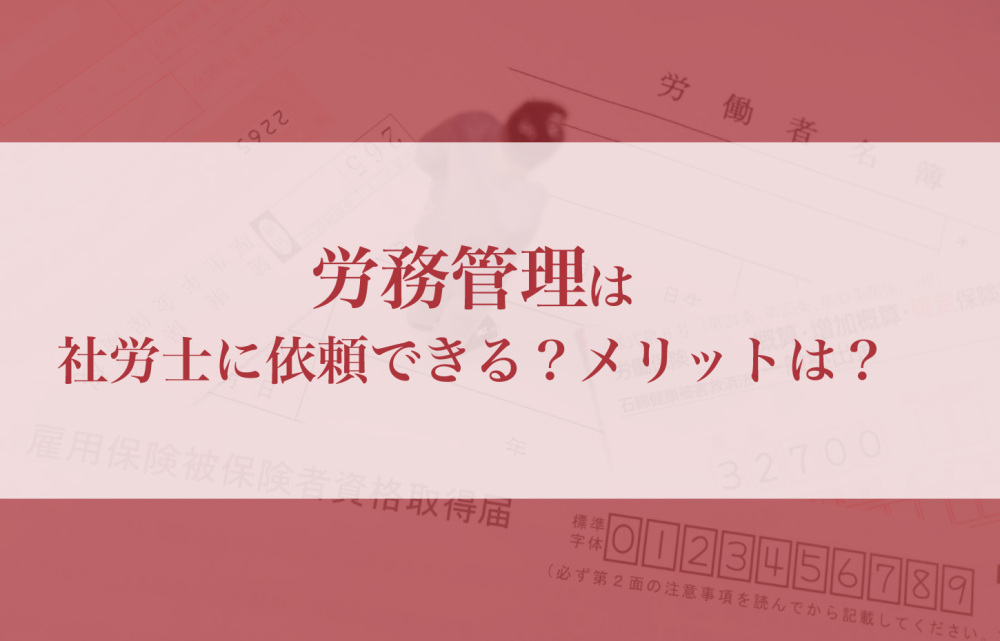
中小企業や小規模事業者では、「日々の業務で手一杯で労務管理まで手が回らない」「担当者に任せきりで、改善もできていない」という声が少なくありません。
勤怠管理や給与計算、社会保険の手続きといった労務業務は、法令に直結する重要な領域でありながら、どうしても後回しにされがちです。
その結果、担当者の負担が増大し、ミスや法令違反のリスクを抱え込んでしまうケースもあります。
こうした状況で検討すべきことが、労務管理の専門家である 社会保険労務士(社労士) への相談・依頼です。
社労士に相談・依頼することで、勤怠や社会保険の手続き、就業規則の整備といった煩雑な業務を代行してもらえるだけでなく、法改正への対応やトラブル防止のための実務的なアドバイスも受けられます。
また、社会保険労務士事務所ダブルブリッジのように、労務管理業務の代行やアドバイスだけではなく、社内の労務管理業務を最小人数で回せるように労務管理のDX化もサポートしている事務所もあります。
このように、「労務管理に工数を割けずに困っている」「担当者の負担を軽減したい」と感じている企業にとって、社労士への相談・依頼は、業務の効率化とリスク回避を同時に実現する有力な選択肢となるでしょう。
本記事では、労務管理を社労士に依頼できるのか、また依頼することで得られるメリットについてわかりやすく解説します。
社労士に労務管理を依頼することで課題のほとんどは解決できる!

中小企業が抱える次のような労務管理の課題のほとんどは、社労士に労務管理を相談・依頼することで解決できます。
- 労務管理業務に割くリソースの無さ
- 労務管理業務におけるミスの多さ
- 法改正への対応の遅れ
- 社会保険や労働保険などの手続きの遅れ
- 担当者への業務集中・属人化
- 就業規則や社内規程の整備・改訂
- イレギュラーな従業員トラブルへの対処
- 外国人労働者に関する問題への対処
- 助成金の申請機会の逸失
社労士は企業の労務管理や社会保険手続きの専門家であり、企業の「人」にまつわる実務を幅広くサポートする存在です。
また、煩雑な勤怠管理業務の一部を社労士が代行することもできます。
社労士に相談・依頼することで、労務管理業務のミスや手続き漏れ、法改正や従業員問題への対応の遅れを予防できるだけでなく、限られた社内リソース不足を補い、業務効率化にもつながります。
また、社会保険労務士事務所ダブルブリッジのように、労務管理業務の代行や、労務問題に関するアドバイスだけではなく、企業の労務管理システムなどの導入サポートをはじめ、DX化の推進をサポートしてくれる事務所も世の中にはあります。
社労士に労務管理を依頼するメリット

社労士に労務管理を依頼することで得られるメリットは、主に次の8つです。
- 守秘義務があるため安心して相談できる
- 労務トラブルを予防するためのアドバイスがもらえる
- 労務トラブルが発生した際の対応を任せられる
- 就業規則や労務ルールの整備支援を受けられる
- 労務監査を受け法令違反を未然に防げる
- 勤怠管理システムが導入しやすい
- 法改正時の対応がスムーズにできる
- 各種助成金申請業務のサポートをしてもらえる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
守秘義務があるため安心して相談できる
社労士には法律で守秘義務が課せられており、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないと定められています。
守秘義務は社労士本人だけでなく、事務所のスタッフに対しても適用されるため、社労士事務所全体で情報管理は徹底されています。
第27条(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
第二十七条の二 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
従業員の個人情報や会社の経営情報など、デリケートな内容でも安心して相談できるのがメリットと言えます。
労務トラブルを予防するためのアドバイスがもらえる
社労士は労働基準法や労働安全衛生法など労働法令に精通しています。
知識と経験をもとに、企業の規模や業種、現状の課題に応じた適切な労務管理体制を構築するためのアドバイスを受けることができます。なお、私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、企業のニーズに合わせて選べるよう2種類の契約プランを用意しています。
一つは人事・労務に関する相談業務のみを行う「アドバイザリー契約」、もう一つは労働社会保険手続き代行と労務相談、助成金の相談まで含めた「手続き・アドバイザリー契約」です。
自社に労務担当者がいるかどうか、依頼したい業務範囲の広さなどに応じて契約形態を選べるため、「相談だけしたい」「手続きもまとめて任せたい」といった企業の事情に柔軟に対応できます。労務トラブルが発生した際の対応を任せられる
従業員との間で労務トラブルが発生してしまった場合でも、社労士に相談すれば法令に基づいた適切な解決策の提示やサポートを受けることができます。
残業代の請求やハラスメントの申し立てなど従業員から何らかの要求があった際も、社労士が窓口となってアドバイスしてくれるため安心です。
また、労基署から臨時の立ち入り調査を受ける際、社労士に依頼すれば立会いをしてもらえます。その後に是正勧告を受けた場合の報告書作成までサポートしてもらえるため、心強い存在です。
特に日頃から顧問契約を結んでいれば、定期的に相談して企業の事情を把握してもらっている分、トラブル発生時もスムーズに対応策を講じてもらえます。
もっとも、紛争が裁判にまで発展した場合は社労士だけで対応できないため、社労士と提携する弁護士、もしくは自社の顧問弁護士とともに解決を図る必要があります。就業規則や労務ルールの整備支援を受けられる
社労士は就業規則や労働時間管理に関する各種ルールの整備支援も行ってくれます。
社内の就業規則が現行の労働法規や助成金や補助金の要件に照らして不備がないかチェックし、必要に応じて改定案を提示してもらえます。
法律改正や助成金や補助金の申請のたびに自社だけで規則を見直すのは大変ですが、社労士に任せれば最新の法令に沿った就業規則を維持することが可能です。
また、社労士は単に法律に合わせるだけでなく、企業の実態に合った制度設計の提案も得意としています。たとえば、社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、法改正に即したオリジナル就業規則の作成・改定支援や、労使協定(36協定等)の策定・届出といった業務もサービスに含まれています。
就業規則の整備によって労働条件を明確化し、会社と従業員双方がルールを共有できれば、労務トラブルの予防にも大いに役立つでしょう。労務監査を受け法令違反を未然に防げる
「労務監査」とは、社労士が企業の人事・労務管理の状況をチェックし、労働関連法規や労使協定、就業規則などが適切に守られているかを点検・評価する業務です。
2024年の社会保険労務士法改正によって、社労士の業務に労務監査が含まれることが法律上明確化されました。第2労務監査に関する業務の明記
社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関す
る事項に係る「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記すること。
(第2条第1項第3号関係)
引用元: 厚生労働省「社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年法律第7 7号)の概要」
労務監査を受けることで、自社では気づいていなかった法令違反の芽を事前に発見し、是正することが可能になります。
特に将来IPO(株式上場)を目指す企業にとっては、社労士の労務監査によってコンプライアンス体制をチェック・証明しておくことが有効です。勤怠管理システムが導入しやすい
勤怠管理や給与計算、社会保険手続きなどの労務管理システムには、紙やエクセルでの管理に比べて次のようなメリットがあります。
- ペーパーレス化による業務削減
- 自動集計による正確性向上
- データの一元管理やリアルタイムでの状況把握
たとえば、勤怠管理システムでは打刻データから労働時間を自動計算できるため、管理者はリアルタイムに従業員の労働時間を把握できます。
長時間労働が発生しそうな部署に早めに対策を講じる、といった運用も簡単にできます。
ただし、新しいシステムを導入する際には「機能や設定が労働基準法や自社の就業規則に沿っているか」が重要です。
ここで頼りになるのが社労士のサポートです。
社労士に依頼・相談することで次のようなメリットを享受でき、スムーズに労務管理システムの導入・定着が実行できます。
- 勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、労務データ分析など、業種・業態に合った最適なシステムを専門家の目線で提案してもらえる
- 導入前に制度面との整合性をチェックし、法令違反や運用ミスを防げる
- 導入時の設定調整や運用ルールの策定もスムーズに進められる
- 導入後も制度改正や運用上の課題に合わせて継続的なアドバイスが受けられる
つまり、社労士の支援を受ければ「システム導入のハードルを下げつつ、自社に最適化された労務管理の仕組み」を整えることができます。
法改正時の対応がスムーズにできる
社労士に労務管理を依頼すれば、頻繁に行われる法改正にもスピーディーかつ的確に対応可能です。
労働基準法をはじめとする労働関連法令は毎年のように新設・改正があり、中小企業にとって法改正の情報収集と対応は負担になりがち。
社労士に労務管理を依頼していれば、関連する法改正の内容をいち早く把握できます。また、改正に合わせた就業規則の変更や運用方法の見直しについてもサポートを受けられます。
各種助成金申請業務のサポートをしてもらえる
勤怠管理や労務管理体制の整備に利用できる助成金が数多く存在します。
たとえば、中小企業が勤怠管理システムを導入して労働環境を改善する場合、「働き方改革推進支援助成金」などの制度を利用すれば、国から費用の一部を補助してもらえます。
しかし、助成金の申請業務は年々審査が厳格化しており、追加書類の提出対応などに追われていると本業を中断せざるを得ないほどの負荷になるかもしれません。
社労士に依頼すればそうした煩雑な役所対応はすべて社労士が行ってくれるため、企業側は安心して本業に専念できます。
さらに、顧問契約を結んでいる場合、助成金の提案から計画書作成、申請書類の準備まで優先的かつ迅速に処理してもらえるのもメリットです。
私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジは各種助成金申請に精通しており、企業の助成金活用をサポートしています。実際に「助成金が受けられるのに機会を逸してしまう」というのは、単純に考えて損です。
助成金の活用は費用面で企業を助けてくれるだけでなく、受給にあたって労務管理を見直す機会にもなるため、結果的に労務環境の改善にもつながります。労務管理を社労士に相談・依頼することでミスやトラブルの予防・対処、業務効率の改善を実現しよう!
労務管理に十分な時間を割けないままアナログな方法を続けていると、業務効率の低下だけでなく、法令違反や労務トラブルを招くリスクも高まります。
そこで有効なのが、労務管理を社労士に相談・依頼することです。
社労士に依頼すれば、勤怠管理・給与計算・社会保険手続きといった煩雑な業務の効率化に加え、法改正への対応や労務トラブルの予防・対処までトータルにサポートを受けられます。
結果として、担当者の負担軽減と業務効率の改善を同時に実現できるのです。
静岡市にある社会保険労務士事務所ダブルブリッジは、社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しており、中小企業の労務管理を適正化・効率化をサポートしております。
最新の就業規則作成支援システムや勤怠管理システムの導入支援、助成金活用、人材育成支援など幅広いサービスを展開しており、特に従業員50名以下の企業における労務管理のDX化を得意としています。
「労務管理に手が回らない」「トラブルやミスを防ぎたい」と感じている方は、ぜひ一度、社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。