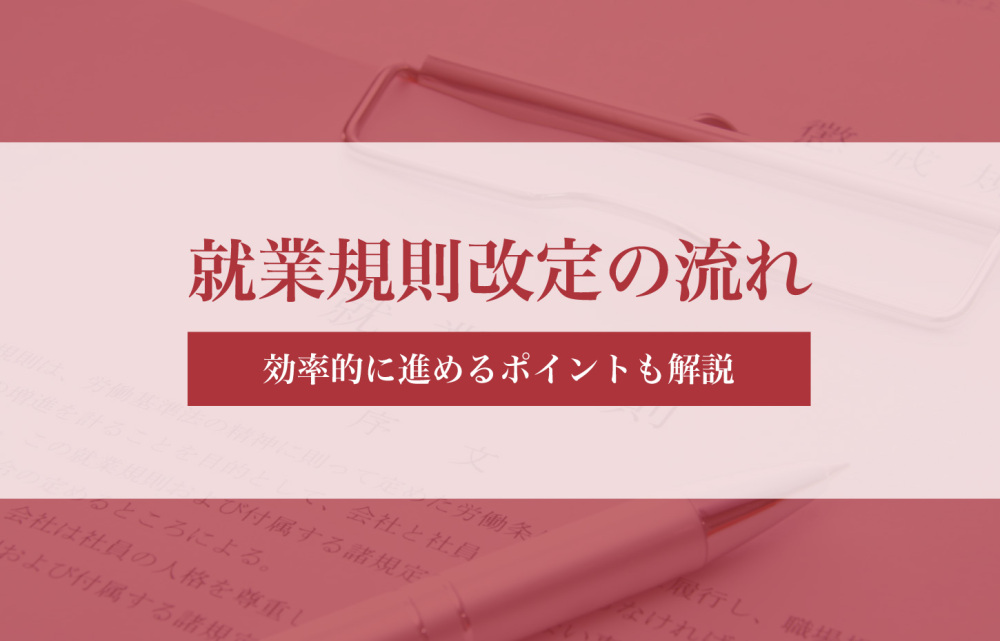INFORMAITION
お知らせ
2025年10月14日
就業規則改定の流れを解説!効率的に進めるポイント
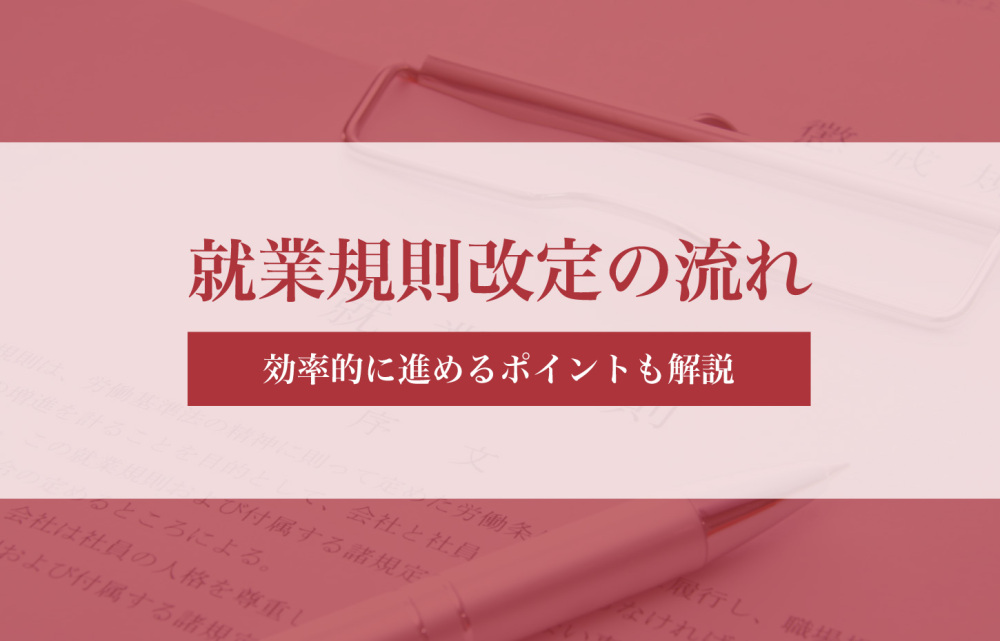
就業規則の改定作業は、主に法改正への対応や、社内でのルール変更、助成金申請に伴い行われます。
しかし、「どう進めれば良いのか分からない」「どれが正解なのかが分からない」ということから、なかなか進められない企業も多いのではないでしょうか。
実際、こういった改定の難しさから、就業規則を作ったころよりも従業員が増えているのにもかかわらず、ずっと改定されずにそのままの状態という企業も多くあるのが現状です。
労働環境と就業規則の内容が一致しないまま放置すると法令違反だけでなく従業員の不満や人材流出にもつながります。
そこで、本記事では、就業規則改定の基本的な流れや、スムーズに進めるポイントについて解説します。
就業規則改定の流れ

就業規則の改定作業は、基本的には次の5つのステップで進めていきます。(※一般的な就業規則改定の流れです。企業が何の目的で就業規則を改定するのか、など目的などによって異なるのでご注意ください)
- ステップ1.現行規則の確認と課題を整理する
- ステップ2.改定案を作成する
- ステップ3.従業員や労働組合へ意見聴取をする
- ステップ4.常時10人以上の労働者がいる事業場なら労働基準監督署への届出をする
- ステップ5.従業員へ周知する
それぞれ、各ステップの詳細と注意点を順に見ていきましょう。
ステップ1.現行規則の確認と課題を整理する
まずは現行就業規則を正しく把握し、実際の勤怠管理や労務実務とどのようにズレているかを確認することから始めます。
具体的には次の2点を行いましょう。
- 勤怠・労務管理の現状の把握
- 法令との不一致やトラブル事例の洗い出し
勤怠・労務管理の現状把握
日々の労働時間の記録方法や休暇取得の実態など、現場でどのように勤怠・労務管理が行われているかを
確認します。
タイムカードや出勤簿を紙やエクセルなどでアナログ管理されている場合は特に、残業の申請・承認方法や休憩時間の運用などを細かく洗い出しましょう。
こうした現場運用と規則の食い違いは早めに把握しておく必要があります。
法令との不一致やトラブル事例の洗い出し
就業規則の内容が最新の法令に適合しているかをチェックします。
近年の労働法改正によって現行規則が法に合致していない項目がないか確認しましょう。
特に労働時間制度、賃金(割増賃金や手当)、育児介護休業、ハラスメント防止規定などは重要なチェックポイントです。
また過去に起きた労務トラブルがあれば、トラブルの原因が就業規則の不備や曖昧さによるものではないかを検証します。
法令違反となりうる箇所や、過去のトラブルから見えてきた課題を徹底的に洗い出すことが重要です。
現行規則と実態・法令のズレをすべてリストアップし、どの部分をどう改定すべきか課題を明確にしておきましょう。
ステップ2.改定案を作成する
現状の課題が洗い出せたら、就業規則の改定案(草案)を策定します。
改定案作成時に押さえておきたいポイントは次の3つです。
- 労働基準法を遵守する
- 勤怠管理や残業規則など実務に即した内容にする
- 新旧対照表を作成する
労働基準法を遵守する
就業規則の内容は必ず労働基準法など労働関連法規の最低基準を満たすものにしなければなりません。
法律で定められた最低条件を下回る規定は無効となり、次のような法定基準が適用されてしまいます。
第12条(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
引用元:労働契約法 | 第12条
第13条(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
引用元:労働契約法 | 第13条
そのため、改定案を作成する際は各条項が法令違反にならないことを慎重に確認しましょう。
また、有給休暇の付与日数や要件なども最新法令に即した内容にする必要があります。
就業規則変更手続きのなかでも最も重要な部分であり、草案段階で社労士などに目を通してもらうことがおすすめです。
法律の最低ラインを下回らないことはもちろん、可能であれば従業員に有利な改善も検討し、法に準拠したクリーンな就業規則案に仕上げましょう。
勤怠管理や残業規則など実務に即した内容にする
就業規則を実際の勤怠管理や残業運用の実態に即した内容にすることが大切です。
せっかく改定しても、実際の職場や業務内容とかけ離れた規則では使われなくなってしまい、従業員とのトラブルの元になります。
改定の目的は、実際にきちんと機能するルールを作ることです。
残業申請のフローを明文化したり、遅刻・早退の取扱いを現状に合わせて明確化するなど、実務の手続きや対応を具体的に規定しましょう。
クラウド型の勤怠管理システムなど、労務管理システムを導入している企業の場合は、システム上の運用に合わせた規定を設けることも有効です。
逆に、これから労務管理システムを導入する場合には、システムと規則内容を連動させることが重要です。
規則の条文と職場での運用をしっかり噛み合わせ、机上のルールではなく現場で活きるルールへとブラッシュアップしましょう。
新旧対照表を作成する
改定案がまとまったら、改定前後の内容を比較できる新旧対照表を作成しておくと便利です。
新旧対照表とは、旧規則の条文と新規則の条文を対応させて一覧化した表のことです。
どの部分がどのように変更されたか一目でわかります。
新旧対照表を用意しておけば、社内の決裁者への説明もスムーズになり、後述する労基署への届出の際にも役立ちます。
新旧対照表は法令上の必須添付書類ではありませんが、多くの労基署では添付が求められるのが実情です。
改定内容を社内外に説明するツールとして、新旧対照表は作成しておいて損はありません。
ステップ3.従業員や労働組合へ意見聴取をする
就業規則の改定時には従業員(労働者)の代表者から意見を聴取することが法的に義務付けられています。
従業員(労働者)の代表者とは、次のような方になります。
- 労働組合がある場合:「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合」が代表
- 労働組合がない場合:選出された「労働者の過半数を代表する者」が代表
従業員が50名以下の中小企業・小規模事業者などにはほとんどの場合、労働組合がないため、基本的には「労働者の過半数を代表する者」が代表者になります。
具体的な選出方法は企業によって異なりますが、「会社が一方的に指名してはいけない」「労働者の過半数の支持を得る方法で選ぶ」「経営側は代表になれない」など厚生労働省通達のルールに照らし合わせると、以下のような方法で従業員代表を選出することが多いです。
- 従業員全員で話し合い、Aさんでいいよねと合意する
- 投票やアンケート形式で候補者を決め、多数決で選ぶ
こうして選出された従業員(労働者)の代表者から意見を聴いた事実を示す「意見書」を就業規則の届出時に提出しなければならず、意見書がないと届出書類は受理されません。
第90条(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
引用元:労働基準法 | 第90条
忘れずに所定の手続きを踏み、従業員代表の意見を求めましょう。
また、意見聴取は単なるお伺いではなく、規則改定を社内に周知する第一歩です。
従業員側に改定の趣旨を理解してもらい、建設的な意見があれば取り入れる姿勢で臨むことが、結果的に改定後の運用定着にも役立ちます。
必ず記録を残すこと
意見聴取を行ったら、結果を書面(意見書)に記録として残しましょう。
意見書には労働組合または過半数代表者から提出された意見(賛成・反対やコメント等)を記載し、代表者の氏名と意見聴取日付を明記します。
意見書に反対意見が書かれていたとしても、就業規則の届出自体は可能ですが、代表者の選出方法が不適切だと意見書自体が無効になる恐れがある点は注意が必要です。
ステップ4.常時10人以上の労働者がいる事業場なら労働基準監督署への届出をする
意見聴取の手続きが完了し、改定内容が固まったら、就業規則の変更届を労働基準監督署に提出します。
法律により、従業員が常時10人以上いる事業場では就業規則の作成・変更時に所轄労基署への届出義務があります。
第89条(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
引用元:労働基準法 | 第89条
「10人以上」には正社員だけでなく契約社員・パート・アルバイト等も含まれるため注意しましょう。
届出の際には、主に以下の必要書類を準備します。
- 就業規則本冊(改定後の全文)
- 労働者代表の意見書
- 新旧対照表(任意)
不備なくスムーズに受理されるよう、提出前に書類がきちんと揃っているか確認しましょう。
提出期限は就業規則を変更した日から10日以内とされています。
変更届は各労働局が提供する様式(書式第九号)に沿って作成し、必要事項を記入します。
あわせて改定内容が一目で分かる新旧対照表を添付すれば、担当官からの質問にも答えやすくなるのでおすすめです。
労基署への届出自体は形式上の受理さえされれば完了です。
提出後に内容によっては労基署から修正指導が入る場合もあります。
不明点があれば事前に労基署や社労士に相談し、届出書類を万全の状態に整えてから提出することが大切です。
なお、届出義務を怠った場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性もありますので、忘れず確実に手続きを行いましょう。
ステップ5.従業員へ周知する
労基署への届出を終えたら、最後に改定後の就業規則を従業員に周知しましょう。
まず、就業規則の周知方法を明確に定めます。
法律では、周知方法として以下の3つが例示されています。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 磁気テープや磁気ディスクなどに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
第52条
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
引用元:労働基準法施行規則 | 第52条
企業は上記いずれかの方法、または複数の方法を組み合わせて、全従業員がいつでも容易に規則内容を確認できる状態を確保しなければなりません。
中小企業で紙の配布を行う場合でも、同時に社内共有フォルダやクラウド勤怠管理システムにも掲載しておくと、リモートワーク中の社員や後日入社した社員も含め漏れなく確認できます。
周知の際には「就業規則を改定したので必ず確認するように」とアナウンスし、読了確認の仕組みを設けるのも有効です。
就業規則の周知が不十分だと、せっかく改定した規則が「ないもの」とみなされてしまうリスクがあります。
また、周知義務違反自体が労基法違反となるため、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けるリスクもあります。
悪質な場合は法律により30万円以下の罰金が科されるケースもあります。
第120条
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
引用元:労働基準法 | 第120条
「全員が新ルールを認識している」という状態を作るまでが就業規則改定の完了です。
丁寧な周知を行いましょう。
就業規則改定をスムーズに進めるための8つのポイント

就業規則改定の作業時には想定していなかった様々な問題や、後々「こうしておけば良かった」という後悔が出てきます。
そこで、改定作業を進める前、または最中には次のようなポイントを意識することが重要です。
- 早めに法改正や社内事情をキャッチアップする
- 改定理由を明確にし、社内に共有する
- 従業員代表の選出は公正にする
- 労務システムやクラウド勤怠管理と合わせて改定する
- 新旧対照表を用意する
- 周知方法を複数準備する
- 社会保険労務士など専門家に相談する
- 定期的に見直す体制をつくる
それぞれ詳しく解説します。
早めに法改正や社内事情をキャッチアップする
就業規則を改定するきっかけの多くは、法改正や社内環境の変化、または助成金の申請です。
こうした情報を早めに把握しておくことで、直前に慌てることなくスムーズに改定できます。
たとえば、「来年施行の法改正で有給休暇の付与条件が変わるらしい」という情報をつかんだら、その時点で就業規則のどこを直す必要があるか検討を始めます。
また、会社の成長や事業内容の変化によって従業員数や働き方が変わる場合にも、現行規則とのズレが生じていないか適宜チェックしましょう。
法改正情報は厚生労働省や社労士事務所のニュースレター等で入手できますが、「なかなかそこまで手が回らない」という方は、社労士などに相談・依頼することで最新情報をキャッチアップできます。
改定理由を明確にし、社内に共有する
就業規則を改定する際は、「なぜ改定が必要なのか」という理由を明確にし、改定理由を経営陣や従業員と共有しておきましょう。
理由が不明瞭なままだと、社内から「なぜルールを変えるのか?」と疑問や抵抗が生まれることがあります。
改定の背景や目的がはっきりしていれば従業員も納得しやすく、協力を得やすくなります。
「法改正対応のため」「残業管理を適正化するため」「社員から要望があったため」など具体的な理由を伝えましょう。
特に従業員(労働者)代表から意見を聴取する際には、改定案の趣旨や背景を丁寧に説明することで理解を得られやすくなります。
改定理由を社内向け資料やメールや説明会で直接伝えるのも有効です。
従業員代表の選出は公正にする
意見聴取を円滑に行うためには、従業員から信頼される代表者を公正な手続きで選出することが欠かせません。
従業員代表の選出方法が不公平だと、「会社の都合のいい人が代表に選ばれただけじゃないの?」と従業員に疑念を持たれ、意見聴取そのものが形骸化してしまう恐れがあります。
民主的な方法(無記名投票や挙手、推薦など)で選出し、全従業員の過半数の支持を得た人物を代表にしましょう。
選挙の実施にあたっては候補者の資格要件(管理職は不可など)を明示し、投票や話し合いの場を設けます。
公正なプロセスで選ばれた代表であれば従業員の信頼も厚く、意見聴取もスムーズに進みます。
また、そうすれば代表者自身も責任を持って意見を集約・表明してくれるもの。
なお選出過程は書面等に記録を残し、後で問合せがあった際に説明できるようにしておくと安心です。
労務システムやクラウド勤怠管理と合わせて改定する
就業規則の改定内容と、自社で使っている労務管理システムや勤怠管理システムの設定を連動させることも、スムーズな運用定着のコツです。
労務管理システム上で残業上限や深夜労働時間帯の設定を新ルールに合わせて変更しておけば、日々の勤怠データ集計が自動的に改定後の規則に沿ったものになります。
逆に、規則を変えたのに勤怠システムの設定を放置していると、現場運用との齟齬が生じてしまいます。
アナログ管理からクラウド勤怠への移行を検討している場合は、このタイミングで就業規則も見直し、システム導入と規則改定をセットで進めるのがおすすめです。
社労士など専門家に相談すれば、労働法に準拠した規則設計とシステム設定の両面から支援を受けることもできます。
新旧対照表を用意する
改定作業を円滑に進めるためには、改定前後の変更点を整理した新旧対照表を早めに作成しておきましょう。
新旧対照表は、社内での説明や労基署への届出、従業員への説明などあらゆる場面で役立ちます。
改定内容を社内決裁する際には、新旧対照表があれば経営層もポイントを把握しやすくなり承認がスピーディーになります。
また、従業員に説明する際も、「どこがどう変わったか」を視覚的に示せるため納得感を持ってもらいやすくなるので作っておいて損はありません。
労基署への提出時には必須ではありませんが、新旧対照表を添付すれば担当官による内容確認がスムーズになり、届出がスピーディーかつ円滑に受理される可能性が高まります。
多少手間はかかりますが、労務管理担当者にとって有益なことが多いため、就業規則改定時にはあわせて作っておくのがおすすめです。
周知方法を複数準備する
就業規則の周知は法律上求められる義務ですが、周知手段は一つに限定する必要はありません。
むしろ全従業員に確実に行き渡らせるため、複数の周知方法を併用しておくと安心です。
紙配布+掲示板掲示、あるいはイントラネット掲載+周知メール送信、といったように二重三重の周知を行えば、「見落としていた」という社員を限りなくゼロにできます。
また、昨今はクラウド勤怠システムや人事労務システム上で就業規則データを共有する企業も増えています。
どの方法にも一長一短あります。
重要なのは全員が新しい就業規則を認識できることです。
周知が不十分だと規則自体が無効と判断される可能性もあるため、周知には念を入れて複数の手段で臨みましょう。
社会保険労務士など専門家に相談する
就業規則の改定は法知識と実務感覚の両方が求められる作業です。
自社内だけで対応するのが不安な場合は、社労士など労務の専門家に相談・依頼することも検討しましょう。
社労士に依頼すれば、最新の法令知識に基づいて自社の状況に合った改定案を作成してもらえますし、改定手続きの流れについてもアドバイスを受けられます。
特に初めての就業規則改定で何から手をつければよいか分からない場合や、法改正が頻繁で追い切れないという場合におすすめです。
費用は掛かりますが、労務コンプライアンス違反による制裁やトラブル対応に比べれば見合った投資です。
なお、就業規則の改定だけでなく、勤怠管理のシステム導入や給与計算業務まで一括して依頼すれば、全体としての労務管理業務のDX化も進められます。
自社のリソース状況や重要度に応じて、社労士の力を上手に活用しましょう。
定期的に見直す体制をつくる
就業規則は一度改定して終わりではなく、定期的に見直し・改定するサイクルを組み込むことが理想です。
法改正や働き方の多様化が進む現代においては、数年放置した規則が陳腐化してしまう可能性もあります。
毎年1回は就業規則を点検する、主要な法改正のタイミングで必ず内容を確認するといったルールを社内で決めておくのがおすすめです。
定期見直しの体制を作ることで、常に最新の就業環境に合った規則を維持できます。
就業規則改定は社会保険労務士事務所ダブルブリッジにお任せください!

就業規則の改定は「現状の確認→改定案作成→従業員代表の意見聴取→労基署へ届出→従業員へ周知」というステップを踏むことが重要です。
本記事で解説したように各ステップを正しく実行すれば、法令違反や周知不足によるトラブルを防ぎ、従業員にとっても分かりやすい職場ルールの運用につながります。
特にアナログな勤怠管理・労務管理を行ってきた企業にとって、就業規則を最新の実態に合わせる作業は労務管理全体の効率化への第一歩であり、きっかけです。
アナログ管理から脱却し、法令遵守かつ職場の現状に合った適切な労務管理体制へとアップデートしてみてはいかがでしょうか。
就業規則改定にあたって専門家のサポートを検討される場合は、ぜひ社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍。
最新の就業規則作成支援システムを導入し、助成金活用サポートや人材育成、DX化支援など幅広く対応できる体制を整えています。
お気軽にご相談ください。