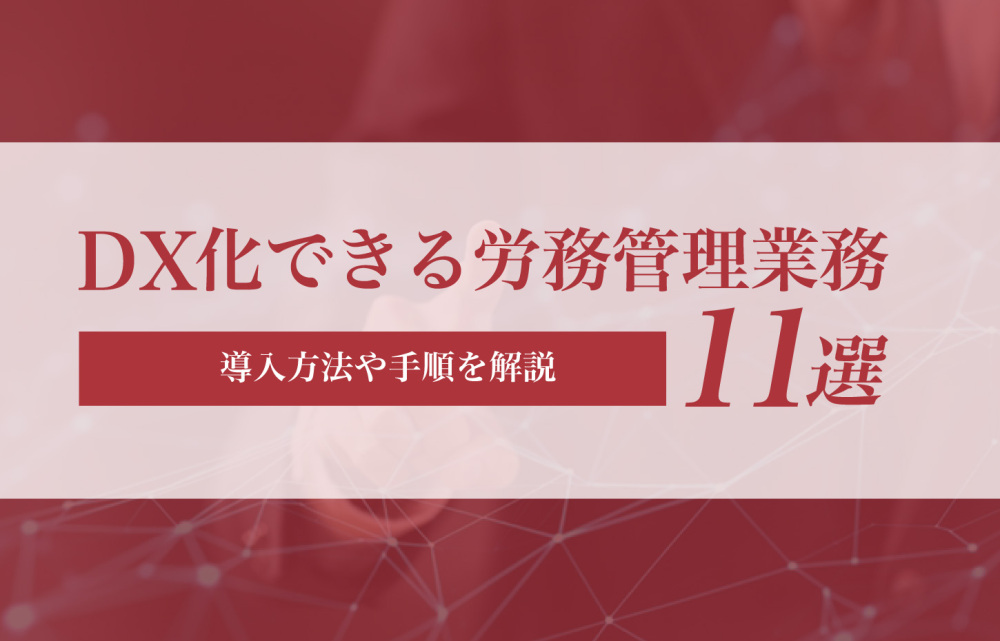INFORMAITION
お知らせ
2025年10月14日
DX化できる労務管理業務11選!導入方法や手順を解説
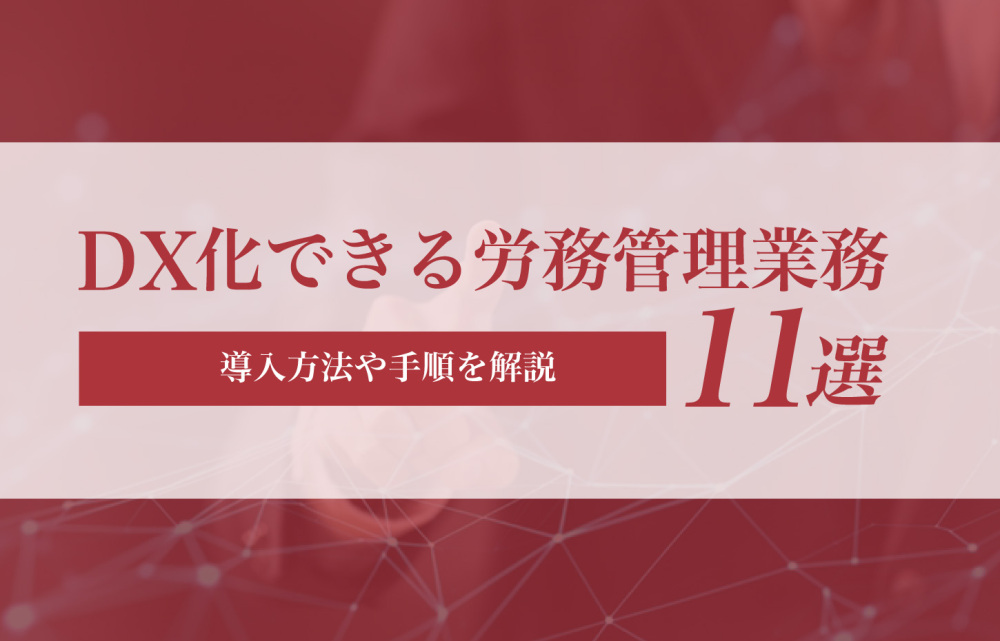
企業の人事・労務担当者の多くは、勤怠管理や給与計算、社会保険手続きといった日々の労務管理業務に膨大な時間を取られてしまっています。
紙やExcelを中心としたアナログな運用では入力ミスや確認作業が増え、生産性が低下するだけでなく、見落としなどヒューマンエラーによる法令違反のリスクすら招きかねません。
こうした課題を解決する手段として導入が進んでいるのが「労務管理DX」です。
デジタルツールやクラウドシステムを活用することで、企業の人事・労務担当者が行っている日々の労務管理業務にかかる工数を大幅に削減することができます。
また、労務管理DXは単なる業務効率化にとどまらず、より企業にとって付加価値の高い業務に人員を集中させたり、残業時間の削減など従業員満足度の向上など、さまざまな企業利益にもつながります。
しかし、「DX化と言っても何から取り掛かればいいかわからない」「どの労務管理業務がDX化できるのか検討がつかない」「日々の業務をこなすのが精一杯でDX化に取り組む余裕がない」など、「DX化に取り組みたいけれど・・・」と手が止まってしまっている人事・労務担当者は多いと思います。
本記事では、実際に社会保険労務士事務所ダブルブリッジでも行っている企業のDX化支援の経験や実績を元に、DX化できる労務管理業務や、DX化をスムーズに進めるコツについてくわしく解説します。
労務管理のDX化とは?

DX化できる労務管理業務を紹介する前に、まずは労務管理DXとは一体どのようなものなのかを知っておきましょう。
まず、DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して組織の仕組みや業務プロセスを変革することを指す言葉です。
経済産業省は、DXの定義を以下のように定めています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化を変革し、競争上の優位性を確立すること
引用元: 経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」
DXは業務効率化に留まらず、企業の競争力や持続的成長を支えるための基盤づくりという点で今後の企業成長には欠かせない重要な要素です。
労務管理のDX化とは
労務管理のDX化とは、勤怠や給与、社会保険手続きなど企業の労務管理業務をクラウドシステムやAI、RPAなどのデジタル技術で効率化する取り組みの総称です。
勤怠打刻集計や給与計算、年末調整といったルーティン業務を自動化することで、企業の人事・労務担当者はより戦略的な人事施策に時間を割けるようになります。
従来バラバラに管理されていた勤怠情報・給与・契約情報などもデジタルツールで一元化されるため、情報共有や可視化が容易になり、「この人にしかできない」という業務の属人化防止にも効果的です。
さらに、クラウド上にデータが集約されリアルタイムに可視化・分析できるため、企業の意思決定のスピードや精度が高まり、経営戦略と人事戦略の連動がしやすくなります。
たとえば、残業時間や人件費の推移をダッシュボードで可視化し、データに基づいて適正な人数の人員配置を検討するといった活用が可能です。
結果として、従業員の働きやすい業務環境を整えると同時に、コスト削減や利益率向上といった企業の競争力向上にも直結するのが労務管理DXです。
DX化できる労務管理業務11選

労務管理業務の中でDX化できる可能性の高い業務は主に次の11業務です。
- 勤怠管理が正確かつ効率的に行える
- 給与計算・支給のミスを防ぎ、法令に準拠した支払いができる
- 社会保険・労働保険手続きを正確かつ期限内に実施できる
- 労働契約や入退社手続きがスムーズに行える
- 年次イベント業務(賞与・昇給・年末調整など)を効率的に遂行できる
- 労務データ分析・レポーティングにより経営判断や人事戦略に活かせる
- 労務相談や他部門との連携を通じて職場環境を改善できる
- 就業規則やコンプライアンス監査に適切に対応できる
- 従業員情報を一元管理し、多様な雇用形態やグローバル展開にも対応できる
- 福利厚生制度を整備し、従業員満足度を高められる
- 安全衛生管理を徹底し、安心して働ける職場環境を維持できる
他にも企業の業種・業態によってさまざまなDX化が検討できると思われますが、まずはこの11の労務管理業務のDX化を検討してみましょう。
1.勤怠管理
出退勤の打刻やシフト作成、残業・休暇申請といったルーティン要素の多い勤怠管理業務は、真っ先にDX化が効果を発揮する領域です。
従業員全員が毎日行う行為を取りまとめしていく業務であるため、紙のタイムカードやExcelなどアナログで管理すればするほど手間もかかります。
そのため、DX化の効果を実感しやすく、人事・労務担当者の業務工数を削減できます。
紙のタイムカード集計に毎月何時間も費やす負担が解消されるだけではなく、各部署での残業・休暇の承認フローの効率化や、リモートワークや直行直帰など多様な働き方への対応、法改正(36協定、有給5日取得義務、最低時給に合わせた昇給など)の対応、他人による不正打刻の防止などが柔軟に可能です。
勤怠管理のDX化を行う場合、以下のような機能を持つクラウド勤怠管理システムの導入が中心的な手段です。
- 打刻(PC・スマホ・ICカード・生体認証など)
- 残業・休暇の申請と承認フローのオンライン化
- 労働時間の自動集計
- 法改正対応(残業時間アラート、有給管理など)
2.給与計算・支給
勤怠データと給与システムを自動連携させることで、残業代や各種手当や税金、保険料控除の計算を自動化できます。
手計算でのExcel入力や電卓での計算ミスを撲滅でき、従業員数が多くなってもスムーズに対応可能です。
さらに、社会保険料率の改定や税制変更への対応もクラウド給与システムが自動アップデートしてくれるため、常に最新のルールを反映した正確な給与処理が可能です。
また、オンライン給与明細を導入すれば従業員はPCやスマホでいつでも明細を確認できるようになり、給与明細の印刷・封入・配布にかかる手間やコストを削減できます。
紙の明細を毎月封入・郵送している企業であれば、これだけでも大きな工数削減と経費削減につながります。
3.社会保険・労働保険手続き
クラウド労務管理システムを導入することで、従業員の入社時に必要な健康保険・厚生年金の資格取得届や、退職時の資格喪失届などをシステムから直接作成し、そのまま電子申請システム(e-Gov)を通じてオンライン提出が可能です。
入力項目もシステム上で自動チェックされるため、ヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
また、提出期限の管理もアラート機能で自動化できるため、提出遅れによる法令違反のリスクも低くすることが可能です。
早めに電子申請に対応しておくことで、こうした制度変更にもスムーズに適応できます。
デジタルデータは検索性も高いため、労働基準監督署など外部機関から調査を受けた際にも迅速に必要書類を提示できる点は大きなメリットとなります。
4.労働契約・入退社手続き
雇用契約書を紙から電子契約に切り替えることで、印刷や押印作業が不要になります。
クラウド契約サービスを導入するなどが具体的な方法です。
入社時の雇用契約書をテンプレート化し、クラウド契約サービスで入社予定者全員の契約書のリンクを送付します。
入社予定者はPCやスマホから契約書の内容を確認し、電子署名で締結が可能です。
また、契約書の製本・郵送に伴うコストも削減できます。
入社時に提出が必要な書類(雇用契約書、身元保証書、マイナンバー提出書類など)もオンライン上のフォーム入力やアップロードで完結でき、セキュリティを担保しながら効率的に処理できます。
提出された書類データはシステム上で自動仕分け・保存され、承認フローもオンライン上で完結します。
さらに、契約書や入社書類の履歴をデジタル管理できるため、後から必要になった際にも検索してすぐに取り出せるのがメリットです。
契約書の改訂履歴も残るため、透明性が高まり、コンプライアンスという観点でもメリットがあります。
5.年次イベント業務
年末調整や社会保険算定基礎届、年度更新など、年に一度の大規模業務もオンライン化できます。
たとえば、従業員自身がデータを入力できるクラウド年末調整システムを導入すれば、紙の申告書を配布・回収して担当者が手入力する従来のやり方と比べ、作業負担を減らすことが可能です。
人事担当者は書類の内容チェックや転記作業から解放され、データの二重入力を防ぎつつ正確性を確保できる点もメリットです。
さらに、「扶養控除申告書の書き方が分からない」といった従業員からの質問も、オンラインシステム上のガイダンスやチャットサポートで即時に解決できます。
年末調整や社会保険算定基礎届の作成・提出、労働保険の年度更新など毎年訪れる人事・労務管理業務をDX化することで、工数を大幅に削減することが期待できます。
6.労務データ分析・レポーティング
クラウド勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで、勤怠や給与データを活用し、残業時間や有給取得率といった指標を自動で可視化できます。
各部署ごとの月別残業時間や有給消化率をグラフでダッシュボード表示することで、経営層や管理職が現状を一目で把握できるのがメリット。
Excelで手作業集計していたレポート作成が不要になり、大幅な工数削減が期待できます。
また、人件費の推移や部署別の労務状況を比較分析することも簡単です。
このようにただ人事・労務業務が効率化できるだけではなく、DX化により長時間労働が常態化している部署への人員配置見直しや、休暇取得促進策の立案など、データに基づいた的確な施策立案や実行が可能になることもメリットの1つです。
さらに、労務関連データを蓄積すれば、将来的にAIを用いた労務リスク予測や人材マネジメントへの活用も期待できます。
7.労務相談・他部門との連携
就業時間や有給残日数の確認、各種社内手続きに関する問い合わせ対応といった業務には、社内チャットツールの導入とAIチャットボットの導入が有効です。
日本の企業でよく利用されている代表的な社内チャットツールが次の5つです。
- Microsoft Teams:大企業や自治体、教育機関などでの導入が多い。Office365との連携がメリット
- Chatwork:中小企業での利用が特に高く、シンプルで使いやすい
- Slack:外資系・IT系企業での導入が多い。外部サービス連携が豊富なのがメリット
- LINE WORKS:LINEのビジネス版。現場スタッフなどデスクワーク以外の従業員を多く抱える企業での導入が多い
- Google Chat:Gooogle Workspaceを使用している企業での導入が多い
このように社内チャットツールを導入すれば、それまでメールと電話でやりとりをしていた他部門の部署との連携がよりスムーズにできるようになります。
また、それぞれAIチャットボットを導入すれば従業員からの質問に24時間即時対応してくれるため、担当者の負担を減らしつつ従業員もわざわざ電話やメールで人事・労務部署に問い合わせをする必要がありません。
こうした仕組みによって人事・労務担当者が電話やメールで繰り返し対応していた工数が大幅に削減されます。
また、質問対応の履歴を蓄積することで、よくある相談内容を分析し制度改善に活かすことも可能です。
8.就業規則・コンプライアンス監査対応
クラウドストレージ(Google DriveやDropboxなど)などに就業規則などの社内規程書類を電子ファイルで一元管理することで、社内ポータルやチャットツールなどを通して従業員と共有できます。
更新履歴もデジタル上に残るため規程改定の透明性が高まり、法令遵守の観点でも効果的です。
たとえば労働基準法の改正に合わせて就業規則を変更した場合、その改定日時や内容をデータ上で履歴管理でき、後から「いつ何を変更したか」を正確に辿ることができます。
従業員は必要なときに自分のPCやスマホから規程をすぐ確認できるため、会社と従業員の認識のズレや誤解を防げます。
また、労務関連データや書類がデジタル化されることで、労働基準監督署の調査や社内監査にも迅速に対応可能です。
たとえば、監督官から36協定や労働時間の記録提出を求められた場合でも、システムから必要データを即座に出力でき、紙書類や複数システムを渡り歩いて情報を探す必要がありません。
結果的に企業としてのコンプライアンス監査への対応力が高まります。
9.従業員情報管理
クラウド人事システムを導入し、従業員の個人情報や雇用形態、スキル情報などを一元管理することが可能です。
クラウド労務管理システムと連携すれば、社員の入社から異動、昇格、退職までの情報を一貫して管理でき、手続きのたびに分散した情報を集める手間がなくなります。
蓄積した人材データを分析すれば、社員のスキルや資格の把握も容易になり、適材適所の配置や将来のリーダー候補の発掘にも役立ちます。
また、正社員・契約社員・パート・フリーランスなど雇用契約ごとに異なる労務ルールも、クラウド人事システム上で柔軟に設定可能です。
10.福利厚生
福利厚生プラットフォーム(ベネフィット、ステーション、リロクラブなど)を導入し、福利厚生制度の利用申請や承認フローをオンライン化することで、従業員が使いたいときに使いやすい環境を整えられます。
紙の申請書を提出したり、人事部に直接メールを送ったりする必要がなくなり、申請ハードルが下がることで福利厚生の利用率向上が期待できます。
さらに、システム上に蓄積された福利厚生の利用データを分析すれば、どの施策がどれだけ利用されているかを可視化も可能。
福利厚生の利用度をデータで示すことで、採用活動で活用できたり、投資対効果(ROI)も明確になり、正確な経営判断材料の1つとしても利用できます。
11.安全衛生管理
クラウド健康管理システムなどを導入し、社員の定期健康診断やストレスチェックの結果を電子管理することで、受診状況を自動で把握できます。
たとえば、健康診断の受診データが医療機関からシステムに直接連携され、誰が未受診か一目で分かるようになります。
また、長時間労働の状況やストレスチェックの高ストレス者情報といったデータも同じプラットフォームで管理すれば、過重労働の兆候を早期に検知し産業医と連携して対策を講じることも可能です。
実際に、最新のクラウド健康管理システムでは健康診断データ・長時間労働データ・ストレスチェック結果を一元的に管理することができ、複合的な健康リスクを抱える社員を抽出していち早くフォローアップできる機能が標準搭載されています。
安全衛生管理のDX化は、企業が従業員の健康管理責任を適切に果たす上で重要な項目。
従業員にとっても、自分の健康データがきちんと管理されフォローされている安心感が生まれ、結果として安心して働ける職場環境づくりにつながります。
労務管理DX導入のステップ

最初からすべての人事・労務管理業務をDX化しようとすると失敗します。
労務管理DXをスムーズかつ効果的に導入していくためには、「小さなところから導入を始めて広げていくこと」が基本です。
また、企業が大きくなればなるほど、全社一気にDX化しようとすると失敗します。
「最初は小さく始めて徐々に大きくしていく」が基本です。
参考までに労務管理DX導入の理想的な手順をご紹介します。
次のように段階を踏んで取り組んでみてください。(※一般的な手順であり、企業によって有効な導入の方法は異なります)
- ステップ1:現状把握と課題整理
- ステップ2:導入目的・ゴール設定
- ステップ3:システム選定・技術検討
- ステップ4:導入準備・運用設計
- ステップ5:試験運用(パイロット導入)
- ステップ6:全社展開・定着化
- ステップ7:効果測定と継続改善
それぞれのステップについて詳しく解説します。
ステップ1:現状把握と課題整理
まずは自社の労務業務全体の洗い出しからです。
具体的には紙やExcelに依存している部分や非効率なプロセスを可視化していきます。
「誰が」「どの業務に」「どれくらい時間をかけているのか」を具体的に把握することが重要です。
たとえば、「毎月の勤怠集計とExcel入力に10時間」「入社手続き書類作成と役所提出に一人当たり半日」「有給申請の紙処理に手間取っている」といった具合に、現状の作業負荷や問題点を数値で示します。
問題点を数値で整理すると、優先的に改善すべき領域が明確になるからです。
逆にここでの現状分析・課題整理が甘いと、システム導入後に「思ったほど効率化できない」「課題だった部分が解決していない」という失敗につながりかねません。
ステップ2:導入目的・ゴール設定
次に、DX化によって「何を実現したいのか」という目的やゴールを明確に設定します。
ただ効率化するだけでなく、法令遵守の強化や従業員体験の改善など、得たい効果を具体化しましょう。
その上で「勤怠集計にかかる時間を半減する」「給与計算ミスをゼロにする」「年末調整を今年度中にペーパーレス化する」といった定量的な目標値を定めます。
ゴールが曖昧なままでは、導入効果を判断できず社内の納得感も得られにくくなりますが、あらかじめ達成基準を定量的に決めておくことで、導入後の効果測定がしやすくなり、改善活動もスムーズに行えます。
ステップ3:システム選定・技術検討
続いて、課題解決に適した労務管理システムを比較検討します。
市販の労務管理クラウドや人事労務ソフトは多数ありますが、自社の目的に合った機能を持つものかを見極める必要があります。
具体的には、以下のポイントをチェックしましょう。
- 必要な機能(勤怠管理・給与計算・電子申請・電子契約など)が搭載されているか
- ITに不慣れな従業員でも直感的に使えるか
- 導入時やトラブル時に支援が受けられるか
- 従業員数や必要機能に見合った料金か
- 個人情報保護の認証取得など十分か
また、将来的な拡張性(人事評価やタレントマネジメント機能への発展など)も考慮しておきましょう。
可能であればデモや無料トライアルを試し、自社の業務フローに適合するか操作性を確認できるようであればなお安心です。
ステップ4:導入準備・運用設計
導入する労務管理システムが決まったら、導入スケジュールを策定し、具体的な運用の流れを決めていきましょう。
具体的には、誰がいつまでに何を担当するか、テスト運用から全社展開までの流れを具体的に決めます。
また、新システムへのデータ移行(社員情報や過去データのインポート)や権限設定(誰がどの機能を使えるかの設定)もこの段階で行います。
並行して、マニュアル整備、運用ルールの明確化も進めましょう。
「打刻漏れ時の対処フロー」「システムで申請する手続き一覧」などを定めて周知し、部署ごとで使い方がばらつかないようにするのがポイント。
運用ルールの明確化とマニュアル整備を綿密に行うことで、運用の定着がしやすくなります。
最後に、導入前に社内の理解を得るため、経営層や現場への説明会を実施し、「なぜシステムを導入するのか(目的)」「従業員にとってどんなメリットがあるのか」を丁寧に伝えることを疎かにしてはいけません。
なぜなら、どんなに優秀な労務管理システムを導入したところで、それを利用する従業員の協力が得られないと運用が進まず、結果的に「導入しない方が良かった」など失敗につながりかねないためです。
そうならないためにも従業員への導入意図とメリットの周知徹底に務めましょう。
ステップ5:試験運用(パイロット導入)
いきなり全社で本格導入しては社内がパニックになってしまいます。
必ず一部部署や限定的な業務での試験運用を行いましょう。
たとえば、本社管理部門だけで勤怠システムを先行導入してみて実務フローに問題がないか確認するといった具合です。
試験導入の部署のフィードバックを集め、不具合や使いにくい点を洗い出して改善策に反映させます。
こういった労務管理システムの導入は、運用する前に想定できない問題が運用後に起こりやすいので、試験導入によってトラブルや不満点を初期段階であぶり出すことは、全社導入後の混乱を大幅に防ぐことにつながります。
ステップ6:全社展開・定着化
試験運用の次は、いよいよ全社への展開です。
初期段階では従来の紙・Excel運用との並行稼働が発生する場合もありますが、段階的に新システムへ移行し従来の運用業務を1つひとつ廃止していきます。
重要なことは、定着するまで徹底的にサポートする体制を整えることです。
困り事があればすぐ相談できるヘルプデスクや、FAQ集・マニュアル整備など、いきなり業務フローが大きく代わってしまう従業員が戸惑わないようサポートしましょう。
また、全社への展開の前に労務管理システムの導入意義や、「最初は慣れ親しんだ業務フローを変えることで大変な労力がかかる可能性があるが、定着すればこんな効率的になる」と導入時に予想される従業員側の苦労と、それを乗り越えた先の大きなメリットを提示しておくのも効果的です。
加えて、定期的に使い方の勉強会や活用事例の共有を行うことで、従業員の理解度と利用率を高める工夫もしていきましょう。
DXツールは導入したら効率化できるものではなく、定着して初めて効率化によるメリットを享受できるものです。
ステップ7:効果測定と継続改善
DXツールは導入して定着したら終わりではありません。
効果測定と分析、そして継続的な業務フローの改善をしていくことが重要です。
具体的には、「勤怠集計時間が◯%削減できたか」「給与計算ミスがゼロになったか」「紙の申請書が何枚減ったか」など、定量的な成果を確認します。
目標を達成できていない場合は、設定や運用方法を見直し追加対策を検討します。
一方、目標以上の効果が出ている場合でも、さらなる改善余地がないか検討しましょう。
労務管理DXは一度導入して終わりではなく、効果を測定し継続的に改善していくことが重要です。
このように、労務管理システムに蓄積されたデータを分析して新たな課題を発見し、人事ポリシーをアップデートするといったPDCAサイクルを回し続けて初めて、より高度な業務効率化を達成することができるのです。
加えて、将来的にAIやRPAなどより高度な仕組みへの発展も視野に入れておくと良いでしょう。
現時点では自動化できていない業務も、技術の進歩やデータ蓄積によりDX化が可能になるかもしれません。
労務管理DXで人事・労務業務の大幅な改善を!

紙やExcelを使って人力で人事・労務管理を行っている企業の場合、今回ご紹介した1つの業務でもDX化できれば、大幅な業務効率化、それに伴う生産性向上やコスト削減につながります。
従業員の業務負担も減るため、残業時間の減少や従業員満足度の向上にもつながりますし、担当者の時間をより付加価値の高い業務に振り向けることが可能になるため、売上向上や利益率向上にもつながるでしょう。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しており、企業の人事・労務管理業務のDX化を幅広くサポートしております。
- 紙やExcelで人事・労務管理を行っており、非効率さを感じている
- 人員不足で正確な人事・労務管理業務ができていない
- 人事・労務管理業務がそろそろ必要だが、そこに割ける人員がいない
このように、人事・労務管理業務のDX化を検討されているのであれば、一度社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。