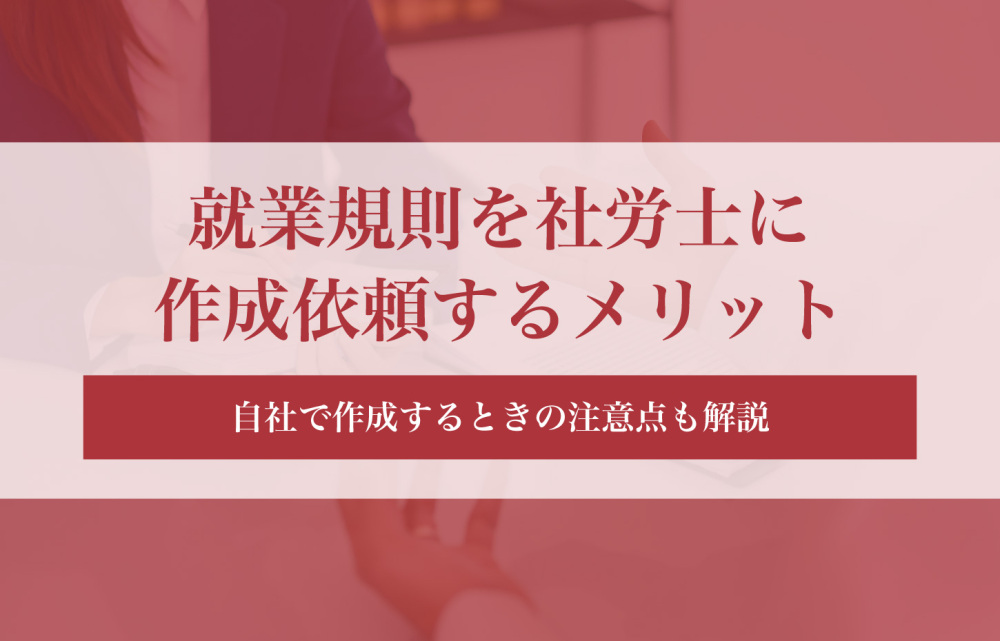INFORMAITION
お知らせ
2025年09月18日
就業規則を社労士に作成依頼するメリット!自社で作成するときの注意点も解説
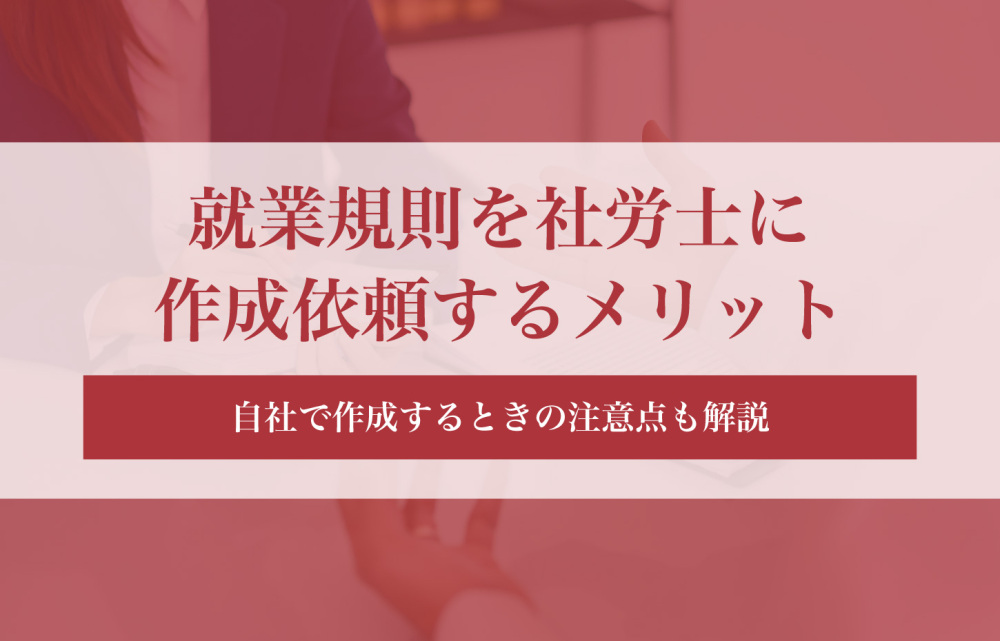
就業規則は会社にとって必要なルールであり、労使間のトラブル防止などに効果的です。
一般的には人事や総務の担当部署で作成しますが、「就業規則に何を書いてよいかわからない」「就業規則が会社の実情に合っていない」などの悩みも多いでしょう。
従業員が一定数以上の会社には就業規則の作成が義務付けられており、違反すると罰金が科せられる恐れがあるので要注意です。
本記事では、就業規則の必要性や、社会保険労務士に作成依頼するメリットなどをわかりやすく解説します。
小規模企業でも就業規則を社労士に依頼できる

会社に就業規則が必要な場合、事業規模に関わらず社会保険労務士に作成依頼できます。
就業規則の作成は労働基準法第89条に定めがあり、従業員が常時10人以上いる会社に義務付けられています。
ただし、10人未満の小規模企業が作成しても問題はありません。
また、助成金を申請する場合などは10人未満でも就業規則が作成されていることを要件とする場合もあります。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
引用元:労働基準法 | 第89条
社内に人事担当がおらず、どのように就業規則を作成してよいかわからない場合は、社会保険労務士に依頼するとよいでしょう。
パートやアルバイトが中心で正社員が少なく、勤務のパターンが複雑な会社でも、就業規則の作成によって勤怠管理が適正化された事例もあります。
ネット上のテンプレートを参考に就業規則を作成する会社もありますが、小規模企業特有の課題には対応できないケースが一般的です。
業務兼任や勤務形態の多様性、助成金活用に視点を置くなど、柔軟な就業規則を作成したい場合は、社会保険労務士に相談してみましょう。
就業規則を社会保険労務士に作成してもらうメリット7つ

就業規則を作成する際は、労務関係の専門知識が必要です。
社会保険労務士は労働関係法に詳しく、会社の業種・業態なども考慮してくれるため、就業規則の作成を依頼すると次のメリットがあります。
- 法的に有効な就業規則を作成できる
- 労使間のトラブルを防止できる
- 従業員の離職率を引き下げられる
- 業種・業態などにマッチした就業規則を作成できる
- 助成金の支給を受けやすくなる
- 就業規則の変更や労働基準監督署への届出がスムーズになる
- 法改正にも柔軟に対応できる
就業規則には労働基準法に規定された「絶対的記載事項」などを定めますが、社会保険労務士は確実に反映してくれるので、法的有効性を担保できるでしょう。
ここからは、就業規則を社会保険労務士に作成してもらう場合、どのようなメリットがあるのか詳しく解説します。
法的に有効な就業規則を作成できる
社会保険労務士に依頼すると、法的に有効な就業規則を作成できます。
就業規則には労働基準法などを反映させますが、業種・業態や経営の意思なども考慮するため、高度な専門知識が必要です。
自社で就業規則を作成した場合は、労働条件が変わった場合の現行化や、法改正に対応できないケースがあるので注意しましょう。
社会保険労務士は適法な就業規則を作成してくれるので、法令違反のリスクを回避できます。
労使間のトラブルを防止できる
就業規則を社会保険労務士が作成すると、労使間の紛争を防ぎやすくなります。
勤務時間や賃金などの規定が曖昧だった場合、残業代未払いなどのトラブルに発展しやすいため、隙のない就業規則を作成する必要があります。
労使間のトラブルがなければ、経営者・従業員ともに本業に専念できるため、会社の成長につながるでしょう。
従業員の離職率を引き下げられる
就業規則の作成を社会保険労務士に依頼し、労働条件を明確にすると、離職率を引き下げる効果があります。
ハラスメントに対する制裁や、表彰規定などが整備されていれば、「この会社で長く働きたい」「成果を出したい」と考えてもらえる可能性があるでしょう。
就業規則には従業員を守り、働きやすい環境を整備する目的もあります。
業種・業態などにマッチした就業規則を作成できる
就業規則を業種・業態にマッチさせたい場合は、社会保険労務士に作成を依頼してみましょう。
たとえば、製造業や建設業は安全衛生を重視しますが、サービス業は顧客情報の管理体制が重視されるため、業種に合わせたカスタマイズが必要です。
小売業や飲食業など、パート社員やアルバイトがいる職場では、賃金や勤務時間、休暇などの規定を整備する必要があるので、会社の業態も考慮しておきましょう。
社会保険労務士に依頼すると、自社の業種などにマッチした就業規則を作成してもらえます。
助成金の支給を受けやすくなる
社会保険労務士が就業規則を作成すると、以下のような助成金事業の採択率が高くなります。
- 両立支援等助成金(男性労働者の育児休業などを支援)
- キャリアアップ助成金(正社員化や賃金増額などを支援)
一部の助成金は就業規則の作成を要件としており、育児休業や賞与・退職金規定などがチェックされるので、申請前に十分な確認が必要です。
要件が多くなるほど見落としや勘違いのリスクも高くなるため、社会保険労務士に任せた方が安心でしょう。
無事に助成金が支給されると、事業や社員の成長につなげやすくなります。
就業規則の変更や労働基準監督署への届出がスムーズになる
常時10人以上を雇用する会社では、就業規則の作成や変更の際に、労働基準監督署への届出が必要です。
届出の際には従業員代表者の意見書、または労働組合の意見書を添付するため、社会保険労務士に任せておけば手続きがスムーズです。
意見書は事業場単位で必要となるため、10人以上の職場が複数ある場合は、社会保険労務士に依頼すると事務を効率化できるでしょう。
法改正にも柔軟に対応できる
労働関係法の改正は新聞やニュースで報道される場合もありますが、簡略的な解説であったり、見逃したりするケースが少なくありません。
社会保険労務士が就業規則を作成すると、その後の法改正にも対応してもらえるので、法令違反のリスクを低減できます。
定期的な相談枠やスポット支援を活用すれば、最低賃金や残業時間の上限など、労使間のトラブルになりやすい項目も常にチェックしてもらえるでしょう。
就業規則を社労士に依頼する際の手続きの流れ

社会保険労務士に就業規則を作成してもらう場合、一般的には以下の流れになります。
- 事前相談・ヒアリング
- 原案作成と内容のすり合わせ
- 労働者代表への意見聴取
- 労働基準監督署への届出
事前相談・ヒアリングから労働基準監督署への届出までは、2カ月程度をみておくとよいでしょう。
各ステップの詳細については、以下を参考にしてください。
事前相談・ヒアリング
社会保険労務士が就業規則を作成する際は、まず事前相談やヒアリングからスタートします。
事前相談では、就業規則に反映させる会社の業種や従業員構成、過去の労務トラブルなどを社会保険労務士に伝えましょう。
社会保険労務士からもさまざまなヒアリングがあるので、労務管理の状況を詳しく説明してください。
ヒアリングは実態調査も兼ねるため、法令違反などの現状も隠さずに伝える必要があります。
原案作成と内容のすり合わせ
事前相談やヒアリングが終わると、社会保険労務士が就業規則の原案を作成します。
原案を手渡された場合は、賃金や退職金、勤務時間などの規定が会社の実情に即しているか、必ず確認してください。
修正が必要な部分は社会保険労務士とすり合わせを行い、実効性のある就業規則に仕上げていきましょう。
労働者代表への意見聴取
就業規則の確定前には、従業員代表または労働組合の意見を聴き取り、意見書を作成してもらいます。
意見書は労働基準法90条に定められており、就業規則に添付して労働基準監督署に提出する必要があります。
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(2)使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
引用元:労働基準法 | 第90条
従業員代表に意見書を作成してもらう際は、反対意見があったとしても、法令違反の項目がなければ、就業規則は法的に有効である旨を説明してください。
意見書には従業員代表の記名も必要ですが、行政手続きのデジタル化により、2021年4月1日以降は押印不要となっています。
従業員代表が意見書の提出や記名を拒否した場合は、意見聴取した事実を証明できるよう、「理由書」を作成しておきましょう。
労働基準監督署への届出
就業規則が完成したら、管轄の労働基準監督署に提出します。
提出方法には労働基準監督署への持ち込みと郵送提出があり、就業規則と意見書は2部ずつ必要です。
1部は返却されるため、郵送提出の場合は返信用封筒を同封しておきましょう。
従業員数10人未満の会社は就業規則の届出義務がないため、社内周知のみとしても構いません。
就業規則の届出に期限は定められていませんが、施行日までには提出するのが望ましいでしょう。
業務上の都合などで就業規則の作成・届出が難しいときは、社会保険労務士に一括対応してもらうとよいでしょう。
就業規則を社労士に依頼せず自社で作成するデメリット

就業規則は厚生労働省のホームページにテンプレートがあるため、自社でも作成可能です。
ただし、法的には問題ない就業規則でも、会社の実情に合わなければ機能しないため、自社作成は以下のデメリットに注意する必要があります。
- 就業規則が法令と労働協約に準拠していない
- 従業員代表の意見を聴取していない
- 就業規則に法律用語や専門用語が多く、従業員に理解されない
- 従業員への周知が徹底されていない
- 労働基準監督署への届出を怠り、是正勧告の対象になる
- テンプレートの使用で重要事項が抜け落ちる
就業規則が法令や労働協約に反していると、違反部分のみ無効となるので要注意です。
たとえば、「残業代は支払わない」など労働基準法に反する記載は、就業規則に記載されていても無効と判断されます。
また、意見書は「同意書」ではないため、会社によっては従業員代表の意見を聴かないケースがあります。
従業員代表の意見を採り入れず、「使用者側に有利なルール」と解釈された場合、労使対立の原因になりかねません。
就業規則は各事業場共通のルールとなるため、作成後は従業員全員に配布する、または見えやすい場所に掲示するなど、周知を徹底してください。
労働基準監督署への届出を怠っていた場合は、労働基準法第120条の規定により、30万円以下の罰金に処される恐れがあります。
他社の就業規則を流用したり、ネット上のテンプレートを使ったりすると、表彰・制裁などの項目が抜け落ちてしまい、経営の意思を反映できなくなるので注意しましょう。
社労士のようなプロに依頼せず、就業規則に不備がある会社のリスク

会社に就業規則がなかった場合、労使間のトラブルが訴訟に発展し、長期的な争いになる可能性があるので注意してください。
規律のない職場はハラスメントが常態化する恐れもあるので、社会保険労務士のようなプロが就業規則を作成していなかった場合は、以下のリスクが想定されます。
- 顧客情報の流出
- パワハラやセクハラの常態化
- 従業員を懲戒処分できない
- 定年退職に応じてもらえない
- 残業代や退職金などの請求トラブル
- 労働基準法に違反する恐れがある
ここからは、就業規則がない、または就業規則に不備がある場合、どのようなリスクが発生するのか詳しく解説します。
顧客情報の流出
就業規則で、顧客情報の取り扱いについて定めなかった場合、同業他社に流出する恐れがあります。
たとえば、退職した従業員が顧客情報を持ち出し、同業他社に就職した場合は、営業活動に悪用されるリスクが考えられます。
顧客情報の流出は会社の信頼を失うため、最悪の場合は廃業を余儀なくされるでしょう。
退職した従業員にも守秘義務を徹底させたい場合は、秘密保持義務を明記した就業規則が必要です。
顧客情報を扱う会社であれば、就業規則に「退職後も業務上知り得た情報については、第三者に漏らしてはならない」などの一文を盛り込むとよいでしょう。
パワハラやセクハラの常態化
就業規則がない会社はハラスメントが常態化しやすいため、パワハラやセクハラが原因となり、従業員が辞めてしまう可能性があります。
パワハラなどを定義した改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)や、セクハラを定義した男女雇用機会均等法は一般的にはあまり知られていないので、就業規則で周知する必要があるでしょう。
ハラスメントは重大なコンプライアンス違反となり、被害者の人権を侵害するため、損害賠償請求に応じるケースもあります。
優秀な人材を育成したい場合は、ハラスメント行為の禁止についても就業規則に盛り込んでおきましょう。
従業員を懲戒処分できない
就業規則に懲戒規定を定めなかった場合、問題行動を起こす社員を辞めさせられないリスクがあります。
従業員に無断欠勤や背任などの問題行為があると、減給や降格などの処分にも影響するため、就業規則には必ず懲戒規定を記載しましょう。
罰則がない会社はパワハラや横領などを防ぎにくいので、経営状態を悪化させる原因になります。
定年退職に応じてもらえない
就業規則がなければ、退職に関するルールも曖昧になります。
たとえば、退職規定のない会社が一定年齢を超えた従業員を退職させる場合、会社都合による解雇となってしまいます。
会社都合の退職に正当理由がなければ、訴訟に発展する可能性があるでしょう。
また、民法第627条では、退職の意思表示から2週間後に雇用契約を終了できると規定していますが、実務上は事務引継ぎが間に合わないため、就業規則の整備が必要です。
退職時のトラブルを防止したい場合は、必ず就業規則に退職規定を盛り込んでおきましょう。
残業代や退職金などの請求トラブル
就業規則を作成していなかった場合、残業代や退職金などの請求トラブルに発展する恐れがあります。
たとえば、残業に関する規定がなければ、残業にカウントされるかどうかや、残業代がいくらになるのかをめぐり、労使の意見が対立するでしょう。
残業代の不払いは労働基準監督署の是正勧告を受ける可能性があり、従わなかった場合は書類送検や罰則の対象になりかねません。
退職金の支給に法律上の義務はありませんが、従業員はもらえるものと思っているケースが一般的です。
就業規則には、退職金支給の有無や、支給額の計算方法を盛り込んでください。
労働基準法に違反する恐れがある
就業規則のない会社は賃金や休暇などのルールが曖昧になるため、労働基準法に違反する恐れがあります。
違反行為によっては、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金になる恐れがあり、悪質な場合は刑事事件として扱われます。
社名が公表される可能性もあるため、従業員を雇用した場合は、法的に有効な就業規則が必要です。
就業規則を作成依頼する社会保険労務士の選び方

社会保険労務士は労働関係法に精通しているため、就業規則の作成を依頼できます。
どの社会保険労務士に依頼してよいか迷った場合は、判断基準としては次の4つが挙げられます。
- 最新の法律に対応してくれること
- 経営の意思を反映してくれること
- 作成費用を明示してくれること
- 弁護士との連携で紛争解決にも対応できること
就業規則は従業員の働き方や会社の業績に影響するので、社会保険労務士と十分な打ち合わせを行っておきましょう。
ここからは、就業規則の作成依頼を前提に、社会保険労務士の選び方を詳しく解説します。
最新の法律に対応してくれること
就業規則の作成を社会保険労務士に依頼する際は、最新の法律に対応してくれるかどうかをチェックしてください。
社会保険労務士が法改正に鈍感だった場合、旧法に準拠した就業規則を作成し、労働基準法などに違反する恐れがあります。
法改正には常にアンテナを張り、就業規則に反映してくれる社会保険労務士を選びましょう。
経営の意思を反映してくれること
就業規則には経営者の思いが込められるため、法的要件を満たしているだけでは不十分です。
社会保険労務士を選ぶ際は、社内に定着させたい規律や従業員の成長など、経営者の意思を反映してくれるかどうかも重視してください。
実効性のある就業規則を作成できれば、採用活動や人材育成などに役立ちます。
作成費用を明示してくれること
就業規則を社会保険労務士に作成してもらう場合、従業員数などに応じて費用がかかります。
費用には特に決まった相場がないので、「何を依頼したらいくらかかる」など、作成費用を明示してくれる社会保険労務士を選びましょう。
料金体系が不明確な場合は、割高な費用を請求される可能性があるので要注意です。
弁護士との連携で紛争解決にも対応できること
社会保険労務士を選ぶ際は、弁護士と連携しているかどうかもチェックするとよいでしょう。
弁護士との連携があれば、労使間のトラブルが発生してもスムーズに解決できる可能性があります。
欠勤を繰り返す社員がいる、外国人労働者を雇用するなど、特殊な事情がある場合は、弁護士と連携した社会保険労務士を選びましょう。
就業規則の作成を社労士に依頼したいなら社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談を

どのような会社にも就業規則は必要ですが、法律の専門知識が欠かせないため、簡単には作成できません。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジには社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しており、自社に合った就業規則の作成や改定相談を承っております。
また最新の就業規則作成支援システムを導入しており、お客様とのやりとりもスピーディーです。
就業規則の作成・改定の際には、お気軽に社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。