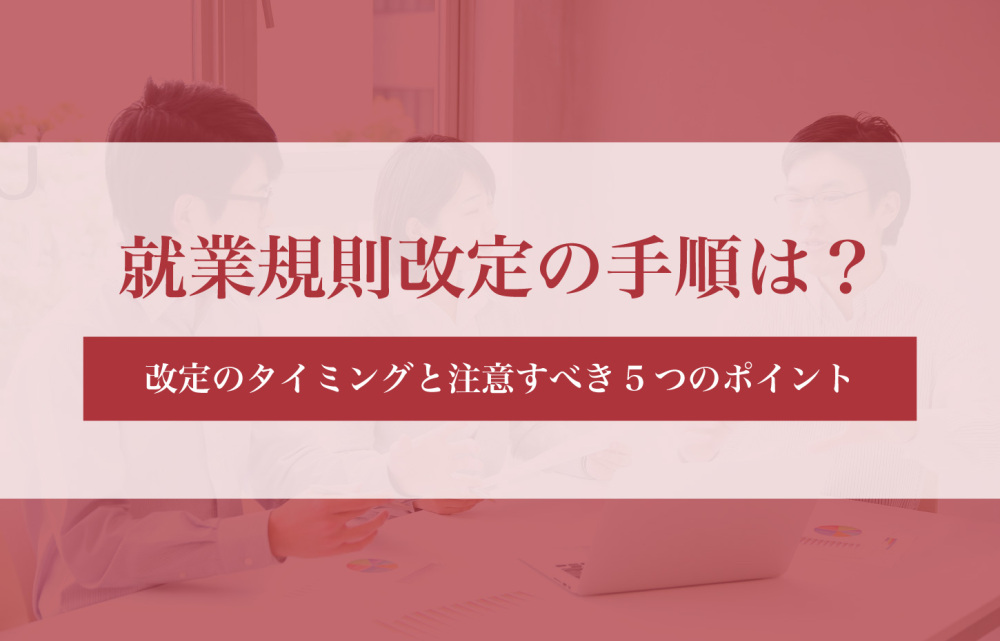INFORMAITION
お知らせ
2025年09月18日
就業規則改定の手順は?改定のタイミングと注意すべき5つのポイント
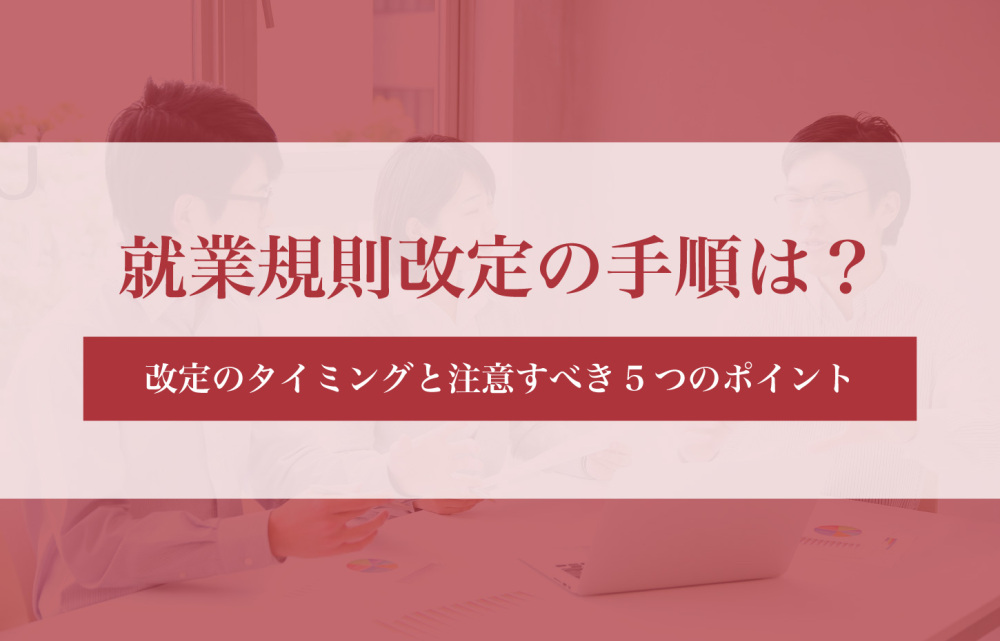
「そろそろ就業規則を見直した方がいい気がするけれど、どこから手をつければいいのかわからない」そのような不安を感じていませんか?
働き方改革やテレワークの普及、法改正によって、企業を取り巻く労働環境は変化しています。
しかし、就業規則は一度作成したまま放置されがち。
実はそのままにしていると、法令違反や従業員とのトラブルにつながる可能性があるのです。
この記事では、就業規則を改定すべきタイミングや具体的な手順、注意点、そしてスムーズに進めるためのコツまで、わかりやすく丁寧に解説します。
就業規則を改定すべきタイミングとは

就業規則は、一度作成すれば終わりというものではありません。法律の改正や働き方の変化、企業の方針転換などに応じて、定期的に見直すことが大切です。
見直しを怠ると、社内ルールが実態と合わず、トラブルの原因になったり、法令違反となって行政からの指導を受けたりすることもあります。
就業規則を改定すべきタイミングは次の通りです。
- 法律が改正されたとき
- 新たな勤務制度(テレワーク・フレックス制など)を導入・変更したとき
- 賃金体系・労働時間などの条件を変更したとき
- 企業の経営状況に変化があったとき
ここからは、就業規則の改定が必要になる主な4つのタイミングを詳しく見ていきましょう。
法律が改正されたとき
法律は、時代に合わせて定期的に改正されます。
たとえば、時間外労働の上限規制、育児・介護休業制度の見直し、ハラスメント防止措置の義務化などが代表的な改正です。
改正内容が就業規則に反映されていないと、法令違反となり、最悪の場合は行政指導や是正勧告の対象となってしまいます。
対応のポイントとしては、法律の改正情報をキャッチしたら、自社の就業規則に該当箇所があるかを確認し、必要があれば速やかに改定しましょう。
新たな勤務制度(テレワーク・フレックス制など)を導入・変更したとき
働き方改革やコロナ禍の影響により、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な勤務制度を導入する企業が増えています。
しかし、こうした制度を導入するには、単に現場で運用を始めるだけでは不十分です。
始業・終業の取扱いや報告ルール、労働時間の管理方法などを、就業規則や協定書に明記する必要があります。
たとえば、以下のような導入・変更がある場合が該当します。
- テレワーク導入時:勤務場所・勤怠管理・費用負担ルールを規定
- フレックス制導入時:清算期間・コアタイム・労働時間の算定方法を明記
制度が曖昧なままだと、労働トラブルや労基署からの指導につながるため、制度変更の際は必ず就業規則を整備しましょう。
賃金体系・労働時間などの条件を変更したとき
賃金制度や労働時間など、社員の働き方に関わる条件を変更する際にも、就業規則の改定が必要です。
たとえば、以下のような変更がある場合が該当します。
- 基本給の支給方法を見直す(職能給→成果給など)
- 固定残業代制度(みなし残業)を導入する
- 所定労働時間を変更する(1日7時間半→8時間など)
賃金体系・労働時間などの条件変更は、従業員の不利益変更と捉えられることもあるため、労使の合意や、丁寧な説明と同意が欠かせません。
就業規則の改定と36協定との関係性
残業や休日出勤をさせるには、会社と労働者代表の間で「36(さぶろく)協定」を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
就業規則で残業時間や勤務時間に関するルールを変更する場合、36協定の内容も同時に見直し、再提出しなければなりません。
たとえば、固定残業代制度を導入する場合、就業規則に「月20時間分の残業代を固定で支給」と記載しただけでは不十分です。
36協定でも、20時間までの残業が可能な体制になっているのが望ましいでしょう。
また、フレックスタイム制に切り替える場合では、就業規則や協定書で清算期間やコアタイムを定めるとともに、36協定でフレックス制に対応した内容(例:清算期間中の総労働時間)を定める必要があります。
就業規則と36協定が連動していない場合、制度運用が「違法」となるリスクがあります。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
引用元:労働基準法 | 第36条
労働時間まわりを改定する際は、必ず両方を確認・整備しましょう。
企業の経営状況に変化があったとき
業績の悪化、組織再編、新事業の開始、M&Aなど、会社の経営状況が変わると、従業員の働き方や処遇も見直す必要が出てきます。
たとえば、「経費削減のために手当を廃止する」「事業統合によって転勤を前提とする職種が増える」「
新部署設立に伴い、勤務体系を変更する」などの変更は就業規則にも反映させておかなければ、「規則と現実にズレがある」として労使トラブルの原因になってしまいます。
手当の廃止や労働条件の不利益変更は、特に慎重な対応が必要です。
就業規則の改定だけでなく、事前の説明や労働者代表との協議、同意を得るなど、適切な手順を踏むことが重要です。
就業規則改定の基本手順

就業規則の改定は、単に「内容を変える」だけでなく、法律に基づいた手順を踏む必要があります。
就業規則改定の手順を間違えると、せっかく作った就業規則が「無効」と判断されるおそれもあるため、注意が必要です。
基本となる7つのステップは次の通りです。
- ステップ1.変更案を検討する
- ステップ2.経営陣の承認を得る
- ステップ3.新しい条文を作成する
- ステップ4.従業員代表者から意見聴取をする
- ステップ5.就業規則を変えるときに必要な意見書など書類を用意する
- ステップ6.就業規則変更届を作成・労基署へ提出する
- ステップ7.従業員への周知を徹底する
ここからは、就業規則改定の手順について詳しく見ていきましょう。
ステップ1.変更案を検討する
まずは、どの条文をどう変更すべきかを明らかにします。
背景には「法律改正」「働き方の変化」「経営方針の変更」など、何らかの理由があるはずです。
変更したい理由に応じて、変更の対象や方向性を整理しましょう。
検討すべきポイントは次のとおりです。
- 労働時間や残業のルールは現行の実態と合っているか
- テレワークやフレックスなどの勤務制度に対応しているか
- 賃金や手当の支給ルールに変更点はあるか
- ハラスメント防止や育児・介護休業など、法改正に対応できているか
可能であれば、労務担当者や顧問社労士の助言を受けながら、実務に合った変更案を作成しましょう。
ステップ2.経営陣の承認を得る
就業規則の変更は、労働者の権利や処遇に関わるため、会社としての意思決定が不可欠です。
法的には経営陣の承認を義務づける規定はありませんが、内部統制や責任の所在を明らかにするためにも、取締役会や経営会議での承認を得ることが一般的です。
特に以下のような変更を行う場合は、必ず経営陣と連携を取りましょう。
- 賃金体系の変更
- 手当や福利厚生の変更
- 新たな評価制度の導入
社内的な信頼性を担保するためにも、「正式な承認」があることを記録に残しておくことが大切です。
ステップ3.新しい条文を作成する
次に、検討した変更案に基づいて、実際の就業規則の条文を作成または修正します。
このとき大切なのは、「あいまいな表現を避け、誰が読んでもルールが理解できる」ように書くことです。
たとえば、「業務の都合により出勤時間を変更することがある」という表現では、どう変更になるのかがわからずあいまいです。
このような場合は、「会社は、業務の都合により前日までに通知したうえで、始業時刻を1時間繰り上げることができる」などのように具体的に書きましょう。
また、過去の改定時の文書や、厚生労働省が公開しているモデル就業規則を参考にすると、法律に即した条文が作りやすくなります。
ステップ4.従業員代表者から意見聴取をする
就業規則を改定する際は、労働者の過半数を代表する「従業員代表」から、書面で意見を聴く必要があります。
意見聴取のポイントは次の通りです。
- 会社側が勝手に代表者を選んではいけません
- 従業員からの推薦や投票で、適切な手続きで選ばれた人が「従業員代表」になります
- 意見書には、賛成・反対のどちらでも構いませんが、意見を聞いたという「事実」が必要です
意見を聴いたあとには、「意見書」を作成し、就業規則の変更届とともに労働基準監督署へ提出します。
ステップ5.就業規則を変えるときに必要な意見書など書類を用意する
就業規則を変更する際には、以下の2つの書類をそろえておく必要があります。
いずれも労働基準監督署への提出に必要な重要書類です。
- 就業規則変更届:就業規則の変更内容を労基署に届け出るための書類。様式第3号(厚労省フォーマット)を使用する。
- 意見書:労働者代表から就業規則の改定に対する意見を記載した書類。必ず「意見を聴取した証明」として添付が必要です。
よくあるミスと注意点としては、日付の不一致です。
「意見書の日付」「変更届の作成日」「施行日」がずれていると、整合性が取れていないと判断されることがあります。
そこで、提出前に、社会保険労務士などの第三者にダブルチェックしてもらうことがポイントです。
また、就業規則変更届や意見書とは異なり、新旧対照表には提出の義務はありませんが、社内で確認できるよう整備しておくと安心です。
ステップ6.就業規則変更届を作成・労基署へ提出する
必要書類がそろい、社内承認が取れたら、就業規則変更届を管轄の労働基準監督署へ提出します。
提出時のポイントは次のとおりです。
- 提出方法: 窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)いずれも可能
- 控えを必ず持参: 窓口提出の場合、控え書類にも「受領印」を押してもらい、提出の証明として保管しておきましょう
- 提出先: 本社や各事業場を管轄する労働基準監督署
ただし、不備があるとその場で差し戻しや修正指導を受けることがあるかもしれません。
事前にチェックリストを使って確認するか、社会保険労務士のサポートを受けると安心です。
ステップ7.従業員への周知を徹底する
最後に、改定した就業規則をすべての従業員に周知することが必要です。
従業員への周知は労働基準法第106条で定められており、周知がなければ就業規則は効力を持ちません。
有効な周知方法は次のとおりです。
- 就業規則を配布する
- 社内イントラネットに掲示する
- 社内共有サーバーや労務室など、従業員が業務中に自由にアクセスできる場所に備え付けていつでも閲覧できるようにする
- 電子データを共有し、アクセス方法を明示する
「PDFを送っただけ」「棚の奥にしまってある」では、周知とは認められない場合があります。
すべての従業員が「閲覧できる状態」であることが重要です。
周知時には、変更内容のポイントを説明する場を設けるなど、従業員の理解を促す工夫も大切です。
就業規則を改定するときの5つの注意点

就業規則の改定は、ただ文章を修正すればよいというものではありません。
法律的な要件や実務上のルールを押さえていないと、せっかく改定しても無効になったり、従業員とのトラブルにつながったりするリスクがあります。
就業規則を改定するときの注意点は次の通りです。
- 不利益変更には「合理性」が求められる
- 意見書が出ない場合は「理由書」で対応することになる
- 事業場ごとの手続きが必要なケースもある
- 周知は配布・社内掲示・電子配信のいずれかで確実に行う
- 変更届の提出は「2部・署名済」で行う
ここからは、実際に改定を進めるうえで押さえておくべき5つの注意点について詳しく解説します。
不利益変更には「合理性」が求められる
就業規則の変更で従業員にとってマイナスになる内容(=不利益変更)を加える場合は、特に注意が必要です。
たとえば、手当の削減、勤務時間の延長、退職金制度の廃止などが該当します。
こうした変更を有効とするには、以下のような「合理性」が求められます。
- 経営上の必要性があるか
- 変更内容が社会的に妥当な水準か
- 従業員に対してきちんと説明・同意を得ているか
ただ「会社が決めたから」と一方的に進めてしまうと、無効と判断されたり、裁判で争われることもあります。
慎重な対応と丁寧な説明が不可欠です。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
引用元:労働基準法 | 第10条
意見書が出ない場合は「理由書」で対応することになる
就業規則を変更する際には、従業員代表から「意見書」をもらうことが原則です。
しかし、実際には「書いてもらえない」「選出方法に問題がある」などで意見書が用意できないこともあります。
そのような場合は、「意見書の提出が困難な事情」として、事情説明を添えた「報告書(説明書)」を提出することになります。
「報告書(説明書)」を提出するといった対応は例外的で、労働基準監督署から選出手続きの正当性を厳しくチェックされるため、やり直しを求められるケースも少なくありません。
「意見書がもらえなかったらどうしよう」と悩む前に、適切な代表者の選出と事前説明を行うことが大切です。
事業場ごとの手続きが必要なケースもある
本社と支社など、複数の「事業場」がある会社の場合、就業規則の変更届は事業場単位で提出しなければならないことがあります。
とくに以下のような場合は注意が必要です。
- 事業場ごとに異なる就業規則を採用している
- 労働者の代表者が事業場単位で選出されている
- 労基署の管轄が異なる地域に複数ある
このようなケースでは、「本社だけでまとめて出せばOK」とはいかないため、煩雑な手続きになります。
事前にどの事業場に届け出が必要か、社労士や労基署に確認しておくのが安全策です。
周知は配布・社内掲示・電子配信のいずれかで確実に行う
就業規則の改定は、「届け出をしただけ」では意味がありません。
すべての従業員に対して周知することが法律上の義務となっています(労働基準法106条)。
周知の方法には、次のような手段が認められています。
- 配布する
- 社内の掲示板に張り出す
- 社内システムやイントラネットにアップして閲覧できるようにする
注意したいのは、ただアップロードしただけでは不十分であること。
「どこにあるか」「どうやって見るのか」をきちんと説明しなければ、周知とは認められません。
説明会を開く、メールで案内するなど、従業員の理解促進もセットで行うことが望ましいでしょう。
変更届の提出は「2部・署名済」で行う
就業規則変更届を労働基準監督署に提出する際には、形式面の不備があると差し戻しになることがよくあります。
とくに次の3点は、非常に差し戻されやすいポイントです。
- 2部提出していない(控え用がない)
- 会社代表の署名が抜けている(※令和3年3月31日以降、押印は不要)
- 意見書に労働者代表の署名がない
また、記載内容の整合性(日付・社名・改定内容)も要チェックです。
「就業規則は改定したのに、提出された書類には古い内容が残っている」といったミスもよくあります。
忙しい時期ほど、書類の形式ミスが起こりやすいため、ダブルチェックを徹底しましょう。
従業員が改定された就業規則に同意しない場合の対応方法

就業規則を改定しても、すべての従業員がすんなり納得してくれるとは限りません。
特に、給与や手当の減額、労働時間の延長など、従業員にとって不利益となる変更がある場合は、「同意できない」と反発されることも珍しくありません。
従業員が改定された就業規則に同意しない場合の対応方法は次の通りです。
- 就業規則の内容が合理的であれば改定できることを覚えておく
- 代替措置・経過措置を講じて納得を得る
ここからは、従業員が就業規則の改定に同意しない場合の対応策を2つのポイントに分けて詳しく見ていきましょう。
就業規則の内容が合理的であれば改定できることを覚えておく
まず大前提として、就業規則の変更にはすべての従業員の「同意」が必要というわけではありません。
労働契約法第10条では、以下のような条件を満たせば、従業員の個別同意がなくても就業規則の変更は「有効」とされています。
変更が有効と認められる条件は次のとおりです。
- 就業規則の変更内容が「合理的」であること
- 従業員にきちんと「周知」されていること
たとえば、働き方改革や法改正に対応するための変更や、会社の経営状況に即した客観的な理由があれば、一部の従業員が反対しても変更は有効になります。
ただし、就業規則の変更内容の「合理性」はあいまいなものではなく、法的判断や判例に基づいた根拠が必要です。
従業員との認識のズレがある場合は、社会保険労務士に相談するのが安心です。
代替措置・経過措置を講じて納得を得る
従業員に不利益となる変更を行う場合、たとえ「合理的」だったとしても、いきなり適用するのはトラブルのもとです。
反発を和らげ、納得感を得るためには、「代替措置」や「経過措置」を設けることが重要です。
具体例は次のとおりです。
- 手当の減額を行う場合:その分、賞与で一時的に補填する(代替措置)
- 休日数の減少する場合:数ヶ月の猶予期間を設けて段階的に変更する(経過措置)
- 評価制度を変更する場合:初年度は旧制度との併用とする(経過措置)
このように、「急にルールが変わると困る」という従業員の不安に寄り添った設計をすることで、納得を得やすくなり、不要な対立や不信感も防げます。
ただし、代替措置や経過措置の設定にも法律上の制約や注意点があるため、社内で判断するのが難しい場合は、労務に強い社労士のサポートがあると安心です。
就業規則の改定をスムーズに進めるための3つのポイント

就業規則の改定は、法律・制度・労使関係など複数の観点を調整しながら進める、想像以上に手間のかかる業務です。
特に従業員に関わる重要なルールを見直す以上、慎重かつ丁寧な対応が求められます。
就業規則の改定をスムーズに進めるためのポイントは次の通りです。
- 早い段階から労働者代表と丁寧なコミュニケーションを取る
- 法改正の最新情報を把握しておく
- 就業規則の専門家(社労士)に相談する
ここからは、改定をスムーズに進めるための3つのポイントについて詳しく解説します。
早い段階から労働者代表と丁寧なコミュニケーションを取る
就業規則を改定する際に、最もつまずきやすいのが従業員側の反発や不信感です。
とくに、手当の見直しや労働条件の変更が含まれる場合、「なぜ変更するのか」「納得できない」といった声が出やすくなります。
だからこそ、初期段階から労働者代表に意見を聞き、改定の背景や目的を丁寧に説明しておくことが重要です。
一方的に通知するのではなく、「対話」を意識することで、従業員の理解と協力を得やすくなります。
結果的に、意見書の取得や社内周知もスムーズに進むため、改定全体のスピードと納得感が変わります。
法改正の最新情報を把握しておく
就業規則は「一度作れば終わり」ではなく、法改正や社会情勢に応じて定期的に見直すことが必要です。
2023年から2023年にかけては、パワハラ・時間外労働の割増賃金率の変更・育児介護休業法の改正などが実施されました。
こうした法改正を見逃してしまうと、就業規則が知らないうちに違法状態になってしまうことも。
従業員からの指摘や、労基署の調査で発覚する前に、法改正の動きをこまめにチェックしておくことが安全対策になります。
就業規則の専門家(社労士)に相談する
就業規則の改定には、法律の知識・書類作成・労基署への提出・従業員対応など、専門的かつ煩雑な作業が多数あります。
慣れていない担当者が一人で対応しようとすると、思わぬミスや時間のロスが発生するリスクも。
そのようなときに心強いのが、就業規則のプロである「社会保険労務士(社労士)」です。
社労士は、法改正の対応や文面のチェック、必要書類の作成はもちろん、従業員代表への説明や労基署対応までトータルでサポートしてくれます。
「改定が必要なのはわかっているけど、正直どう進めればいいかわからない」「社内で進める時間も人手も足りない」そのようなときは、迷わず専門家に相談することが、最もスムーズかつ確実な方法です。
就業規則の改定では「手順」「周知」「合理性」がカギ!

就業規則の改定は、単なる文書の修正作業ではありません。
「法的な手順を守ること」「従業員への確実な周知」「内容の合理性」の3つが揃って、はじめて有効な改定として認められます。
しかし実際には、「どこをどう変えればいいのか分からない」「意見書や届出の処理が不安」「従業員の反発が怖くて動けない」といったお悩みを抱える企業も多いのが現実です。
そのようなときは、労務・規則改定のプロである「社会保険労務士事務所ダブルブリッジ」にお任せください。
社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しており、お急ぎの対応もお引き受けしております。
制度設計から条文の作成、意見書の取得・労基署対応、従業員説明会の運営まで、煩雑な手続きすべてをトータルでサポートします。
「うちの規則、このままで大丈夫?」と感じた今こそ、見直しのチャンスです。
まずはお気軽にご相談ください。