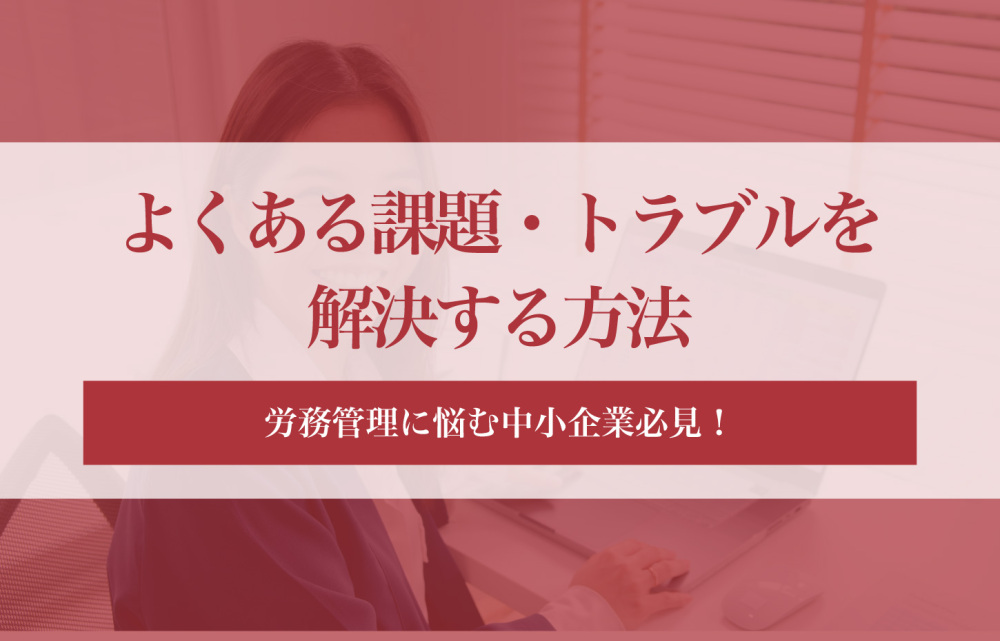INFORMAITION
お知らせ
2025年09月18日
労務管理に悩む中小企業必見!よくある課題・トラブルを解決する方法
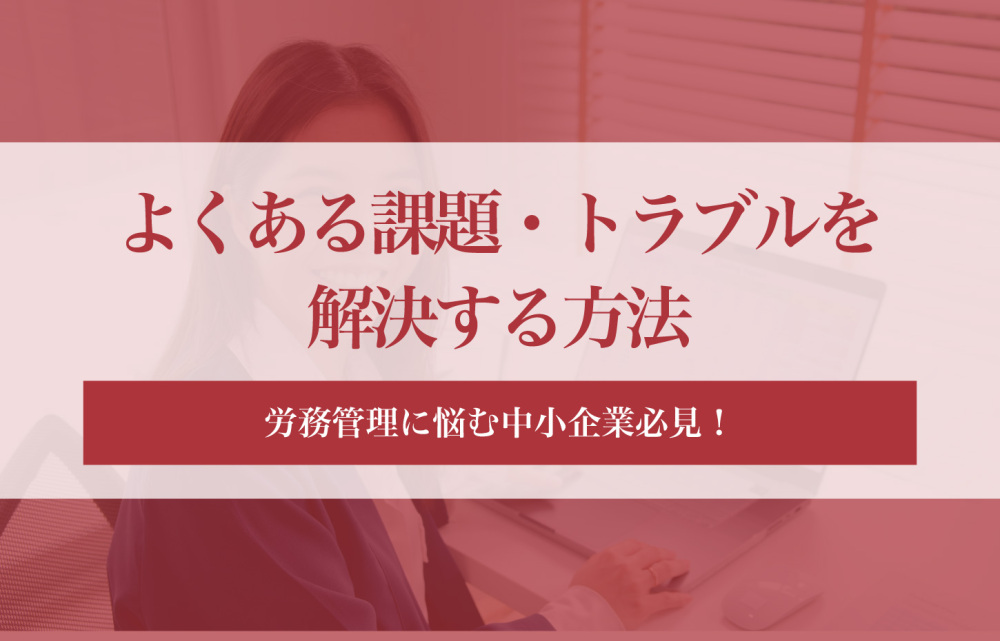
従業員が安心して働くために重要なのが労務管理です。
しかし、中小企業では人手不足や専門知識の欠如から、適切な労務管理ができていないことも珍しくありません。
そんなときに頼りになるのが、労務管理の専門家である社労士の存在です。
本記事では、中小企業ならではの労務管理における課題やトラブルを解説し、社労士に労務管理を委託するメリットを紹介します。
中小企業ならではの労務管理における課題

中小企業は大手企業と違い、限られた人員で業務を分担し進める必要があります。
そのため、以下のように中小企業特有の課題が生じやすいのが特徴です。
- 従業員の状況把握
- 法改正への対応
- 各種手続きに時間がかかる
- 法令遵守
- 手作業によるミス
- 業務過多による退職
- 評価基準が曖昧
- 研修・人材育成の制度
それぞれのケースについて解説していきます。
従業員の状況把握
1つ目の課題は、従業員の状況把握です。
一人ひとりの勤務時間や休憩、有給休暇の取得状況に加え、ストレスチェックや健康診断の受診状況など、把握・管理すべき項目は多岐にわたります。
とくに従業員の人数が多い中小企業は、それぞれの状況把握への対応が難しいでしょう。
業務の属人化や見落とし、ミスなどが課題になりがちです。
残業代の未払いや休憩時間の未確保、健康診断の未受診などは、労働トラブルや法令違反につながるリスクもあります。
法改正への対応
法改正への対応も、中小企業の課題の一つです。
法改正は頻繁に行われることも多く、その都度スピーディーで適切な対応が求められます。
たとえば2023年からは、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用されるようになりました。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法 | 第37条第1項
「知らなかった」では済まされないのが法改正。
最新情報への対応を怠れば、意図せずに法令違反をしてしまうリスクがあります。
日々の業務をこなしながら最新情報を常にキャッチし、法改正への対応をし続けることが、中小企業の課題です。
各種手続きに時間がかかる
中小企業によくある3つ目の課題は、各種手続きに時間がかかる点です。
中小企業は、入退社に関する手続き、産前産後育児休業や傷病手当金、労災に関する手続き、年末調整などの幅広い業務を少人数でこなさなければなりません。
大手企業と違って担当者が少ない企業も多く、一人当たりの負担がより大きくなるでしょう。
業務が集中し、各種手続きに時間がかかる・残業時間が増える・パンク状態になるというリスクが発生しやすくなります。
法令遵守
中小企業は人員不足や法改正へのスピーディーな対応が難しいなどの理由により、法令遵守が困難なことも課題の一つです。
パワーハラスメントやコンプライアンスが重視される一方で、中小企業は専門知識が不足しがちです。
また、具体的なルールや再発防止体制が整っていないケースもあり、問題が起きてから対応する「後手対応」になりやすいといえるでしょう。
その結果、従業員の退職や企業としての信頼性低下につながります。
手作業によるミス
4つ目の課題は、手作業によるミスです。
中小企業のなかには、勤務管理や給与計算をアナログ管理しているところが存在します。
手作業は転記ミスや計算ミスが起こりやすく、従業員からの問い合わせ対応に追われることも。
従業員・担当者双方にとってストレスになるでしょう。
業務過多による退職
5つ目の課題は、業務過多による退職です。
中小企業は従業員の勤務時間や休憩時間・有給休暇などの集計、社会保険や雇用保険の手続き、年末調整の手続きなどを少人数で担当していることもあるでしょう。
業務過多により、担当者が退職を検討することも念頭におかなければなりません。
評価基準が曖昧
評価基準が曖昧になり、公平性に欠ける点も中小企業ならではの課題です。
給与や昇進に関する評価が担当者の主観になってしまうと、従業員のモチベーション低下や退職につながることも。
「何を基準に評価しているの?」「私情で決めているのではないか」と誤解を招く可能性があり、優秀な人材の離職にもつながりかねません。
研修・人材育成の制度
中小企業では、研修や人材育成の制度が整っていないことも多くあります。
研修期間を設けていない・新人教育係がいないなど、一人ひとりに対して支援することが難しい企業も多いでしょう。
新人教育に専念できる人員を確保できず、知識や経験が不十分のまま働くことになるため、早期退職や定着率の低下につながります。
中小企業の労務管理におけるよくあるトラブル

労務管理は、企業と従業員の双方が安心して働くために欠かせない基盤です。
しかし、中小企業ではさまざまな要因から労務管理を疎かにしてしまい、トラブルに発展するケースが少なくありません。
中小企業の労務管理におけるよくあるトラブルは、以下のとおりです。
- 残業代の未払い
- 有給休暇の取得
- 退職・解雇問題
- ハラスメント
- 労働条件の変更
順番に解説するのでぜひ参考にしてください。
残業代の未払い
中小企業で多く見られるのが、残業代の未払いによるトラブルです。
労働基準法では、1分単位で賃金を支払うことが適切とされています。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
引用元:労働基準法 | 第24条
しかし、15分単位や30分単位で残業時間を計算し、満たない場合は切り捨てて残業代を計算しているケースが多くあります。
「従業員は納得してくれている」と思っていても、退職後に残業の未払いを訴えられる事例も。
告発があった場合は、他の従業員の残業時間や支払い状況まで徹底的に調査が行われ、残業の未払いが発覚した際は当然支払いを求められます。
従業員の労働時間の管理には十分な注意が必要です。
有給休暇の取得
2つ目のよくあるトラブルは、有給休暇の取得です。
6ヶ月以上勤務に加えて、全労働日の8割以上出勤している従業員には、正社員・パート問わず有給休暇を付与することが労働基準法によって定められています。
2019年4月には「年5日の年次有給休暇の取得義務化」も施行されました。
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
引用元:労働基準法 | 第39条第7項
しかし、中小企業では「忙しい」「人手不足だから」と、有給休暇の取得を妨げてしまうケースがあります。
「有給休暇をとらせてもらえない」「誰も取得していないから言い出せない」と従業員が不満に感じる場合、トラブルやモチベーション低下、退職につながりかねません。
企業全体で有給休暇の取得を促進する意識をもつことが大切です。
退職・解雇問題
退職や解雇問題も、中小企業によくあるトラブルの一つです。
中小企業では、経営者と従業員の距離感が近い場合もあるでしょう。
また「きちんと働いてくれない」「他の従業員に悪影響だ」と感じる従業員がいることもあるかもしれません。
しかし労働基準法では解雇に関する取り決めが厳しいため、一方的な解雇はもちろん、従業員が「解雇された」と感じるような言動は控えなければなりません。
カッとなっても「明日から来なくていい」「もう辞めろ」などの発言は、不当解雇とみなされる恐れがあるため、絶対に避けるよう注意しましょう。
また、円満退職したと思っていても、退職後に「解雇された」と主張され、労働基準監督署や裁判所に訴え出られるリスクもあります。
従業員の退職・解雇については、誤解のないように慎重に進める必要があります。
ハラスメント
パワハラ・マタハラ・セクハラなどのハラスメントに関するトラブルも、中小企業では多くあります。
有効なハラスメント対策は以下のとおりです。
- 相談窓口の設置
- 企業全体での周知
- 再発防止策の実施
昨今はハラスメントに対する対応が重要視されているため、対策を怠れば企業の信頼性低下につながるでしょう。
場合によっては、企業責任を問われることもあります。
ハラスメントへの関心は強まってきており、しっかりとした対策を行うことが大切です。
労働条件の変更
労働条件の変更も、中小企業でトラブルになりやすい事例の一つです。
たとえば、以下のように従業員にとってマイナスになる労働条件の変更には注意が必要です。
- 基本給の減額
- リフレッシュ休暇の廃止
- 休日の削減
- 休職期間の短縮
経営上仕方なく判断した場合でも、従業員にとってマイナスになる変更は、トラブルに発展する可能性があります。
労働条件を変更する際は十分な説明と従業員からの合意を得て、慎重に進めていきましょう。
中小企業の労務管理には社労士がおすすめ

社労士は直近の合格率が6〜7%とされる難関の国家資格です。
厳しい試験を突破した社労士は、まさに人事・労務管理の専門家です。
業務内容は以下のように多岐にわたります。
- 社会保険・雇用保険の手続き代行
- 帳簿書類の作成
- 労務管理に関するコンサルティング
- 就業規則の作成・変更
- 給与計算
- 労務相談
中小企業にとって社労士は、経営を共に支えるパートナーです。
自社の状況に合ったサポートを受けることで、健全な運営や企業の成長につながるでしょう。
中小企業の労務管理を社労士に委託するメリット

中小企業の労務管理を社労士に委託するメリットは、以下のとおりです。
- 主要業務に集中できる
- スピーディーかつ適切な対応をしてくれる
- 情報収集がスムーズにできる
- トラブル発生のリスクを軽減できる
- 強固なセキュリティ体制がある
1つずつ解説するので、確認していきましょう。
主要業務に集中できる
1つ目のメリットは、主要業務に集中できる点です。
労務管理には、多くの専門知識と労力が必要になります。
日々の業務をこなしながらすべてに対応するのは、担当者にとって負担になるでしょう。
社労士に委託することで、経営者や担当者は労務管理から解放され、主要業務に集中できます。
負担軽減、業務の効率化、生産性の向上につながり、注力すべき業務に集中できるようになるでしょう。
スピーディーかつ適切な対応をしてくれる
労務管理の専門家である社労士に委託することで、法改正や制度変更などにスピーディーかつ適切な対応が叶います。
労務関連のルールは頻繁に変更されるため「対応しきれない」「ついていけない」と悩む経営者や担当者は少なくありません。
常に最新情報をキャッチし、適切に判断・対応してくれる社労士は、企業にとって心強い存在です。
最善の策を講じることによって、ミスやトラブルの回避にもつながるでしょう。
情報収集がスムーズにできる
情報収集がスムーズにできるのもメリットです。
助成金や補助金制度、労働法改正などの情報を常に収集するのは、並大抵のことではありません。
社労士に委託すれば、的確に情報収集を行い、自社に合ったアドバイスを受けられます。
制度の注意点や活用方法などの疑問点をすぐに解消することも可能です。
情報収集を社労士に任せて業務に集中できるのは、企業にとってメリットだといえるでしょう。
トラブル発生のリスクを軽減できる
トラブル発生のリスクを軽減できるのも、社労士に委託するメリットの一つです。
労務関連のミスはトラブルに発展するケースが多くあります。
倒産増加が背景にあり、2023年度(4-3月)の支給者数は2万4,300人と前年度から約1万人増えた。
引用元:東京商工リサーチ|「未払賃金立替払」、倒産増で23年度は2万4000人に大幅増
社労士は労働条件の明確化やマニュアルの整備、従業員へのコンサルティングを通して、トラブルを未然に防いでくれます。
とくに残業代の未払いは労働基準法違反に該当します。
ハラスメントは安全配慮義務違反として損害賠償の対象になる可能性があるため、労務管理の専門家に任せるのが大切です。
強固なセキュリティ体制がある
社労士には強固なセキュリティ体制があるため、情報漏洩を防げるのもメリットといえるでしょう。
社会保険労務士には、社会保険労務士法第21条に基づく守秘義務が課されており、情報漏洩リスクの抑制が図られています。
(秘密を守る義務)
第二十一条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
引用元:社会保険労務士法 | 第21条
労務管理をするうえで、従業員の個人情報や企業の機密情報などの、極めて重要なデータを取り扱います。
そのため、労務管理には強固なセキュリティ対策が必要不可欠です。
社労士に委託すれば情報漏洩を防ぎ、安心して業務を進められます。
中小企業の労務管理のために社労士を選ぶ際のチェックポイント

中小企業が社労士に委託することで、安心と業務の効率化、トラブル防止などさまざまなメリットがあります。
しかし、その効果を最大限に発揮するためには、どのような社労士を選ぶかが重要です。
社労士を選ぶ際は、以下のチェックポイントに注目しましょう。
- 自社の業界での経験・知識が豊富か
- レスポンスや対応がスピーディーか
- 「相性が良い」「相談しやすい」と思えるか
- 最新ツールを活用しているか
- サービスの範囲は広いか
- 費用が相場内であるか
順番に解説するのでぜひチェックしてください。
自社の業界での経験・知識が豊富か
社労士を選ぶ際に大切なのは、自社の業界に対してどれくらい理解度があるかです。
業界によって労務管理における課題やトラブルの傾向は異なります。
できるだけ自社の業界での経験・知識が豊富な社労士を選びましょう。
自社の業界での経験・知識が豊富な社労士を選べれば、より実践的で的確なアドバイスに期待できます。
レスポンスや対応がスピーディーか
日々業務をするうえで、迅速な対応が求められる場面は多くあります。
対応が遅ければ、事態が悪化し収拾がつかなくなってしまうことも。
レスポンスや対応が早く、柔軟かつ適切に対応してくれる社労士を選びましょう。
「相性が良い」「相談しやすい」と思えるか
相性の良さや相談のしやすさも重要なポイントです。
どんなに経験や知識が豊富でも「相談しにくい」「話しかけにくい」と感じる社労士とでは業務が進めにくいでしょう。
打ち合わせの際に、親身になってアドバイスしてくれる社労士なのか見極めることが大切です。
最新ツールを活用しているか
昨今、労務管理はDX化が進んでいます。
最新ツールを活用している社労士であれば、業務の効率化に期待できます。
最新ツールに対応しているのかは、社労士を選ぶうえで重要な判断材料になるでしょう。
業務の効率化や自動化を視野に入れているなら、最新ツールを活用しているのか確認するのがおすすめです。
サービスの範囲は広いか
労務に関する業務は幅広くあるため、どれくらいのサービスに対応しているかも、社労士を選ぶうえで重要なポイントです。
就業規則の作成や各種保険の手続き、助成金や労務トラブルへのサポートなど、社労士に求めるサービスが企業によって異なります。
幅広く対応している社労士であれば、将来的な課題にも柔軟に対応してくれるでしょう。
費用が相場内であるか
支払う費用が相場内かどうかも必ず確認しましょう。
安すぎても不安になりますが、高すぎるとコストパフォーマンスが悪くなり、継続依頼が難しくなります。
どれくらいの費用が発生するのか、どのサービスに追加料金が発生するのかなどを比較し検討するといいでしょう。
中小企業の労務管理には社労士がベスト!体制を整え従業員と企業を守ろう

限られたリソースのなかで労務管理を行う中小企業にとって、スムーズに対応するのは限界があります。
労務管理の専門家である社労士に委託し、複雑な法改正や手続き、トラブル対応などを任せましょう。
社労士に委託すれば、本来の業務に集中し、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジは、社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しております。
基本業務、助成金活用サポート、人材育成など幅広く対応できるので、安心して業務に注力できます。
なかでもDX化支援や障害年金申請の代行、外国人やモンスター社員への対応に特化しています。
労務管理を外注したい方、社内規則を整えたい方、他の社労士事務所が苦手あるいは手におえない顧客を抱えている方はお気軽にご相談ください。
お問合せはこちらから。