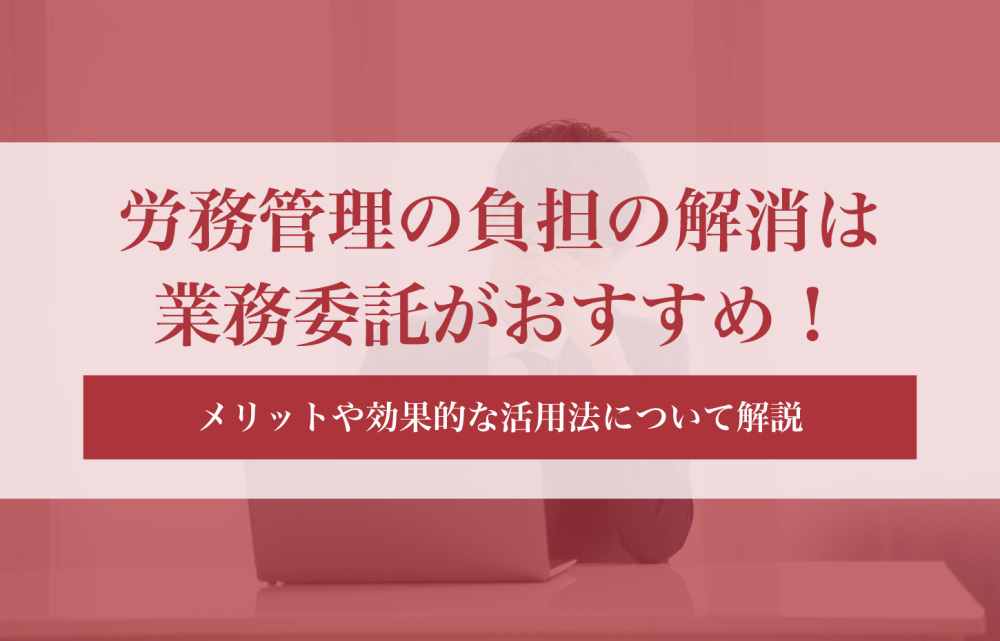INFORMAITION
お知らせ
2025年09月18日
労務管理の負担の解消は業務委託がおすすめ!メリットや効果的な活用法について解説
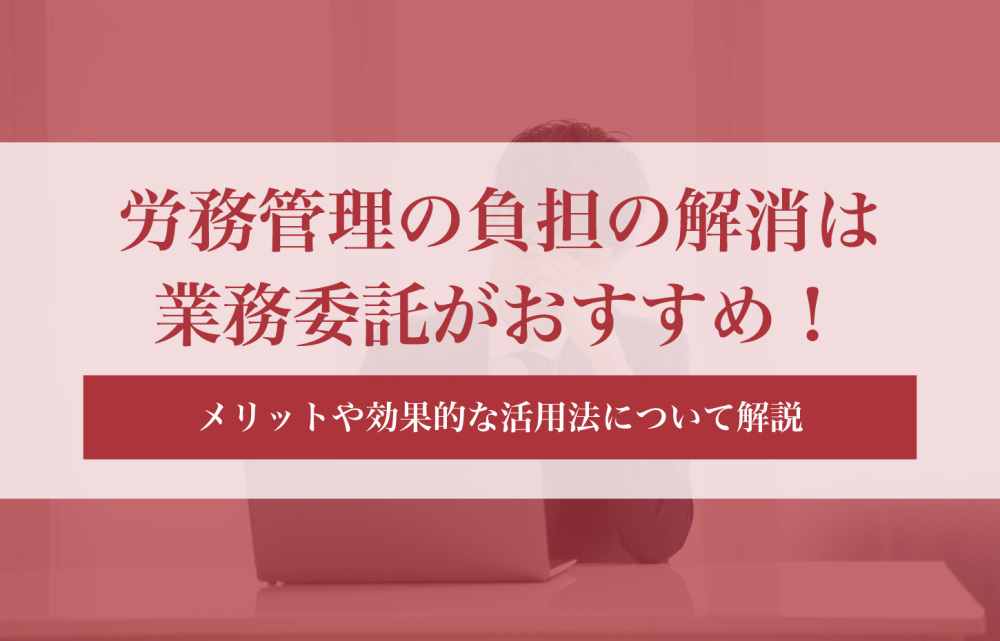
法改正への対応や専門知識の不足、人材確保の困難さなどに課題を感じている中小企業も多いのではないでしょうか。
労務管理は、従業員の雇用から退職まで継続的に対応する重要な業務です。
そんな中小企業の経営者に向けて、当記事では労務管理の課題を解決する「外部委託の活用」について詳しく解説します。
中小企業が労務管理を外部委託したい場合によくある課題

多くの中小企業では労務管理に関して次の表のような問題が発生し、経営者や業務担当者の負担となっている実情があります。
| よくある課題 | 内容 |
|---|---|
| 法改正への対応 | 労働基準法や社会保険制度の頻繁な改正に追いつけない |
| コンプライアンス対応 | ハラスメント対策や、労働基準監督署から受ける調査・是正勧告への対処が難しい |
| 人材不足 | 労務管理の専門知識を持つ人材の確保が難しい |
| 業務負荷の増大 | 給与計算や各種手続きに多くの時間を要している |
| DX・テクノロジー活用の遅れ | 効率的なシステムの導入や効果的な運用ができていない |
こうした課題は相互に関連するものでもあり、1つの問題が生じることによって別の問題まで生じるケースは珍しくありません。
たとえば「人材不足」の問題を解決できずにいると「業務負荷の増大」を引き起こす可能性があり、「法改正への対応」ができずにいると「コンプライアンス対応」も困難になってしまいます。
そこで労務管理に関する課題には、包括的な解決策を検討することが重要といえるでしょう。
労務管理の課題解決方法!委託・代行・アウトソーシングの使い分けがカギ

労務管理の課題を解決する方法として、次の4つが挙げられます。
- 労務管理システムの導入
- オンラインアシスタントサービスの活用
- 専門人材の雇用
- 社労士事務所へのアウトソーシング
それぞれの特徴と適用場面について詳しく見ていきましょう。
労務管理システムの導入
給与計算や勤怠管理、各種申請などを統合的に管理できるソフトウェアがあります。
このソフトウェアを社内で導入し、業務をシステム化することにより、手作業によるミスの削減と業務効率の向上が期待できます。
ただし、システムの選定や導入には相応の初期投資が必要となり、効果を十分に発揮するには従業員が操作方法を理解しなければなりません。
また、「法改正に対応したアップデートが適切に行われるかどうか」など、システムの選定にも留意しなくてはなりません。
オンラインアシスタントサービスの活用
オンラインアシスタントサービスは、インターネットを通じて労務管理業務の一部をサポートするサービスです。
データ入力や書類作成など比較的単純な作業を外部に委託して、社内リソースをより重要な業務に集中させることができるでしょう。
費用が比較的安価である点はメリットといえますが、専門性の高い業務に対応できない場合があります。
特に社会保険労務士法(※)で独占業務として法定されている範囲については社労士資格を持つ者でなければ対応できませんので、利用可能範囲には十分注意してください。
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
引用元:社会保険労務士法 | 第27条
専門人材の雇用
社会保険労務士資格を持つ人材、労務管理の経験豊富な人材を直接雇用するという方法もあります。
社内に専門性の高い人材がいると、対応も迅速になり、業務の質も向上することが期待できます。
しかしながら、人材確保の難しさや人件費の負担は大きな課題となるでしょう。
特に中小企業では、「専門家を常勤で雇用するだけの予算を割けない」「優良な人材が集まらない」というケースも多いです。
社労士事務所へのアウトソーシング
社労士事務所にアウトソーシングするという方法もあり、この方法では専門性の高い対応とコストパフォーマンスの両立が図れるケースが多く見られます。
社労士の独占業務を含む幅広い業務に対応でき、法改正への対応も迅速に行えます。
また、必要なときに必要な分のサービスを利用でき、コスト効率も上げられるでしょう。
さらに、複数の専門家が在籍する事務所であれば、1人の専門家の得意分野に限定されることなくより多様な案件にも対処していくことも可能です。
労務管理について外部委託できる業務内容

労務管理について外部委託するとき、次のような業務を専門業者に依頼することができます。
| 業務区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 基本的な労務管理業務 | 給与計算、勤怠管理システムの運用、社会保険の手続き、労働保険の手続き、給付金申請 |
| 制度設計に関連する業務 | 就業規則の作成・改訂、賃金規程の策定、労使協定の作成 |
| コンプライアンスへの対応業務 | 労働基準監督署や年金事務所への対応、是正勧告への対応、契約書の作成 |
| その他の専門的な業務 | 助成金・補助金申請のサポート、労働紛争の予防、人材育成や研修、メンタルヘルス対策 |
ただし、社会保険・労働保険に関する申請書の作成や提出代行、就業規則の作成などは社労士の独占業務とされているため必ず有資格者が担当しなくてはなりません。
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
委託先の選定時には、業務に対応する資格に関しても十分な確認が必要です。
労務管理人材の「雇用」「外部委託」の違いを費用面含めて解説

労務管理業務を処理する方法として、専門人材を「雇用」するのと「外部委託」するのとでは大きな違いがあります。
雇用契約を締結する場合、指揮命令のもと労働者に業務を遂行してもらうことができますが、労働者に対する法的保護は手厚く、減給や解雇などは簡単にできません。
一般的に、1人につき1年で400万円~600万円程度のコストが継続的にかかり続けます。
また、社会保険料等の法定福利費に加え、育成の負担なども発生します。
一方の外部委託では、業務の遂行方法に対して細かく指示することはできませんが、労働法の適用がないため契約内容の変更や解約なども比較的容易です。
ただし唐突な解約は、民法の規定に従い、相手方がすでに進めていた割合で報酬の支払い義務が生じることもありますし避けなくてはなりません。
(受任者の報酬)
第六百四十八条
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
引用元:民法 | 第648条第3項
コストは委託内容・範囲・従業員数によって異なるものの、中小企業であれば月額数万円程度が相場とされています。
ただし、外部委託をする場合でも業務内容やサポート範囲はよく確認しなければ費用倒れとなる可能性がありますので、安さだけに着目して判断することは避けましょう。
労務管理を外部委託する5つのメリット

労務管理の外部委託は、企業運営に大きな効果をもたらします。
特に大きなメリットとして次の5つが挙げられます。
- 業務ミスの削減・品質向上
- 法改正対応の迅速化
- コア業務への集中促進
- 人材採用・教育の負担軽減
- コスト削減
以下では、こうしたメリットがもたらす具体的な効果について詳しく見ていきましょう。
業務ミスの削減・品質向上
専門業者への委託により、自社で処理する場合によく発生する給与計算のミス、社会保険料の計算ミス、各種届出の期限遅れなどを防ぎやすくなります。
こうしたミスは従業員の不信を招くだけでなく、労働基準監督署からの指導や追徴金の発生といったリスクにもつながるため注意しなくてはなりません。
この点、プロが担当すれば一定水準以上の品質維持が実現されるでしょう。
法改正対応の迅速化
労働法や社会保険制度は頻繁に改正が行われており、その都度適切な対応が求められます。
自社で情報収集するのは大変な作業ですが、専門業者であれば常に最新の法改正情報を把握しているため、自社の手間が省けます。
改正内容の理解や実務への反映も、専門知識を持つプロが迅速に対応してくれるでしょう。
こうして法改正への対応遅れによるリスクを回避し、安心して事業運営に集中できる環境が整います。
コア業務への集中促進
労務管理業務を外部委託することで、経営者や従業員がより重要な業務に時間を割けるようになります。
営業活動や商品開発、顧客サービスの向上など、売上に直結する業務にリソースを集中できる点は大きなメリットといえるでしょう。
特に中小企業では、限られた人材で多くの業務をこなす必要があるため、業務の選択・集中は生産性を上げるための鍵となります。
人材採用・教育の負担軽減
労務管理の専門人材を採用する場合、求人活動から面接、入社後の教育まで、多くの時間とコストが必要です。
しかし、外部委託を活用すればこうした負担を大幅に軽減できます。
即座に専門的なサポートが受けられ、労務管理に対する不安もすぐに解消されるでしょう。
ただし、社内の人材育成自体は企業の成長にとって大事な要素であることに変わりはありません。
コスト削減
外部委託により、労務管理にかかる総コストを削減できる可能性があります。
実際、人件費と比較すれば外部委託の方が経済的となるケースは多いです。
特に従業員数が少ない企業だと、専任の担当者を雇用するより外部委託した方が費用対効果は高くなる傾向にあります。
ただし、委託内容や契約条件によっては費用が想定以上にかかる場合もあるため、事前に料金体系をよく確認しておくことが大事です。
労務管理を外部委託するときの注意点

労務管理を外部委託することには多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべきポイントも存在します。
特に注意しておきたいのはこちらの点です。
- 「丸投げですべて解決」とはならない
- 委託先ときちんと連携する
- 委託先を慎重に選定する
- 業務委託契約書に基本項目をしっかり記載する
- 情報漏えい・個人情報管理対策をする
- 労働者派遣や偽装請負にならないようにする
各注意点の詳細を見ていきましょう。
「丸投げですべて解決」とはならない
外部委託を行ったとしても、労務管理に関する最終的な責任は企業側にあることを理解しておく必要があります。
委託先にミスや対応遅れがあったとしても、従業員や関係機関に対する責任は基本的に企業が負います。
そのため、委託先任せにするのではなく、適切な管理監督を実施する姿勢を意識してください。
定期的な報告や進捗確認を通じて、業務の状況を把握する体制を整えておくと良いでしょう。
委託先ときちんと連携する
外部委託に成功して期待する効果を得るには、委託先との連携が不可欠です。
コミュニケーションが上手く取れていないと、手続きの遅れや誤った処理が発生するリスクが高くなります。
たとえば連絡手段が確立されておらずメッセージの行き違いなどがあると、効率的に業務が遂行できません。
自社が書類を渡さないといけない日、委託先が必要な作業を終えなければならない日など、互いに期限を定めて適切にルールを運用していく体制も重要です。
定期的な打ち合わせを行い、双方向の情報共有を心がけましょう。
委託先を慎重に選定する
労務管理の委託先選びが、その後の業務品質に大きく影響します。
「オンラインアシスタントサービスの利用」「人材の雇用」「社労士事務所への委託」など同じカテゴリのサービスでも、個々の業者によって専門性や対応力には大きな差があるためです。
そこで料金の安さだけで選ぶのではなく、実績や専門性、サポート体制を総合的に評価しましょう。
複数の候補を比較検討し、自社のニーズにもっとも適した委託先を選択することも大事です。
業務委託契約書に基本項目をしっかり記載する
外部委託にあたっては、契約書を作成すべきです。
このとき作成する業務委託契約書には、トラブル防止のための基本的な項目、たとえば業務範囲・報酬体系・契約期間・責任分担・秘密保持・再委託の有無などは漏れなく含めるようにしましょう。
記載方法についても、曖昧な表現を避け、具体的かつ詳細に記載することが重要です。
契約の内容が不明瞭だと、後々のトラブルや追加費用の発生につながるリスクが高まってしまいます。
情報漏えい・個人情報管理対策をする
労務管理業務を遂行する過程では、従業員のマイナンバーなど個人情報を多く取り扱います。
そこで、委託先で情報セキュリティ対策が適切に施されていることも確認しましょう。
具体的には、アクセス制限が適切になされているか、データの保管方法について適切なルールがあるか、情報を破棄するときの手順が適切か、といったポイントをチェックします。
必要に応じて業務委託契約書に情報管理に関わる条項を盛り込むことも検討しましょう。
労働者派遣や偽装請負にならないようにする
外部委託においても、業務の進め方に注意しなければ各種労働関連法に抵触するおそれがあります。
たとえば、発注者側が委託先の従業員に対して直接指揮命令を行ってしまうことで、違法な労働者派遣と評価されることも考えられます。
そのため、業務に対する指摘があるときでも必ず委託先の責任者との話を通じて問題解決を図りましょう。
違法と評価されることには行政指導や罰則が適用されるリスクがあるため、自社と委託先との間で適切な業務分担・責任体制を構築すべきです。
失敗しない労務管理委託先の選び方・チェックポイント

労務管理の外部委託で失敗しないためには、上記の注意点を意識するほか、「適切な委託先を選ぶこと」が大事です。
そして、委託先を選定する際には次の3つの点をチェックしましょう。
- 対応可能な業務範囲がどうなっているかで選ぶ
- 料金体系の透明性で選ぶ
- システム連携・DX支援への対応力で選ぶ
各チェックポイントについて、具体的な確認方法を紹介していきます。
対応可能な業務範囲がどうなっているかで選ぶ
委託先選定にあたってのチェックポイントの1つ目は「委託先の専門分野と対応可能な業務範囲の詳細」です。
社労士が在籍しているか、独占業務への対応は可能か、といった基本的な確認から始めましょう。
また、給与計算、各種手続き、就業規則作成、助成金申請など、自社で必要な業務をカバーしてもらえるかも確認します。
サポート体制に関しても、緊急時の対応や相談窓口の有無など、具体的なサービス内容を把握しておくことが大切です。
料金体系の透明性で選ぶ
チェックポイントの2つ目は「料金の算定方法と内訳が明確に示されているか」です。
月額固定制、従業員数連動制、業務単価制など、料金体系は委託先によって異なります。
初期費用の有無、追加業務が発生した場合の料金設定、契約期間による割引制度などもそれぞれで異なります。
どのような仕組みで具体的な金額が定まり、そして自社が依頼したとき実際にいくらかかるのかを把握していくと、比較検討も進めやすくなるでしょう。
また、単に安いか高いかだけで判断するのではなく、費用対効果にも着目すべきです。
システム連携・DX支援への対応力で選ぶ
労務管理の効率化には、IT活用が不可欠です。
そこで業務システムの利用を前提に、3つ目のチェックポイントとして「委託先が労務管理システムの導入・運用やDX化にも対応できるか」にも着目しましょう。
労務管理のDX化支援やシステム導入のアドバイスを受けられる環境は、今後業務を効率的に進めていくためにも重要なポイントです。
将来を見据えて、テクノロジー活用に積極的な委託先を選択することが望ましいでしょう。
労務管理の外部委託は社会保険労務士事務所ダブルブリッジにお任せください

この記事では、労務管理の負担を解消する方法について解説しました。
労務管理の外部委託を検討中であれば、社会保険労務士事務所ダブルブリッジにぜひご相談ください。
社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しており、「DX化支援」「就業規則改定」「障害年金申請の代行」を得意とするほか、労務管理業務を網羅的にサポートできます。
ほかの社労士事務所では対応が困難な案件についても、弁護士や他士業との連携により解決いたします。
お問合せはこちらから。