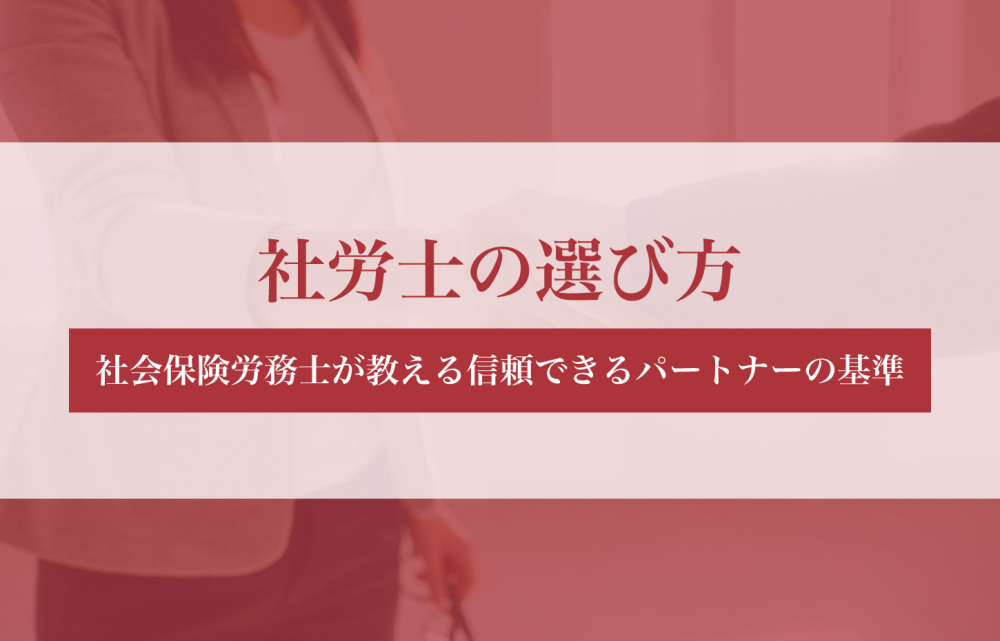INFORMAITION
お知らせ
2025年07月25日
社労士の選び方!社会保険労務士が教える信頼できるパートナーの基準
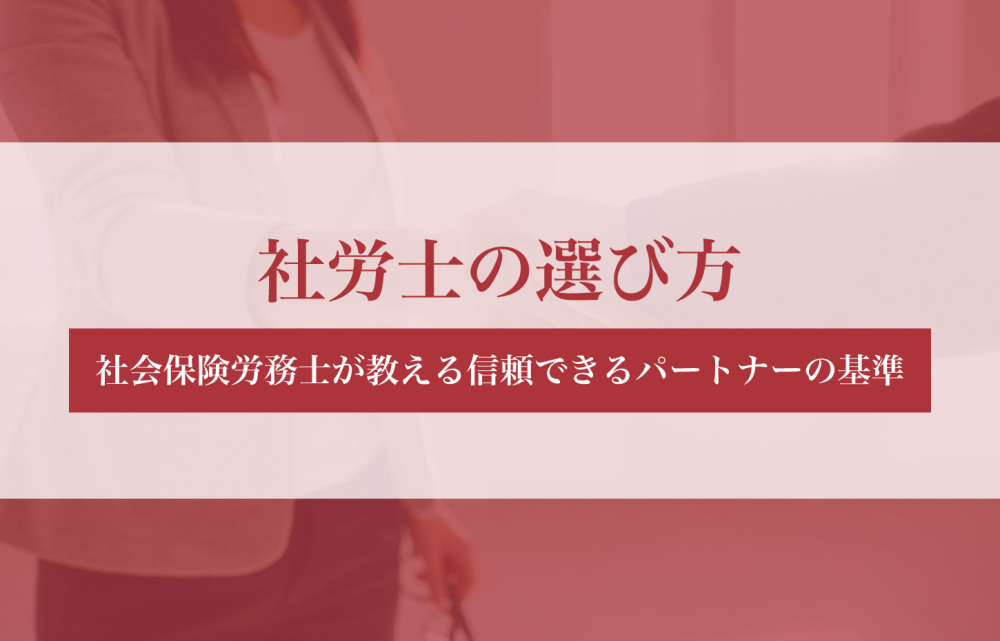
社労士に依頼したいけれど、「どこを見て選べばいいのかわからない」「後悔したくない」と悩んでいませんか?
実は、社労士選びで失敗したという声は意外と聞かれます。「料金だけで決めてしまった」「相談しづらい人だった」など、あとから不満を感じるケースも少なくありません。
社労士は会社の労務管理を任せる重要なパートナーです。
だからこそ、自社に合った信頼できる人を選ぶことで、労務トラブルの予防や従業員対応の迅速化が実現し、経営の安定にもつながります。
この記事では、中小企業の経営者が社会保険労務士の選び方を考える上での失敗パターンと、失敗しないためのチェックポイントをわかりやすく解説します。
社会保険労務士の選び方を考える上での9つの失敗パターン

社労士は、会社の人に関わる大切なパートナーです。
しかし、よく考えずに契約してしまうと、「思っていたサポートが受けられなかった」「余計な費用がかかった」と後悔することも少なくありません。
中小企業の経営者がついやってしまいがちな社労士選びの失敗パターンは次のとおりです。
- 料金だけで選んでしまう
- 近さだけ・紹介されたからというだけで決めてしまう
- 契約条件や費用の説明が曖昧なまま契約してしまう
- 一度も面談をしていないで決めてしまう
- 話しづらさや相性の悪さを無視してしまう
- 質問に答えられない社労士を選んでしまう
- ITやクラウド対応の可否を確かめず決めてしまう
- 業種や事業規模に合っていない社労士を選んでしまう
- 他士業との違いを理解せず選んでしまう
ここからは、社労士選びの9つの失敗パターンについて詳しく解説します
料金だけで選んでしまう
「とにかく安い社会保険労務士にしよう」と料金だけを重視して決めてしまうと、必要なサポートが受けられなかったり、トラブル時に対応が不十分だったりするリスクがあります。
たとえば、月額顧問料が安くても、相談は月1回までとか、手続きは別料金というケースも。
社会保険労務士は、料金の安さだけでなく、「何をどこまで対応してくれるのか」を確認して総合的に判断することが大切です。
近さだけ・紹介されたからというだけで決めてしまう
「自宅やオフィスから近いから便利そう」「知人に紹介されたから安心」といった理由だけで社労士を選ぶのは危険です。
確かに物理的に近いことや、紹介者がいることは安心材料ではありますが、社労士にも得意・不得意があります。
たとえば、製造業に強い社労士と、医療・福祉に強い社労士では、対応できる内容やアドバイスの質が異なります。
そのため、距離や紹介だけを理由にせず、「自社の業種・課題に対して的確なサポートができるか」を重視しましょう。
ホームページや事例紹介、初回面談を通じて、相性や実績を客観的に判断することが重要です。
契約条件や費用の説明が曖昧なまま契約してしまう
社労士と契約する際、「あとで正式な契約書を出します」「一応この内容で進めておきますね」と言われて、詳細が曖昧なまま依頼してしまうケースがあります。
詳細が曖昧なままの依頼は非常にリスクが高く、後から「その対応は別料金になります」「それは契約範囲外です」などと追加費用を請求されるトラブルに発展することも。
こうした事態を防ぐためには、顧問料やスポット料金、対応範囲などを事前に文書で提示してもらうことが大切です。
見積書や契約書の内容を読み込み、わからない点は遠慮なく質問しましょう。
説明が曖昧だったり、書類を出したがらない社労士は要注意です。
一度も面談をしていないで決めてしまう
ホームページや料金表だけを見て、社労士と一度も面談せずに契約を決めてしまうのは危険です。
「評判が良い」「専門性が高そう」と感じても、実際に会ってみないと分からないことがたくさんあります。
たとえば、話し方の雰囲気や対応スピード、相談への姿勢などは、面談を通して初めて見えてくるものです。
契約前に少なくとも1回は対面やオンラインでの面談を行い、「この人に安心して相談できそうか」を自分の目と耳で確認しましょう。
話しづらさや相性の悪さを無視してしまう
「専門知識があるなら、多少話しづらくても仕方ない」と思って契約してしまうと、後々のストレスになります。
社労士には、給与・労務・人間関係などデリケートな話を相談する場面が多くあります。
話しにくさや相性の悪さを我慢していると、気軽に相談できず、問題になるまで放置してしまうことも。
初回面談の際に、「この人なら本音を話せそうか」「質問しやすい雰囲気か」を感じ取ることが大切です。
技術的な専門性だけでなく、「相談のしやすさ」も重要な選定基準として考えましょう。
質問に答えられない社労士を選んでしまう
面談の場でこちらが質問をしたときに、曖昧な返事やごまかすような回答しか返ってこない社労士には注意が必要です。
本当に信頼できる社労士であれば、難しい質問に対しても「分からない場合は調べてご連絡します」と誠実に対応するはずですし、必要に応じて具体的な制度名や対応事例を挙げて説明してくれます。
質問に対する答え方は、その社労士の「経験値」と「実務能力」を見極める絶好の機会です。
専門用語ばかりでわかりにくい説明や、内容があいまいなまま終わる場合は、慎重に判断したほうがよいでしょう。
ITやクラウド対応の可否を確かめず決めてしまう
給与計算ソフトや労務手続きの電子申請、チャットでのやり取りなど、労務管理の現場ではIT化・クラウド化がどんどん進んでいます。
ところが、社労士の中には「紙とFAX中心」「メールの返信が遅い」など、いまだにアナログな対応をしている事務所もあります。
もし自社がクラウドサービス(たとえばfreee、マネーフォワードなど)を活用している場合、社労士もクラウドサービスに対応できないと、やり取りが非効率になり、かえって手間が増えてしまうことも。
契約前には必ず、ITツールへの対応力や普段のやり取り方法などを確認しましょう。
デジタルに強い社労士は、スピード感のある対応や、ペーパーレス化による業務効率化の提案もしてくれることが多く、今後の経営において味方になります。
業種や事業規模に合っていない社労士を選んでしまう
社労士にも得意な業種・規模があります。
たとえば、建設業と飲食業では労働時間や法令のポイントがまったく異なりますし、従業員10人の会社と100人の会社では、求められる労務管理のレベルも変わってきます。
自社の業界や規模に合わない社労士を選んでしまうと、表面的なアドバイスしかもらえなかったり、実情にそぐわない対応をされてしまう可能性があります。
選ぶ際は、「これまでにどんな業種や会社規模を担当してきたか」を具体的に聞くことが大切です。
過去の実績や対応事例をもとに、自社との相性を見極めましょう。
他士業との違いを理解せず選んでしまう
「助成金の相談ができるなら、ついでに税金のことも聞こう」「労働トラブルを社労士に相談したら法的な対応もしてくれるはず」と考えて依頼したら、「それは社労士の業務範囲外です」と断られてしまい、がっかりした経験がある方も多いのではないでしょうか。
社労士は、労働・社会保険の手続きや人事・労務の専門家であり、税務(税理士)や法律トラブル(弁護士)とは明らかに業務範囲が異なります。
他士業との違いを理解しないまま依頼してしまうと、「期待していたことができない」「結局他の専門家に頼むことになった」といった後悔につながります。
社労士に「何を依頼できて、どこからが別の士業の仕事なのか」を契約前に基本的な業務範囲を確認しておくことが、満足のいくパートナー選びの第一歩です。
信頼できる社労士の選び方!8つのチェックポイント

社労士は、単に手続きを代行してくれるだけの存在ではありません。
経営者に寄り添い、法令遵守と働きやすい職場づくりを支える「人と組織の専門家」です。
後悔しない社労士選びのために、事前に確認すべきチェックポイントは次のとおりです。
- 事務所の従業員が複数いるかどうか
- 経営者目線で話す相手かどうか
- 必要な業務に対応できる社労士かどうか
- 相談がしやすいか・レスポンスが早いかどうか
- 過去に労務トラブルの対応実績があるかどうか
- クラウド・ITツールの活用はできるか
- 料金体系は分かりやすいか
- 担当者は誰か・どのようなサポート体制なのか
ここからは、後悔しない社労士選びのチェックポイントについて詳しく見ていきましょう。
事務所の従業員が複数いるかどうか
まず確認したいのは、社労士事務所の従業員規模です。
従業員が複数名在籍している事務所であれば、担当者が不在の際にも別のスタッフが対応できるなど、サポート体制に安定感があります。
業務の分業やチェック体制も整いやすく、スピード感のある対応が期待できるでしょう。
大切なのは事業所としてどの程度の人数で運営されているかを見極めることです。
たとえば、少人数の事務所の場合、トップである所長が対応してくれるから、という安心感はあっても、所長に何かあれば委託していた業務はストップしたり、遅れたりしてしまいます。
そのため、ある程度の従業員規模を持っている事務所の方がそういったリスクが少なく、いざという時の対応も安定します。
自社のニーズに合った規模の事務所を選ぶことが本当の意味で信頼できる社会保険労務士事務所を見つける重要なポイントです。
経営者目線で話す相手かどうか
単なる法律知識の提供にとどまらず、「御社の場合、この制度は使いづらいかもしれません」など、実情をふまえたアドバイスをくれる社労士は頼りになります。
たとえば、「制度上は可能でも、人手不足の現場には不向き」と判断してくれたり、「助成金申請は可能だが、その後の管理に手間がかかる」と説明してくれたりといったように、経営の現実に即した提案ができるかを面談の中で確認してみましょう。
必要な業務に対応できる社労士かどうか
社労士によって得意分野はさまざまです。
就業規則の作成、助成金申請、クラウド導入支援、労務トラブル対応など、必要な業務に対応できるかどうかは必ず事前に確認しましょう。
たとえば、「助成金に強い」「IT企業の労務管理に精通している」「メンタルヘルスやハラスメント対応の実績が豊富」など、自社の課題や業種に合った経験を持つ社労士に依頼することで、実務に即したサポートが受けられます。
相談がしやすいか・レスポンスが早いかどうか
社労士に相談したいとき、気軽に連絡できるかどうか、対応のスピードが早いかは非常に重要です。
たとえば、メールやチャットへの返信が早かったり、「気になることはいつでも連絡ください」と言ってくれたり。定期的にフォローアップの連絡があったりすると安心ですよね。
こうしたコミュニケーションのしやすさが、労務トラブルの予防やスムーズな対応につながります。
初回相談のやり取りを通じて、反応のスピードや姿勢を見ておきましょう。
過去に労務トラブルの対応実績があるかどうか
万が一、解雇・未払い残業・労基署の調査などのトラブルが発生したとき、社労士に対応経験がなければ心細くなってしまいます。
「どのようなトラブル対応をしたことはありますか?」と聞いてみて、どんな対応をしてきたか、結果どうなったか、どのような事前対策を提案しているかなどを確認しましょう。
トラブル対応経験がある社労士は、過去の事例をもとに「こういったケースではこのような対応が必要」と事前にアドバイスしてくれるため、労務リスクを未然に回避しやすくなります。
クラウド・ITツールの活用はできるか
勤怠管理、給与計算、労務管理はクラウドツールの導入で効率化できます。
自社がfreee人事労務やマネーフォワードクラウド勤怠などを使っている、あるいは導入予定がある場合は、そのツールに対応できる社労士かを必ず確認しましょう。
また、電子申請への対応可否・データ共有の方法(Dropbox、Google Driveなど)・チャットツール(ChatworkやLINE)への対応なども、日々のやり取りの快適さに直結します。
料金体系は分かりやすいか
顧問契約の場合は月額、スポット対応の場合は1件ごとの料金体系がはっきりしているかどうかを確認しましょう。
信頼できる社労士は、顧問料に何が含まれるか、オプション費用はあるか、年末調整や助成金申請などの別料金の扱いを事前に説明してくれます。
不明瞭な見積もりや、契約書の提示を渋る事務所は注意が必要です。
担当者は誰か・どのようなサポート体制なのか
契約時に「担当者が誰か分からない」「相談しても毎回別の人が出てくる」ようでは、スムーズな連携は期待できません。
チェックすべきポイントは、担当者が固定かどうか、担当が不在のときの代替体制があるか、トラブル対応時の緊急連絡手段があるかなど。
サポート体制の「中身」を確認することで、安心して長く付き合える社労士かどうかが見えてきます。
信頼できる社労士の選び方で安心経営を!

社労士選びは、単なる事務作業の外注ではなく、経営の安心と持続的成長を支えるパートナー探しです。
料金の安さや紹介だけで安易に決めてしまうと、思わぬトラブルやミスマッチに発展することも。
だからこそ、「何を任せたいのか」「どんな社労士なら話しやすいか」「どのくらいの対応力が必要か」といった視点で、じっくり見極めることが大切です。
中小企業の成長段階に合わせて、柔軟かつ丁寧に対応してくれる社労士を見つければ、日々の労務管理がスムーズになり、経営の余裕も生まれます。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジではは、9名体制(うち社会保険労務士4名)で、幅広い労務業務に対応できる社会保険労務士事務所です。
中小企業から創業間もない企業まで、課題や目的に応じて、最適なサポートをご提案し、DX化支援や就業規則改定、障害年金申請の代行など、他事務所では対応しづらい複雑な案件にも柔軟に対応できる体制を整えています。
また、外国人労働者の対応やモンスター社員とのトラブル対応など、他の士業(弁護士・税理士など)と連携しての複合的な問題にも対応可能です。
「信頼できる社労士を探したい」「人事労務の相談ができる専門家とつながりたい」とお考えの方は、社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。