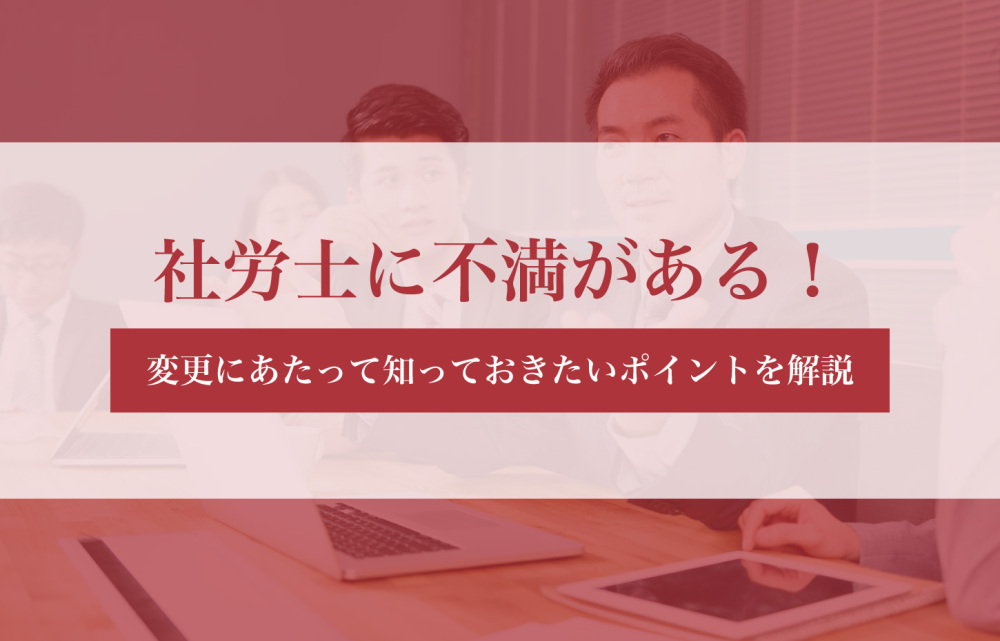INFORMAITION
お知らせ
2025年07月25日
社労士への不満に悩む経営者必見!変更にあたって知っておきたいポイントを解説
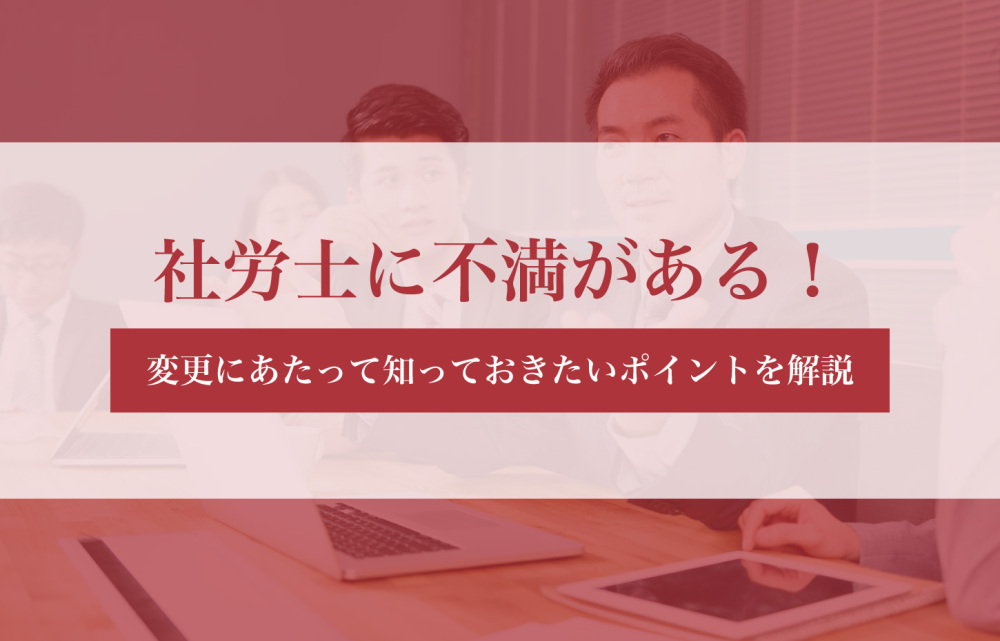
社労士に対する期待と現実とのギャップ、認識のズレなどから、不満が生じることがあります。
この不満をそのままに契約を続けることは、労務改善や助成金活用に対する機会損失、費用の面などからも好ましくありません。
「契約を見直すほどではないかも」「変更には手間がかかるため踏み切れない」と考える方も多いでしょう。
しかし当記事で不満を放置することのリスクをご認識いただき、不満への対処法にも目を通していただければと思います。
社労士に対するよくある6つの不満

中小企業の経営者が社労士に対して抱く不満には、いくつかの共通するパターンが見られます。
大きく分けると次の6つです。
- 対応が遅くなかなか返信してくれない
- 助成金や人事労務に対する積極的な提案がない
- サポート内容に対して費用が高い
- ミス・不備が多く信用に欠ける
- 対応が悪く気軽に相談できない
- 法改正やデジタルへの対応が不十分
これらのよくある不満について紹介します。
対応が遅くなかなか返信してくれない
「急ぎで対処したい問題が発生したにも関わらず、連絡から数日経っても返事が来ない」というケースがあります。
特に人事トラブルや労働基準監督署からの指導など、迅速な対応が求められる場面ではこの対応の遅さが深刻な問題となることもあります。
社労士の立場からすれば、複数の顧問先を抱えておりスケジュール調整に苦労している場合も多いのが実情でしょう。
しかし会社側としては、少なくとも初期対応や回答時期の目安については当日中に示してもらいたいというのが本音だと思われます。
助成金や人事労務に対する積極的な提案がない
「自社から頼んだ必要最小限の業務にしか対応してくれず、より良い労務環境を作るための気づきや提案が得られない」という不満もよくあるものです。
たとえば、助成金の活用可能性について情報提供が受けられなかったり、就業規則の見直しを提案してくれなかったり、といったケースです。
その背景として、社労士が「法令遵守」を第一に考える一方、会社側は「現場に役立つ提案」を求めるという方向性のずれも関係しています。
当然、会社側にも法令遵守の体制を整えたいというニーズはあるかと思います。
しかしながら、消極的な取り組みだけでは収益性を上げることができず、事業者としての継続的な活動ができません。
その観点からは、特に助成金に関する提案は重要です。
意識的に情報収集しなければ自社の活動内容に合った助成金の存在に気付くことすらできず、また、情報が得られても要件への適合性を評価することが難しいという問題に直面します。
後になってその存在に気が付き、不満が生じることもあるでしょう。
サポート内容に対して費用が高い
「支払っている顧問料に対し、提供されるサービス内容がつりあっていないのではないか」とコストに関する不満を抱くこともよくあります。
また、ほかの社労士事務所の料金体系を目にしたときに、現状の料金設定が高額であると気づくケースもあります。
特に、コンサルティングまで期待していたにも関わらず定型的な業務にしか対応してくれない場合だと、期待外れ感から余計にコストパフォーマンスが悪く見えてしまうこともあるでしょう。
ミス・不備が多く信用に欠ける
「社労士という専門家に依頼しているにも関わらず不手際が多く、本当にちゃんと対応できているのか心配だ」と不満を持つケースもあります。
必要な手続きで期限を過ぎてしまったり書類の記載内容に誤りがあったりすると、会社の信用問題にも関わってきます。
そもそも社労士に依頼する業務は社内で対応しても法的に問題はなく、あえて外注しているのはその専門性の高さを信用し、業務効率を上げるためでもあります。
社労士の専門性の高さや正確性を期待していたにも関わらずミスをされては、不満を感じるのも当然です。
対応が悪く気軽に相談できない
高圧的な態度を取られたり質問に対して面倒くさそうな反応をされたりすると、気軽に相談することができなくなります。
また、必要なやり取りをする際にもストレスを感じてしまいます。
このように気軽に相談ができないとなれば、せっかく契約を交わした社労士を十分に有効活用できず、費用対効果も下がってしまうでしょう。
法改正やデジタルへの対応が不十分
「働き方改革関連法をはじめとする法改正に対し、情報提供・対応策の提案がない」「デジタル化の流れに対応できていない」といった不満も多いです。
とりわけ近年は便利なITツールやクラウドシステムも多く登場しており、その活用で業務効率が大きく変わることもあります。
労務管理においても、勤怠管理や給与計算などの業務システムを提案してもらうことで、業務の自動化やミス削減につながる体制を構築できます。
しかし、そうしたDX化支援に対応できる社労士はまだまだ少ないのが現状です。
ただし、これは個々の社労士の問題だけでなく社労士業界全体にいえる古い体質が関係しているとも考えられます。
業界全体の保守性が要因の1つでもあるため、すぐにこの状況が変わることはないでしょう。
そこで業務システムの導入なども相談・依頼したいのであれば、デジタル対応を強みとする社労士事務所を探すことをおすすめします。
社労士に対するリアルな不満の口コミ!

実際に社労士との契約で困った経験をした経営者の声を見てみましょう。
以下のような不満は決して珍しいものではなく、多くの企業で共通して発生している問題です。
- 「従業員の傷病手当金の書類をタイムリーに提出してもらえませんでした。あまりに対応が遅く電話すると「忘れていました。これから対応します。』と言われ唖然とした。」
- 「就業規則の改定をお願いしたのですが、初回の相談から時間になっても音沙汰なく、不安になり催促をしたら、クレーマー呼ばわりされた。」
- 「相談時に初歩的な質問をすると嘲笑され、小バカにした態度で人の話を聞いてくれない。本当に残念で時間の無駄でした。」
- 「高いお金を払っているのに就業規則がいつまで経っても納品されない。助成金についてもこちらから連絡をしないと教えてくれないし、この調子だと受給できるのか不安だ。」
こうした口コミからも分かるように、多くの経営者が社労士との関係において何らかの課題を抱えているのが実情です。
不満を持ったまま社労士と顧問契約を続ける問題点

社労士に対する不満を放置したまま顧問契約を継続することの問題として、次の4つが挙げられます。
- 労務トラブルのリスクが上がる
- 費用の負担が大きくなる
- 従業員満足度の低下と人材流出が起こる
- 機会の損失や競争力の低下につながる
ここからは、各問題点について見ていきましょう。
労務トラブルのリスクが上がる
適切な労務管理ができていないと、従業員との間でトラブルが発生するリスクが高まります。
就業規則の整備が不十分であったり法改正への対応が遅れたりすると、意図せずとも法律に反した状態となってしまうこともあるのです。
特に就業規則に関しては、「社労士に丸投げした結果、現場の実情と合っていないルールが残ってしまい、従業員と揉めてしまった」という問題も起こり得ます。
また、労働基準監督署の調査が入った際に適切な対応ができず、是正勧告を受けるリスクも高くなってしまいます。
費用の負担が大きくなる
費用対効果の低いサービスへの継続的な支払いは、経営を圧迫する要因となります。
また顧問料という直接的な費用負担のほか、「労務トラブルが発生した際の対応コスト」「法令違反による罰則金」などの費用が発生する危険性もありますし、人事労務の業務効率低下による間接的なコスト増も起こり得ます。
特に、コンサルティングが受けられることを考慮して費用対効果を想定していた場合は、期待するサービスがないことによって余計なコストがかかり続けてしまうでしょう。
依頼できる業務範囲の誤解は費用に対する不満をより深刻化させるため、事前によく把握しておかなければなりません。
従業員満足度の低下と人材流出が起こる
労働環境の改善が進まなければ従業員の不満は蓄積し、優秀な人材の流出につながる可能性があります。
優秀な人材を獲得するのも難しくなってしまうでしょう。
一方で、有給休暇の取得促進やハラスメント対策といった従業員の関心が高い分野への取り組みには、企業イメージ向上といった効果も期待できます。
そこで、適切な労務上のアドバイスをしてくれる社労士の存在が重要です。
とはいえ、この問題に対処するには社労士側だけでなく会社側も積極的に向き合う姿勢が必要です。
放置や社労士に対する過信が職場環境の悪化を招くこともあるため、労務改善を社労士に任せきりにすべきではありません。
機会の損失や競争力の低下につながる
助成金や優遇制度の活用機会を逃すことで、得られたかもしれない資金や優遇措置を受けられなくなります。
これが大きな機会損失となり、競合他社との差が広がる要因にもなりかねません。
そのため、「積極的な提案をしてくれない」と不満を抱えたまま契約を続けるのではなく、何らかの対処を行うべきです。
とはいえ、顧問契約を交わした社労士に常にその提案の義務が課されるわけではありません。
「助成金の提案を社労士がしてくれるものと勝手に思い込んでおり、有用な制度を活用しそびれた」といった問題も起こり得ます。
契約プランにそういった積極的な提案やコンサルティングのサービスが含まれているのか、最低限の業務のみを依頼する契約を交わしていないか、振り返ってみましょう。
今の社労士に不満があるときの対処法

社労士に対する不満を抱えたまま放置するのは上述のとおりリスクがありますので、何らかの対処が必要です。
このときのアプローチとしては大きく次の3つを挙げられます。
- 不満を直接伝えて改善を図る
- 契約プランを見直してもらう
- 社労士の変更を検討する
以下で、各アプローチの詳細を見ていきましょう。
不満を直接伝えて改善を図る
まず考えられるのは「不満点を社労士に伝えて改善を求める」というアプローチです。
対応が遅いという不満であれば、連絡の際の希望する回答期限を設けたり緊急時の連絡方法について確認したりすることが有効でしょう。
提案がないという不満に関しては、定期的に打ち合わせを行い自社からもその意向を伝えることが有効です。
社労士側もクライアントが何に不満を感じているか把握できていない可能性があり、具体的な要望を示すことで対応してもらえるかもしれません。
ただし、このアプローチが有効なのは社労士側に改善の意思がある場合に限られます。
契約プランを見直してもらう
不満点の改善という根本的な問題解決が難しい場合は、「契約プランを見直して費用対効果のバランスを調整する」というアプローチも検討してみましょう。
顧問社労士に期待する業務への認識を改め、特定の業務についてのみ、コストを抑えながら依頼を行うのです。
ただし、このアプローチで解決するのは主に費用の問題です。
内部体制の強化、助成金の活用、業務システムの導入など積極的な取り組みについての支援を必要としているなら本質的な解決にはなりません。
社労士の変更を検討する
上記の2つの対処法で問題を解消できない場合は、「自社に合った社労士に変更する」というアプローチも検討してみましょう。
また、話し合いによって対応の改善が見込める場合であっても、新しい社労士との契約を検討した方が長期的には有益である可能性もあります。
適切なパートナーを見つけることができればこれまでの不満が解消され、より良い労務管理体制を構築できるでしょう。
社労士に不満があり変更が必要かどうか判断するときのチェックリスト

社労士を変更すべきかどうか迷った際は、以下のチェックリストを参考にご検討ください。
多くの項目に該当するときは、変更を前向きに検討することをおすすめします。
| コミュニケーションに対する不満 | ・連絡してから数日経っても返事が来ないことが頻繁にある ・質問を投げかけても十分な説明をしてもらえない ・専門用語ばかりで、かみ砕いたわかりやすい説明をしてくれない ・自社からの求めに対し、高圧的または面倒そうな態度を示す |
|---|---|
| サービス内容に対する不満 | ・最低限の手続きにしか対応してくれない ・助成金に関する提案をしてくれない ・法改正があっても自社から質問しないと対応方法についてアドバイスしてくれない ・ITツールに疎く、書面でのやり取りが必須 ・ほかの専門家(税理士等)との連携がない |
| 信頼・信用に対する不満 | ・手続きのミスや不備が複数回発生している ・期限を守らないことがある ・最新の制度について把握していないことがある ・業界の変化についていけていない ・自社の成長に合わせたサポートが期待できない |
| 費用に対する不満 | ・サービス内容に対して費用が高額と感じる ・他事務所と比較して料金設定が高額 ・何に対して追加料金が生じるのか不明瞭 |
今の社労士に不満があるならダブルブリッジにご相談ください

社労士への不満は放置せず、早めに対応することをおすすめします。
改善の要求から契約プランの見直しなどにより、労務管理の体制をより良くできるかもしれません。
もし改善が見込めない場合、新しい社労士との顧問契約の検討をおすすめします。
「どうやって新しい社労士を探そう」「どこに頼むべきかわからない」とお悩みであれば、お気軽に社会保険労務士事務所ダブルブリッジへご相談いただければと思います。
当事務所では社労士としての基本的な業務はもちろん、次のような領域に対処可能です。
- 給与計算代行
- 助成金活用サポート
- 人材育成・研修
- 労働基準監督署・年金事務所への調査対応
- 是正勧告内容の適正化および是正報告書の作成
- 就業規則の作成・改定
- 労使協定の策定
- 起業・創業支援
- 老齢・障害・遺族年金請求 など
特に、給与計算など労務のDX化支援、就業規則改定、障害年金申請などを得意としており、従業員規模1000名以上の企業様の労務管理など小規模の社労士事務所では手に負えない案件にもご対応しております。
現状に不満を抱えている方は、ぜひ社会保険労務士事務所ダブルブリッジまで一度ご相談ください。