INFORMAITION
お知らせ
2025年07月07日
社会保険労務士はどこで探す?目的別に探し方を解説
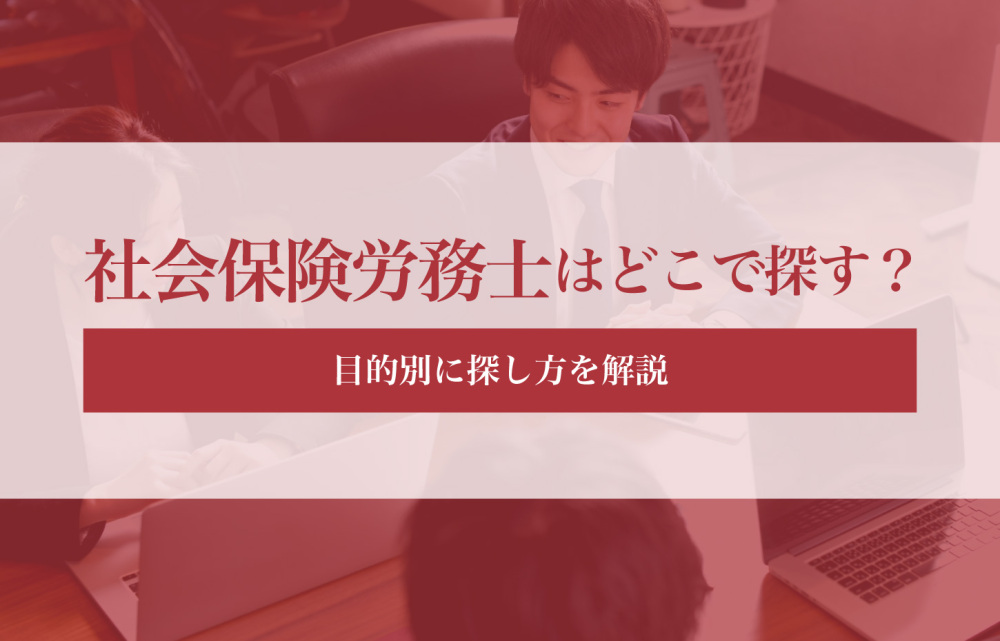
助成金の申請や労務トラブルへの対応、就業規則の整備など、今すぐ専門家に相談したいと思ったときに、頼りになるのが社会保険労務士です。
しかし、税理士や弁護士のように紹介サイトやネット上の情報が豊富ではないため、「誰に頼めばいいのかわからない」と悩む経営者も少なくありません。
この記事では、社労士に相談したい方のために、目的別・スタイル別に社会保険労務士の探し方をわかりやすく解説します。
「社会保険労務士に何を依頼したいか?」によって探す手段が変わる

社会保険労務士を探すとき、大切なのは「何を依頼したいか」をはっきりさせることです。
依頼内容によって、適した社労士のタイプや探し方がまったく異なるからです。
目的があいまいなままだと、相性の悪い社労士を選んでしまったり、費用や対応に不満が出たりすることもあります。
そうしたミスマッチを防ぐために、「自社が何をサポートしてほしいのか」を具体的にしておきましょう。
たとえば、次のような目的をもって社会保険労務士を探すことがおすすめです。
- 助成金申請をお願いしたい
- 労働トラブルへの対応を任せたい
- 就業規則を作成・見直したい
- 社会保険・労働保険の手続きを代行してほしい
- 顧問契約を結んで日常的に相談したい
また、「単発か継続か?」「専門性重視か地域密着か?」をはっきりさせると探しやすくなります。
一度きりの手続きだけ頼みたいのか、長期的に伴走してもらいたいのかで、選ぶ基準は変わるからです。
「助成金の最新情報に強い都内の社労士」なのか、「地域で評判の相談しやすい社労士」なのか、どちらが自社に合っているかを明らかにしておくことで、検索や比較もスムーズになります。
主な社会保険労務士の探し方は5つ

社労士を探す方法にはいくつかありますが、大切なのは「自社に合う人をどうやって見つけるか」という視点です。
初めての方でも実践しやすい、代表的な探し方は次の5つです。
- ①「外国人雇用専門」「建設業特化」「IT業界に強い」など士検索サイト・マッチングサービスを利用する
- ②社労士会の支部を通じて探す
- ③知人経由・顧問士業から紹介を受ける
- ④地域密着型・中小企業向けセミナーや相談会へ参加する
- ⑤Google・SNSで直接検索する
ここからは、自社のニーズに合った方法を見つけるために、社会保険労務士の探し方をみていきましょう。
①「外国人雇用専門」「建設業特化」「IT業界に強い」など士検索サイト・マッチングサービスを利用する
「助成金に強い社労士がいい」「建設業界に詳しい人がいい」など、特定の専門性を重視したいときに便利なのが、検索サイトやマッチングサービスです。
社会保険労務士を探すには、以下のようなプラットフォームがあります。
- 社労士サーチ.com(全国社会保険労務士会連合会)
- 比較biz
- ミツモア
こうしたサイトでは、地域での絞り込みや依頼内容ごとの検索ができるほか、口コミや料金目安が掲載されている場合もあり、初めての方でも比較しやすくなっています。
②社労士会の支部を通じて探す
信頼できる社労士を地域で探したいなら、各都道府県にある社会保険労務士会の支部を利用する方法もあります。
多くの社労士会では、次のようなサポートを行っています。
- 相談窓口の設置
- 依頼内容や希望条件に応じた社労士の紹介
特に、法改正への対応や労務トラブルなど、専門性が求められる場面では、実績ある地元の社労士を紹介してもらえるのは安心です。
「誰を選べばいいか分からない」「地域密着の社労士が希望」という場合にも適した方法です。
③知人経由・顧問士業から紹介を受ける
知人や、すでに契約している税理士・会計士・行政書士など他の士業から社労士を紹介してもらうのも有効な手段のひとつです。
紹介のメリットは、すでに信頼関係のある人からの推薦なので、安心感があること。
紹介者と連携が取れていることで、業務がスムーズに進むケースも多いです。
ただし、注意点もあります。
紹介された社労士が必ずしも自社と相性が良いとは限らないことです。
「紹介されたから断りづらい」「言いたいことを言いにくい」と感じてしまうケースもあるため、初回面談などでしっかり見極めることが大切です。
④地域密着型・中小企業向けセミナーや相談会へ参加する
社労士と直接会って話したい場合には、「助成金活用セミナー」や「労務相談会」などに参加するのがよいでしょう。
こうしたセミナーは、商工会議所や地域の金融機関が主催していることが多く、地元に根ざした社労士に出会えるチャンスです。
参加者向けに無料の個別相談タイムが設けられていることもあり、相談からそのまま依頼に発展するケースもあります。
ただし、開催時期が不定期なので、自社が社労士を探したいタイミングと合わないことも。
情報収集は早めに行い、商工会議所や地元金融機関のホームページ、会報誌などを定期的にチェックしておきましょう。
⑤Google・SNSで直接検索する
インターネット検索やSNSを活用して、自分で社労士を探す方法もあります。
最近では、社労士がホームページやブログ、YouTube、X(旧Twitter)などで情報を発信しており、投稿内容から得意分野や対応スタンス、人柄などが見えてきます。
「〇〇市 社労士 助成金」「社労士 外国人雇用 専門」「建設業 労務管理 社労士」などのキーワードで検索してみると、専門的な知識や実績を持つ社労士のサイトや投稿が見つかります。
実績紹介や過去の相談事例、顧客の声が掲載されていれば、相性を見極める手がかりになります。
目的別:おすすめ社会保険労務士の探し方

税理士や弁護士とは異なり、社会労務士は税理士のように毎月の業務委託が必要な士業ではなく、単発で依頼するケースが多い士業です。
だからこそ、目的に合わせた最適な探し方を知っておくことが、失敗しない社労士選びのポイントになります。
目的別に社労士を探す代表的な方法は、次の7つです。
- 助成金の申請をしたい
- 就業規則を新しく作りたい・改定したい
- 労務トラブル(残業・解雇・メンタル等)の相談がしたい
- 社労士と継続的な顧問契約を結びたい(全体的に任せたい)
- 雇用調整助成金・育児休業など、スポットで専門的な対応が必要
- 人事労務ソフトや電子申請の導入支援をしてほしい
- 業界に精通している社労士に依頼したい(建設業/運送業/介護業など)
ここからは自社の目的に合う社労士を紹介します。
助成金の申請をしたい
「キャリアアップ助成金」や「両立支援等助成金」など、申請のハードルが高く感じられる助成金こそ、手続きに慣れた社労士に依頼するのがおすすめです。
「ミツモア」などのマッチングサービスで、助成金に対応可能の社労士を探したり、助成金に特化した社労士をGoogle検索で見つけたりするとよいでしょう。
実績として、「キャリアアップ助成金」や「両立支援助成金」の取扱い経験が掲載されているかどうかを確認すると安心です。
社労士によっては「成功報酬型(受給決定後に報酬発生)」のところもあれば、「着手金+成功報酬」のところもあります。
契約前に料金形態をしっかり確認しましょう。
就業規則を新しく作りたい・改定したい
就業規則の作成や見直しは、社労士の中でも定番の得意分野です。
業種や働き方の変化に合わせて、自社に合った規則を整備することで、トラブル予防にもつながります。
「就業規則 専門 社労士」などのキーワードで検索し、専門サイトやブログをチェックしたり、マッチングサイトや都道府県の社労士会支部を通じて依頼したりするとよいでしょう。
「自社の業種・運用実態に応じたオーダーメイド対応か」「テンプレートを活用して安価に作成してくれるか」は、予算とのバランスを考えて選びます。
さらに、「働き方改革対応」「ハラスメント防止対応」など改定の理由に関する知識・実績があるかも確認しておくと安心です。
労務トラブル(残業・解雇・メンタル等)の相談がしたい
従業員とのトラブルが発生したときには、対応経験が豊富な社労士の存在が心強い味方になります。
「労務トラブル名+社労士」で検索し、関連する情報発信を行っている社労士事務所を見つけたり、「残業代トラブル 社労士」「うつ病休職 社労士」など、具体的なキーワードで検索したりするとよいでしょう。
「紛争解決手続代理業務(特定社労士)」の資格を持つ社労士は、労働局のあっせんなど、個別労働関係紛争の一部において代理人として関与することが可能です。
依頼前の初回相談では、「弁護士との連携が可能か」「緊急時に電話・面談で迅速に対応してもらえるか」を確認しておきましょう。
トラブル対応はスピードと判断力が重要なので、対応の柔軟性や連絡の取りやすさも、重要な判断材料になります。
社労士と継続的な顧問契約を結びたい(全体的に任せたい)
日々の労務管理や法改正への対応など、継続的なサポートを社労士に任せたい場合は、顧問契約を前提とした社労士選びが重要です。
おすすめは、地元密着型の社労士事務所や社労士法人に直接問い合わせる方法です。
Googleマップやインターネットで「地域名+社労士」で検索すると、近隣の事務所が見つかります。
顧問契約を検討する際は、顧問契約の範囲、月額費用の内訳や報酬体系、担当者制や訪問頻度などの継続体制を事前に確認しましょう。
「担当が毎回変わらないか」「定期的に訪問してくれるか」など、やりとりのしやすさや関係の継続性も大事なチェックポイントです。
産前産後休業・育児休業など、スポットで専門的な対応が必要
産休・育休対応などの一時的に専門的な対応が必要なケースでは、テーマ特化型の社労士を選ぶのが効果的です。
「〇〇助成金 社労士」や「育児休業 社労士」など、テーマと社労士をセットで検索すると、その分野に詳しい社労士事務所のサイトや記事が見つかります。
また、信頼できる目安として、国の施策や法改正に関する情報発信(ブログ・SNSなど)を継続的に行っている社労士は、知識の更新が早く、対応力が高い傾向があります。
スポット契約の場合は、料金体系や対応範囲、成果報酬などを契約前に明らかにしてもらうことがトラブル防止のカギです。
人事労務ソフトや電子申請の導入支援をしてほしい
業務効率化やテレワーク対応で、クラウド型の人事労務ソフトの導入を検討している場合は、そのツールに対応している社労士に依頼しましょう。
「SmartHR 対応 社労士 〇〇市」「クラウド対応 社労士」「労務管理 デジタル 社労士」のような検索で探すのが有効です。
また、マッチングサイトでは、各社労士の対応ツールが明記されている場合も多く、確認がしやすいです。
依頼前には、システムの初期設定や運用支援の有無、使用ツールとの連携実績、料金体系などをしっかり確認しましょう。
単なる導入支援にとどまらず、データ管理や電子申請の体制構築まで任せたい場合は、ITリテラシーの高い社労士を選ぶことが大切です。
業界に精通している社労士に依頼したい(建設業/運送業/介護業など)
建設・運送・介護といった業界ごとに、労務管理のポイントや必要な助成金制度は異なります。
だからこそ、業界に詳しい社労士を選ぶことが重要です。
「建設業 社労士 助成金」「運送業 労務管理 社労士」「介護業 就業規則 社労士」のようなキーワード検索がよいでしょう。
特にその業界での支援実績や対応事例をホームページで紹介している事務所は、安心して相談できます。
タイミングが合えば、業界団体のセミナーや勉強会に登壇している社労士や、専門メディアで寄稿している人を選ぶのもおすすめです。
同業他社への支援実績があるかどうかも確認してみましょう。
事務所のホームページで「対応事例」や「お客様の声」などの項目を確認することで、支援対象企業の業種や規模を知る手がかりになります。
自社にとって相性の良い社会保険労務士を探して見極めるチェックポイント

社会保険労務士(社労士)を選ぶとき、「誰に頼むか」によって支援の質や満足度は変わります。
顧問契約のような継続的な関係を築く場合はもちろん、スポットでの依頼であっても相性の良し悪しが結果に直結します。
相性のいい社労士を見極めるポイントは、次の通りです。
- 実績や専門分野が「自社の課題」とマッチしているか?
- 自社と同規模・同業種の支援経験があるか?
- レスポンスが早く、連絡が取りやすいか?
- 顧問料・手数料の説明が明確か?
- 電子申請・クラウド対応など業務の効率化に対応しているか?
- 長期的な関係を築けそうか?(相性・人柄も含め)
ここからは、信頼できる社労士に出会うために、事前に確認しておきたい6つのチェックポイントを紹介します。
実績や専門分野が「自社の課題」とマッチしているか?
まず確認すべきは、その社労士が自社が抱えている課題に対してどれだけ経験や知識があるかです。
たとえば、「助成金に強いと明記されているか」「人事制度や規則整備に特化しているか」「労務トラブルの対応の実績が紹介されているか」といった具合に、専門分野が明らかにされているかをチェックしましょう。
事務所のホームページやブログ、過去の支援事例などを通じて、客観的に確認できる情報があるかどうかも重要です。
実績をしっかりと公開している社労士は、業務に自信があるといえるでしょう。
自社と同規模・同業種の支援経験があるか?
会社の規模や業種によって、必要な労務管理の内容は異なります。
従業員数10名未満の会社と100名を超える会社では、必要な仕組みや支援方法も変わってきます。
たとえば、「50名以下の中小企業に対する支援経験があるか?」「自社と同じ業種への対応実績は?」といった視点で確認することが大切です。
初回相談時には、「過去に支援した企業の規模感や業種」について具体的に質問してみましょう。
同じような企業のサポート実績があれば、自社の事情にもスムーズに対応してもらいやすくなります。
レスポンスが早く、連絡が取りやすいか?
社労士とのやり取りでは、「急いで相談したい」という場面も少なくありません。
トラブルや法改正対応など、スピードが求められることも多いため、日常的な連絡の取りやすさは大事なポイントです。
たとえば、「メールやチャット対応が可能か?」「連絡した際の返信スピードはどれくらいか?」「問い合わせへの対応が丁寧か?」などは確認しておきます。
顧問契約を結ぶ前の段階でも、最初のメールや電話対応から「スピード感」や「人柄」が見えてくることがあります。
小さなやり取りから、信頼できる相手かどうかを見極めていきましょう。
顧問料・手数料の説明が明確か?
社労士に依頼するうえで、料金体系の分かりやすさはとても大切です。
金額だけでなく、「どこまで対応してくれるのか」という範囲とのバランスを確認します。
たとえば、「相談対応のみなのか」「手続き書類の作成・提出まで含まれるのか」「スポット対応はしてくれるのか」など、サービスの範囲が明らかにされているかをチェックしましょう。
助成金申請などの場合は、「成功報酬型」や「着手金あり」など、個別の料金体系が適用されることもあります。
契約前には、その条件や成果の定義も含めてきちんと確認しておくことが大切です。
見積書や契約書に料金の内訳が、あいまいなまま契約してしまうと後々トラブルになる可能性があります。
気になることは遠慮せずに聞き、納得してから契約するようにしましょう。
電子申請・クラウド対応など業務の効率化に対応しているか?
最近は、人事労務業務もデジタル化が進んでいるため、社労士にもデジタルレベルの正確な対応力が求められます。
業務のスムーズさや手続きのスピード感にも関わってくるため、効率化に前向きな社労士かどうかを確認することは重要です。
たとえば、「e-Govによる電子申請に対応しているか」「freee、SmartHR、マネーフォワードなどのクラウドソフトに対応しているか」「PDFやクラウドストレージを活用して書類のやり取りができるか」などを確認しておきましょう。
こうしたツールに対応している社労士であれば、紙のやり取りや郵送の手間が減り、時間もコストも削減できます。
長期的な関係を築けそうか?(相性・人柄も含め)
社労士との関係は、単なる業務委託ではなく、経営を支えるパートナー関係になることもあります。
だからこそ、相性や信頼感、人柄も大切な判断材料です。
たとえば、「話し方や説明のわかりやすさなど経営者との相性はどうか」「困ったときに相談しやすい雰囲気があるか」などは、初回の面談や無料相談の際に感じられるポイントです。
「この人なら長く付き合えそう」「話しやすい」「否定せず受け止めてくれる」と感じる社労士なら、何かあったときにも安心して相談できます。
たとえば、「この業界での支援実績はありますか?」「急ぎの相談にはどのように対応していただけますか?」といった具体的な質問を投げかけて、相手の姿勢や対応力を見極めましょう。
少しでも違和感を覚えるようであれば、他にも相談して比較してみると良いでしょう。
自社と相性の良い社会保険労務士を探すことが重要!

社会保険労務士は、企業の労務を支える重要な存在です。
今回ご紹介したように、依頼したい内容や契約スタイル、業界や企業規模に合った社労士かどうかを事前に見極めることで、失敗やミスマッチを避けることができます。
実績や専門分野、連絡のしやすさ、料金の明確さ、さらには相性など、多角的な視点で比較・検討することが、自社にとって最適なパートナー選びへの第一歩です。
社労士をお探しなら社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。
私たちダブルブリッジは、9名体制(うち社会保険労務士4名)で、幅広い労務業務に対応できる社労士法人です。
中小企業から創業間もない企業まで、課題や目的に応じて、最適なサポートをご提案し、DX化支援や就業規則改定、障害年金申請の代行など、他事務所では対応しづらい複雑な案件にも柔軟に対応できる体制を整えています。
また、外国人労働者の対応やモンスター社員とのトラブル対応など、他の士業(弁護士・税理士など)と連携しての複合的な問題にも対応可能です。
「労務管理を外注したい」「社内の規則を整えたい」「他の社労士では難しかった相談がある」といったご用件は、社会保険労務士事務所ダブルブリッジにご相談ください。
