INFORMAITION
お知らせ
2025年07月07日
社労士事務所は売却できる?売却先や顧客の引き継ぎはどうする?
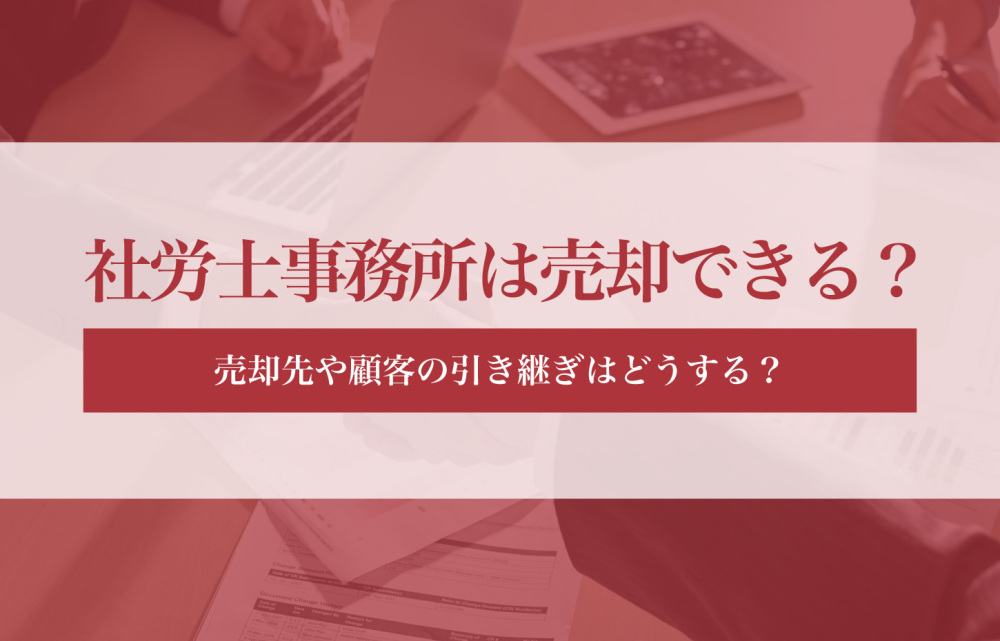
開業している社会保険労務士が引退する場合、事務所の存続を考える必要があります。
後継者不在で廃業するケースもありますが、事務所の売却も選択肢の一つです。
しかし、事務所を売却する機会はほとんどないため、以下のような疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
- 社会保険労務士事務所は売却できるの?
- クライアントは引き継ぎできるのか?
- 売却先はどうやって探す?
- どこに売却したらよい?
一般的に、「士業事務所=売却できない」」と思われがちですが、近年では「士業M&A市場」が活発化しており、事務所の売却も可能です。
本記事では、社会保険労務士事務所の売却可能性と具体的な進め方について、実務的な観点で解説します。
そもそも社会保険労務士事務所は事業売却できるのか?

社会保険労務士事務所は株式会社と同じく、事業売却できます。
売却形態は事務所の資産や株式などを売却する「事業譲渡」、または顧客リストや従業員などを引き継ぐ「M&A」が一般的です。
法人格の有無に関わらず、収益源となる業務委託契約や顧問契約、ノウハウや人材も売却対象となります。
ただし、業務自体の売却は可能ですが、社会保険労務士の資格の売却はできません。
社会保険労務士事務所の売却に伴う懸念点

社会保険労務士事務所を売却する際は、以下の懸念点を払拭する必要があります。
- 現在のクライアントはどうなる?
- クライアントにはどう説明する?
- 売却先はどうやって探す?
事業売却はクライアントに与える影響が大きいため、丁寧な説明や売却先への引き継ぎが重要です。
ここからは、社会保険労務士事務所の売却について、課題となる懸念点を詳しくみていきます。
現在のクライアントはどうなる?
事業の売却後もクライアントとの顧問契約を継続する際は、「引き継ぎ型M&A」や「段階的承継」の仕組みを活用できます。
引き継ぎ型M&Aでは、業務委託契約を売却先に承継できるため、クライアントに与える影響が最小限です。
段階的承継の場合は、新・旧の経営者が一定期間協力し、クライアントや従業員を徐々に引き継ぎます。
引き継ぎが完了するまでの間は、旧経営者が顧問や相談役に就任しても構いません。
なお、売却後に契約内容や料金が変更となる場合、原則として「クライアントとの合意の上で明確に説明」している必要があります。
料金が上がると、クライアントが他の事務所に乗り換える可能性もありますが、受入先が決まれば社会保険や給与関係の事務が停滞しません。
クライアントとの関係が解消されても、新たな社会保険労務士によって業務が保証される場合は、喜ばしい状況といえるでしょう。
クライアントにはどう説明する?
社会保険労務士事務所を売却する場合、クライアントとの信頼関係には十分な配慮が必要です。
クライアントとの信頼関係が損なわれると、事業承継の成功率は下がります。
そのため、売却通知の送付のみでは信頼関係を損なう恐れがあるため、以下の項目をはっきり伝えてください。
- 売却やM&Aの理由(加齢による健康不安や後継者問題など)
- 譲渡日
- 承継先の実績や信頼性
- 業務内容や料金体系に大きな変化がないこと
- 新たな代表者のあいさつ文やプロフィール
- 売却やM&Aに関する問い合わせ先
- 今までのご愛顧に対する感謝
付き合いの長いクライアントなど、事情によっては個別面談や電話によるフォローも重要です。
最後まで丁寧に対応すると、売却先への引き継ぎがスムーズになるでしょう。
売却先はどうやって探す?
社会保険労務士を引退する際は、以下の方法で事務所の売却先を探してみましょう。
- M&Aや事業承継経験のある同業他事務所を探す
- 社会保険労務士会・支部内ネットワークを利用する
- 知人や士業グループへ個別に打診する
- 士業専門のM&A仲介会社
同業の事務所がM&Aなどを経験しており、クライアントや従業員の受け入れも可能であれば、おすすめの売却先といえます。
事務所の売却先を探す場合は、以下のメリット・デメリットも参考にしてください。
M&Aや事業承継経験のある、ある程度の規模感の同業他事務所を探す
同業他事務所を探す場合は、「社会保険労務士事務所・M&A・事業承継・受け入れ・実績」などのキーワードでネット検索してください。
社会保険労務士法人のホームページには、「事業承継歓迎」や「拠点拡大中」、「パートナー募集」などが掲載されている場合があります。
同業他事務所に売却する際は、以下のメリット・デメリットを考慮しておきましょう。
| メリット | ・仲介手数料が不要 ・条件交渉の柔軟性が高い ・承継実績がある法人は顧客や従業員の引き継ぎがスムーズ ・売却後も「顧問」や「アドバイザー」として継続的に関われる |
| デメリット | ・情報収集や契約内容の整備などは自己対応 ・経営者交替により、クライアントが離れてしまうリスクがある ・売却価格が折り合わない可能性がある |
売却先の社会保険労務士事務所を探す場合、士業M&A事例が掲載されたネットニュースや、業界紙などのチェックもおすすめです。
売却価格や条件設定(例:一括払いか分割払いか、旧代表者の関与期間、従業員の継続雇用など)にあたっては、士業M&Aの専門家(弁護士・行政書士など)のアドバイスも参考になります。
社労士会・支部内ネットワークを利用する
社会保険労務士会連合会や支部内ネットワークを利用すると、後継者が見つかる可能性があります。
勉強会や研修会、支部会議などに参加した際は、知り合いの会員に声をかけてみましょう。
士業のネットワークで売却先を探す場合は、以下のメリット・デメリットも参考にしてください。
| メリット | ・信頼関係のある身近なネットワークであるため実務や倫理観を共有しやすい ・手数料などが原則不要 ・引き継ぎ後も柔軟に連携できる(顧問に就任するなど) |
|---|---|
| デメリット | ・相手がすぐに見つかるとは限らず、タイミングに左右される ・売却価格などの条件が折り合わない場合がある |
料金形態や従業員の給与など、金銭面は当人同士の交渉です。
売却先にM&Aや事業承継の経験がなければ、スムーズな引き継ぎに対応できず、クライアントや従業員が不利益を被る可能性があります。
事務所売却のトラブルを避けたい場合は、M&Aなどに詳しい専門家(たとえば、士業専門のM&A仲介経験があり、契約書の作成にも対応できる弁護士や行政書士)のアドバイスを受けておきましょう。
既存の知人や士業グループへ個別に打診する
知人の社会保険労務士や、協業している税理士・行政書士などがいる場合は、非公式に売却の意向を伝えてみましょう。
自ら売却の意向を発信すると、信頼できる引き受け手を人づてに紹介される場合もあります。
士業グループに売却を打診する際は、以下のメリット・デメリットも理解しておきましょう。
| メリット | ・信頼と相性を前提に引き継ぎやすい ・引き継ぎ条件を柔軟に調整できる ・買い手にメリットが伝わりやすい |
| デメリット | ・サポート体制の変更により、クライアントが離れるリスクがある ・売却先の経営方針によっては従業員が離職する恐れがある ・売却価格の交渉が難航する |
士業グループに事務所を売却する場合、法的手続きや条件整理が甘くなりがちです。
曖昧な内容の契約書を取り交わすと、雇用条件や顧客サポートの品質を悪化させる恐れがあります。
必要に応じて士業M&Aの専門家(弁護士や行政書士など)に関わってもらい、契約内容などを整備してください。
士業専門のM&A仲介会社
M&A仲介会社は買収希望者を探し、売却希望者とマッチングしてくれます。
売却時には希望条件(地域・規模・売却価格・従業員雇用など)を設定し、匿名の交渉スタートも可能です。
仲介会社には以下のメリット・デメリットがあるので、利用するかどうかは慎重に判断してください。
| メリット | ・自力で相手を探すよりも効率的かつ安全にマッチングできる ・契約書の雛形や、面談・交渉もサポートしてくれる ・事務所の価値を客観的に診断してもらえる |
|---|---|
| デメリット | ・手数料が高い ・案件によっては成約までに時間がかかる ・引き継ぎ後にクライアントや従業員が不利益を被る可能性がある |
初回の相談は無料になるケースが多く、非公開性も高いため、安心して利用できるでしょう。
ただし、着手金や成功報酬には統一的な基準がないため、相場以上の金額を請求される可能性があります。
一方で、過去の成約実績や得意業種なども確認し、信頼できる仲介会社を選ぶことが重要です。
士業M&Aの専門知識が不足していると、不利な条件を提示される場合もあるので要注意です。
売却先はどう選ぶ?
社会保険労務士事務所の売却先を選ぶ際は、以下の基準で判断してみましょう。
- 売却先がM&Aや事業承継を経験しているか
- クライアントや従業員の受け入れを経験しているか
- 売却先の規模が適切かどうか(クライアントや従業員の受け入れに対応できる規模)
- 業務内容や料金に大きな違いがないか
- 直感(信頼できそうかどうか)
売却先の経営方針や、業務内容が大きく異なると、クライアントのサポートに対応できない恐れもあります。
複数の売却先から似たような条件を提示されたときは、自分の直感を信じてもよいでしょう。
社会保険労務士事務所の売却の流れ

社会保険労務士事務所を売却するときは、以下の流れを参考にしてください。
- 売却準備
- 売却先探し
- 面談
- 契約交渉
- 顧客通知
- 売却成立
まず自所の資産整理からスタートし、契約交渉などを経て売却が成立するため、一般的には6カ月~1年程度かかります。
ここからは、具体的なステップを一つずつ確認していきましょう。
STEP1:売却準備:資産・顧問情報・内部体制の棚卸し
社会保険労務士事務所の売却においては、まず準備段階として以下の資産などを整理します。
- 顧問先リストの整備(契約内容や解約リスクなど)
- 売上や利益構造の明確化(直近3年分の売上や費用など)
- 従業員情報の取りまとめ(雇用形態、担当業務、就業規則、社会保険など)
- PCやソフトウェア、車両・設備などの資産一覧
- 事務所の賃貸契約やリース契約情報
- 未収金や未払金
- 現行の顧問契約書や業務マニュアルなどの書類一式
売却の際には事務所の価値を算定するため、有形・無形の資産から売却額を見積もります。
買い手との信頼関係を構築する場合、引き継ぎ可能な契約や人材、収益構造などの整理が重要となるので、感覚的な見積りをしないように注意してください。
未収金は財務体質の悪化を招き、事務所の価値を引き下げる原因になるため、可能な限り回収してください。
未払金は相手方が引き継ぐケースもありますが、売却前に支払いを済ませると、価格交渉がスムーズに進みます。
第三者にも資産状況がわかるよう、関係書類を「見える化」しておけば、一定の評価を得られるでしょう。
STEP2:売却先探し:信頼できる引き継ぎ相手の選定
事務所の売却準備が整ったら、次は売却先を選定します。
売却先は以下の候補から決めますが、売却価格だけを重視せず、信頼性などの選定基準も考慮してください。
| 主な売却先の探し方 | ・士業専門M&A仲介会社 ・社会保険労務士会連合会や支部ネットワーク ・知人紹介や他士業ネットワーク ・自力で探す |
| 売却先の選定基準 | ・事業承継やM&Aの経験 ・クライアントや従業員の受け入れ経験 ・事務所の規模 ・経営の方向性や業務内容、費用感があまり変わらないかどうか ・直感(信頼できる相手かどうか) |
複数候補がいる場合はそれぞれに打診し、誠実な対応かどうかも比較検討してみましょう。
最終的には「安心してバトンを渡せるか?」など、直感的な判断も必要です。
STEP3: 面談:業務方針・引き継ぎ条件の確認
売却先の候補が決まったら、直接面談やオンライン面談により、1対1で打ち合わせを行ってください。
相手がどのような事務所なのか、引き継ぎに耐えられる体制かどうかを見極め、自分の考えも丁寧に伝えましょう。
面談の際には、以下のポイントも確認してください。
- 顧問先のサポート体制(担当者や訪問対応の可否)
- 料金体系やサービス内容の変更有無
- 引き継ぎ期間中の旧代表の関与
- 既存従業員の受け入れ条件
- 売却後も旧代表が関与するかどうか
クライアントの情報を説明する場合、顧問先の資料(属性・業種・契約数など)を準備しておけば、好印象となりやすいです。
ただし、売却によって業務品質が下がると、クライアントの信用を失いかねないため、顧問や相談役として残るかどうかも話し合っておきましょう。
業務スタイルや経営理念が合わない場合は、無理に売却しない判断も必要です。
STEP4: 契約交渉:価格・雇用・引き継ぎ内容の最終合意
売却先との契約交渉では、双方の意向を出し合って売却価格を決定します。
いつ・誰が・どうやって引き継ぐかなど、実務の協議も必要になるため、以下の項目を決めていきましょう。
- 売却金額と支払い方法(一括または分割など)
- 引き継ぎ期間と旧代表の関与
- 従業員の雇用契約引き継ぎの有無
- 顧問契約の承継方式(名義変更、新規契約)
- 移転やオフィス賃貸契約の引き継ぎ
曖昧な表現はトラブルの原因になりかねないため、契約書の作成に不安がある場合は、弁護士や行政書士など第三者のサポートを受けてください。
顧客情報の開示を漏らしたり、誤った情報を流したりすると、最終合意に至らない可能性があるので要注意です。
クライアントや従業員への影響も考慮し、短期間で売却できるようにスケジュールを調整しましょう。
STEP5: 顧客通知:売却の説明と理解の確保
社会保険労務士事務所の売却条件が固まったら、顧問先の同意を得るステップに移ります。
顧問先には代表者変更や業務承継を書面で通知しますが、主要顧客や長期の契約先については、個別訪問や電話による説明も必要です。
事業承継などを説明する際には、以下のポイントにも留意しておきましょう。
- 売却・承継の背景を誠実に伝える(高齢や健康上の理由など)
- 引き継ぎ先のプロフィールやサポート体制を説明
- サービス・料金体系が維持される点を強調
- 必要であれば、新代表のあいさつ機会を設ける
必要に応じて新代表者とともにクライアントを訪問し、書面の通知も新旧代表者の連名にしてください。
クライアントを丁寧にフォローすると、信頼関係を保ったままスムーズに移行できるでしょう。
STEP6: 売却成立:契約締結と業務開始
事務所の売却についてクライアントの同意を得た後は、事業譲渡契約書などを締結します。
以下の手続きにも対応すると、社会保険労務士事務所の売却は完了です。
- 登記・名義変更(事務所が法人の場合)
- 税務署や社会保険労務士会連合会への廃業・登録変更届の提出
- 必要書類や顧問先データの受け渡し
- 必要に応じて社会保険労務士損害賠償保険の解約または名義変更
クライアントや従業員、関係者の混乱を避けるため、売却後も数週間〜数カ月の移行期間を設けるのが理想的です。
売却完了後は円満にリタイヤできますが、健康面に問題がなければ、セカンドキャリアの形成を考えてもよいでしょう。
社会保険労務士事務所の売却に関するよくある質問

社会保険労務士事務所を売却する際は、売却価格の相場や、廃業との違いなどを理解しておく必要があります。
一度契約書にサインすると、後で変更できなくなる恐れがあるため、以下のような質問・疑問は早めに解消しておきましょう。
資格がない人や法人に売却はできる?
売却先は個人開業の社会保険労務士、または社会保険労務士法人に限られます。
単なる資本家や一般法人など、社会保険労務士がいない相手方には譲渡できません。
税理士法人などに売却する際は、社会保険労務士の従業員を設置する必要があります。
社会保険労務士でない者がその名称を用いて業を行うことは法律で禁じられており、資格がない方や法人には売却できません。
従業員がいる場合、どうすればいい?
今後も社会保険労務士事務所の従業員として働きたい意思があれば、雇用継続可能な売却先を探す必要があります。
以下のように対応すると、従業員の引き継ぎがスムーズです。
- 売却条件に従業員の継続雇用を含める
- 雇用契約書や労働条件通知書を整理しておく
- 給与や就業規則の変更予定があれば説明する
従業員も「事務所の価値」の一部となるため、給与水準などが近い売却先を探してみましょう。
売却金額はどうやって決まるの?相場は?
社会保険労務士事務所の売却金額は、年間売上の0.5倍~1.5倍程度が相場です。
ただし、顧問数や業務内容、従業員体制などから総合的に評価されるため、ブランド価値の高い事務所は年間売上の2倍~3倍で売却できる可能性があります。
たとえば、首都圏に拠点を持ち、専門業種に特化している事務所などが該当します。
事務所の信頼性や安定性が高く、財務体質も良好であれば、相場以上の金額でも売却可能でしょう。
仲介会社は使ったほうがいい?
基本的には同業他事務所を探し、自分で売却交渉を進めた方がよいでしょう。
M&A仲介会社は匿名で買い手候補を探し、安全なマッチングや契約書の作成などもサポートしてくれます。
価格交渉にも対応してもらえますが、着手金や仲介手数料、成功報酬などのコストがかかるため、大きな出費を避けられません。
売却先とマッチングした後や、売却後にも制約が多いので、柔軟な契約を結べない可能性があります。
売却後も一定期間だけ関わりたいのだけど可能?
売却時の契約によっては可能です。
事業譲渡契約書に引き継ぎ期間やアドバイザー契約などの条項を設けると、旧代表者として1~6カ月程度は関与できます。
買い手事務所や顧問先、従業員のすべてにとって安心感があるため、相談役などのポジションを積極的に検討してみましょう。
売却後に一定期間だけ関与したい場合は、旧代表として顧問契約を締結すれば可能です。
期間や報酬などは事前に明文化しておきましょう。
廃業と売却はどう違うの?
廃業は事務所の閉鎖のみを指しますが、売却は事業の引き継ぎです。
具体的には以下の違いがあり、売却は「信頼をバトンのように渡す」イメージです。
| 項目 | 廃業 | 売却 |
|---|---|---|
| 顧問先 | 契約終了 | 売却先に承継 |
| 従業員 | 雇用終了 | 継続雇用の可能性あり |
| 売却収益 | なし | 対価を得られる |
| 旧代表の関与 | なし | 引き継ぎ支援などが可能 |
廃業は業務委託契約などが終了するため、クライアントは新たな社会保険労務士事務所を探す必要があります。
売却は終わりではなく「信頼のバトンタッチ」

社会保険労務士事務所の顧問契約や、従業員の雇用契約を存続させたい場合は、事業承継を検討してみましょう。
たとえば、売却後に顧問業や社労士向け講師業、執筆活動に取り組む社労士も増えています。
「売却=引退」ではなく、次のステージを目指すための新しい選択肢です。
どこに売却したらよいのか迷ったときは、ぜひ「社会保険労務士事務所ダブルブリッジ」にご相談ください。
ダブルブリッジには、社会保険労務士事務所の事業承継やM&Aの実績があり、クライアントや従業員の引き継ぎも行っています。
従業員の在宅勤務にも対応しているので、遠隔地でも業務に携わっていただけます。
顧客・従業員・家族、そしてご自身の未来のためにも、ダブルブリッジとともに「誠実な売却」を実現しましょう。
