INFORMAITION
お知らせ
2025年07月07日
社労士事務所を事業承継したい!まず考えるべき5つのこと
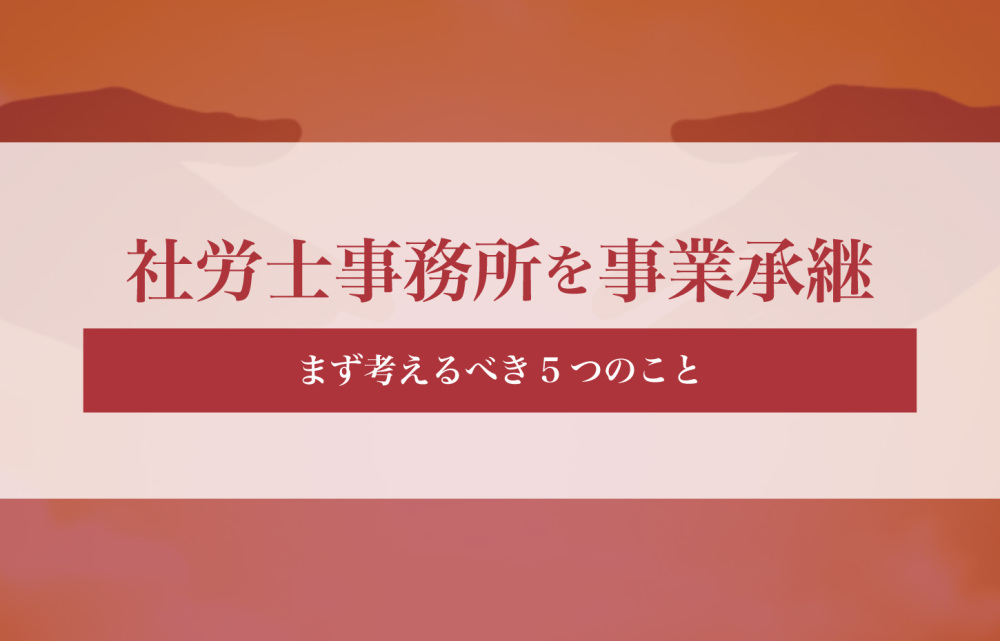
社会保険労務士として活動する中で、加齢や体調不良、あるいは事業を引き継ぐ人がいないといった事情により、事務所の今後を考え始める方も多いのではないでしょうか。
日本の社会保険労務士業界では、既に高齢化が進んでいる状況です。
特に60歳を超える開業社会保険労務士の割合が、約35%以上を占めます。
| 2024 年3月 31 日現在の登録者の年齢別構成は、20 歳代(0.4%)、30 歳代(6.5%)、40 歳代、(24.3%)、50 歳代(31.1%)、60 歳代(22.3%)、70 歳代(11.9%)、80 歳代(3.0%)、90 歳代以上(0.5%)となっており、50 歳代の割合が最も多く、40 歳代、60 歳代と続いている。平均年齢 は 56.27 歳、最年少は 22 歳、最年長が 102 歳となっている。 引用元:中央経済社-社会保険労務士白書-2024年版 |
これまで築き上げてきた信頼やノウハウ、顧客資産を廃業で終わらせるのはもったいないですよね。
この記事では、「社会保険労務士事務所の事業承継」について、その方法や準備、検討すべき点を具体的に解説します。
そもそも社会保険労務士事務所の事業承継は可能?

まず結論から述べると、社会保険労務士事務所においても、事業承継はできます。
顧問契約やスタッフ、ノウハウといった事業資産の引き継ぎが行えます。
具体的には、顧問契約書・給与計算システム・就業規則データ・スタッフの雇用契約などが引き継ぎ対象。
もちろん、資格自体は承継できません。
しかし、事務所機能や、顧客との関係性は承継し、継続していくことは可能です。
税理士や司法書士の業界では、既に事業承継が広く行われており、社会保険労務士業界でも、市場が拡大しつつあります。
社会保険労務士事務所の事業承継の方法は2種類

社会保険労務士事務所の事業承継の方法は、以下の2つです。
- 親族・所内後継者への承継(内部承継)
- 第三者への承継(外部承継・M&A)
それぞれの承継方法について、以下の表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 内部承継 | 外部承継(M&A) |
|---|---|---|
| 承継相手 | 共同代表・親族・職員など | 他の社労士事務所・法人 |
| 信頼関係 | 高い(構築済み) | 交渉次第 |
| 承継資金 | 少なめ or なし | 譲渡益あり(売却収入) |
| 承継準備期間 | 比較的長く取れる | スピード調整可能(数か月〜) |
| 顧問先の反応 | 安心されやすい | 丁寧な説明が必要 |
| トラブルの可能性 | 内部に起因する場合あり | 文化・スタイルの違いで摩擦も |
以下からはそれぞれの承継について詳しく見ていきましょう。
内部承継
内部承継とは、自身の子どもや親族、または事務所の従業員や共同代表など、親族や所内の関係者に事務所を継がせる方法です。
なお、内部承継に際しては、社会保険労務士名簿の登録変更や旧代表の登録証票の返納、新代表の登録証票交付申請が、法人の場合は法務局での登記変更(※代表社員の変更)、社労士会への届出(代表社員変更届)が必要となります。
長年築いてきた信頼関係が土台となるため、経営方針や価値観のズレが起きにくいという特徴があります。
内部承継の主なメリットは以下の通りです。
- 既に信頼関係が築けており、業務内容や顧問先の状況も共有されている
- 顧客や従業員にとっても安心感があり、離脱のリスクが低い
- 事務所の理念や文化を受け継ぐことで、経営方針の一貫性を保ちやすい
一方、デメリットも存在します。
- 親族や事務所内に適切な後継者がいない場合、承継自体が難しい
- 資格を有していても経営マネジメント力や営業力が不足していると、運営が不安定になる可能性がある
- 内部での事業承継は、とかく手続きが曖昧になりがちで、税務や契約、組織の変更に関する整備が不十分になる懸念がある(例:税務署への事業譲渡届出書の提出や、スタッフとの雇用契約更新、各種顧問契約の名義変更などが抜け落ちるケース))
なお、想定される承継としては、以下のようなパターンが挙げられます。
- 資格を保有している、または今後取得予定の親族に承継
- 勤続年数の長い、有資格者のベテラン職員を次期代表に据える承継
- 共同代表制から単独代表制への移行を想定した承継
内部承継は、既に十分な信頼関係があるため、事業の引継ぎは比較的スムーズです。
後継者の選定や育成、そして具体的な手続きに時間をかけることが、事業承継の成功につながります。
後継者と早い段階から引き継ぎを進めるのがポイント
内部承継をスムーズに進めるポイントは、以下の通りです。
- 後継者へは、早い時期から事業の引継ぎを行い、経営に必要な経験を積ませる
- 「承継支援プログラム」の利用や、士業M&Aアドバイザーといった、専門家の助けを借りる
引き継ぎが事前に計画されていれば、事業も安定しやすくなるでしょう。
また、後継者にとっても、経営者としての自覚をもつことにつながります。
もし自分たちだけで事業承継することが難しければ、専門家を頼ることもおすすめです。
専門家にアドバイスをしてもらうことで、自分たちだけで承継しようとするよりも、スムーズで確実な事業承継が実現できるのです。
外部承継・M&A
外部承継、またはM&Aとは、親族や事務所職員以外の第三者に事務所を売却し、事業を引き継ぐ方法です。
士業M&Aとも呼ばれ、昨今では社会保険労務士業界でも急速に拡大しています。
外部承継の主なメリットは以下の通りです。
- 跡継ぎがいない場合でも、事業承継の選択が可能
- 事務所の価値を資産化できるため、売却益を得られる
- 買い手によっては、より組織的なサポート体制を顧問先に提供できるようになる
一方、デメリットも存在します。
- 顧問先が、社会保険労務士が変わることに不安を抱く可能性がある
- 従業員に対し、雇用条件やこれまでの事務所文化が変わることへの配慮が必要
- 買い手の選定を誤ると、顧問先からの信頼や顧客満足度が下がり、契約解除のリスクが生じる
想定される承継パターンとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 他の地域からの事業拡大を考えている、社会保険労務士事務所への売却や承継
- 同業の、個人で営む社会保険労務士との合併や、吸収による承継
- 顧問先を一括で引き継ぎたいと希望する、第三者への譲渡による承継
外部承継が向いているケースは、主に以下の通りです。
- 後継者が全くいない場合
- 引退時期が明確に近づいており、タイムリミットがある場合
- 顧問先や従業員の将来を第三者に託したいという意思がある場合
外部承継を選ぶことで、後継者問題が解決するだけでなく、これまでお世話になった顧問先や、尽力してくれた従業員の生活を守り、新たな事業の発展にもつながります。
どうしても後継者が見つからない、引退まで時間がないという時には、外部承継も検討してみてはいかがでしょうか。
価格だけでなく、「顧客・従業員を大切にしてくれるか」を基準に判断するのがポイント
外部承継をスムーズに進めるポイントは、以下の通りです。
- 買い手企業が「どのような顧客層を重視しているか」や「自社の社員にどう向き合っているか」を面談で確認する
- もし過去にM&Aや吸収合併などの経験がある場合は、その後の運営状況についても詳しく尋ねる
事務所の価値は「数字」だけでなく、「信頼関係」によって成り立っています。
承継によってこの信頼関係を壊してしまっては、本末転倒です。
信頼関係とは、「顧問先が安心して相談できる人間関係」「定期的に顔を合わせて築いてきた信頼感」など。
失うと、契約継続の確率が下がるリスクもあります。
そして最も重要なのは、買い手との「理念・スタンスが合うか」です。
信用できる相手に引き渡して、安心して事務所の未来を預けましょう。
社会保険労務士が事業承継を考える際にまず決めるべき5つのこと

事業承継を考える際に、最初に決めておくべきポイントは以下の通りです。
- いつまでに事業承継したいか
- 承継後にどう関わりたいか
- 事業のどこまでを引き継ぐか
- 誰に事業承継したいか
- クライアントや従業員にどのように伝えるか
事業承継の事前準備を怠ってしまうと、引き継ぎがスムーズに進まないだけでなく、予期せぬ問題に発展する可能性もあります。
ここからは、事業承継を考える5つのポイントを解説していきます。
いつまでに事業承継したいか
事業承継を検討する際に、まずは、「いつまでに完了させたいか」という目標時期をはっきりさせましょう。
「1年以内に引退したい」あるいは「あと3年は現役でいたい」など、目標時期を具体的に定めます。
特に病気や加齢が理由の場合は、不測の事態に備えて早めの行動が大切です。
しっかりしたタイムラインがあると、後継者の選定や引き継ぎの準備、顧問先への連絡などを逆算してスムーズに進めることができます。
承継後にどう関わりたいか
事業承継後、事業にどのように関わりたいかを具体的に決めておきましょう。
なぜならあなたの希望によっては、事業承継の形式(内部承継かM&Aか)や買い手の選定基準も大きく変わるからです。
選択肢としては、以下のようなものがあります。
- 事務所名義や関与を一切外して、事業から完全に身を引く(完全引退)
- 数ヶ月から1年程度、非常勤で顧問や相談役として引き続き事業に関わる
- 事務所の代表を交代するなど、名義は残しつつ、少しずつ事業を引き継いでいく
事業承継後も、「顧問」や「相談役」として、一定期間関わるケースが多く見られます。
事業承継後もなんらかの形で関わり続ければ、顧問先の不安を払拭し、引き継ぎが円滑になるでしょう。
事務所の「顔」として残るのであれば、必ず、後継者と報酬や責任範囲、引き継ぎ期間、そして役割分担をはっきりさせておきましょう。
事業のどこまでを引き継ぐか
事務所の全ての事業を「包括的に引き継ぐのか」、あるいは特定の顧問先や専門業務のみを「一部引き継ぐのか」を決める必要があります。
事業のどこまでを引き継ぐかによって、承継方法(売却、提携、統合など)も変わるからです。
引き継ぐ内容は、主に以下の通りです。
- 顧問契約書の引き継ぎや、更新の有無の確認
- スタッフの雇用関係の継続の有無
- 業務マニュアルや顧客対応履歴、これまでのノウハウなどの知的資産
- ソフトウェアやリース契約、事務所設備の資産類
引き継ぐ範囲をはっきりと決めて、あなたにとって最適な承継方法を選びましょう。
現在の事務所の棚卸しをしておくとスムーズ
事業承継を円滑に進めるには、今の事務所が「何を持ち、どう機能しているのか」を正確に見える化しておく必要があります。
特に外部承継の場合は、買い手側が事務所の価値を正確に評価するために、詳細な情報が必要です。
具体的に棚卸しで整理すべき項目は、以下の通りです。
- 顧問先リスト(契約内容・報酬・担当業務など)
- 財務状況(売上構成・収益状況)の可視化
- 従業員の有無と雇用条件
- 業務マニュアル(社内向け・外部向け)の業務マニュアル
- 契約書類(顧問先・委託先・従業員)
- 過去の業務資料(顧問先ごとの対応履歴も含む)
事務所の資産や業務状況を棚卸しておけば、承継準備は飛躍的にスムーズになります。
誰に事業承継したいか
事業承継を誰にするかは、さまざまな選択肢があります。
誰に承継するかによって、準備すべき書類や交渉手段、今後の信頼関係の構築などは変わってしまうもの。
承継相手として、次が挙げられます。
- 身内(親族・子)への承継
- 所内後継者(職員・共同代表者)への承継
- 外部への承継(M&A)
ここからはそれぞれの承継相手について、詳しく見ていきましょう。
身内(親族・子)への承継
息子・娘といった血縁関係の親族が社会保険労務士資格を保有している、または取得予定である場合に、選択されるケースです。
小規模事務所では稀ですが、家業として事業を受け継ぐイメージに近いと言えます。
身内への承継のメリットは以下の通りです。
- 価値観や理念を共有をしやすく、 承継後の事務所の方向性がぶれにくい
- 顧問先や従業員に、「自然な承継」として受け入れられやすい
- 資金面では、無償や条件緩和での譲渡が可能なため、金銭トラブルが起きにくい
一方、デメリットも存在します。
- 親族が社会保険労務士資格を持っていない、または事業に興味がないことがある
- 先代と後継とで、仕事への適性や意欲に差があると、承継後に、事業縮小や信頼損失のリスクがある
- 感情的な対立が起こると、家族関係に悪影響を及ぼす
身内への承継が向いているケースは以下の通りです。
- 家族経営的に事務所を運営してきた場合
- 親族にすでに資格者がいて、事務所の業務を理解している場合
- 長期的な計画で、徐々にバトンを渡したいと考えている場合
身内の方への承継だからこそ、事前の準備と綿密な話し合いが重要です。
長期的な計画をしっかり立てて、引き継ぎをスムーズにしてください。
所内後継者(職員・共同代表者)への承継
既に事務所に在籍しているスタッフやパートナー(共同経営者)に代表権や経営を引き継ぐ形です。
「内部承継」とも呼ばれ、社内で育った人材を後継者に据える方法と言えるでしょう。
所内後継者への承継のメリットは以下の通りです。
- 顧問先や業務内容、従業員の体制などを理解しているため、引き継ぎがスムーズ
- 既に信頼関係が構築されているので、安心して交渉を進められる
- 顧問先やスタッフにも安心感を与えやすいので、承継後の離脱リスクが低い
一方、デメリットも存在します。
- 経営者としての覚悟やスキルが未熟な場合もある
- 従業員に経営者になるための資金力がないと、資本関係の整理が難航する可能性がある
- オーナー交代にあたり、社会保険労務士会への登録変更や名義変更といった法的手続きが必要となる
所内後継者への承継が向いているケースは以下の通りです。
- 有資格者のベテラン職員が長く勤務している場合
- 共同経営者が既に一部の経営判断に関わっている場合
- 顧問先との関係を変えずに引き継ぎたいと考えている場合
所内後継者への承継は、これまで築き上げた信頼関係を活かせる反面、経営者としての育成と資金面の課題解決が、重要なポイントとなります。
外部への承継(M&A)
外部への承継(M&A)は、親族や所内に適切な後継者がいない場合に有効な手段です。
引き継ぎ相手は、無関係の第三者(社会保険労務士事務所・社会保険労務士法人)になり、顧問契約や事務所資産、スタッフなどを引き継ぎます。
M&A仲介会社などを利用したり、直接探して連絡したりして、相手を見つけるのが一般的です。
外部への承継の主なメリットは以下の通りです。
- 親族や所内に後継者がいなくても、事業承継ができる
- 地域、規模、専門分野など、希望条件に応じた買い手とマッチングできる
- 事業の売却益を得られるため、収入や退職後の資金を確保できる
一方、デメリットも存在します。
- 顧問先やスタッフにとっては「知らない相手」になるため、不安と感じられやすい
- 事務所文化や業務スタイルの違いによって、引き継ぎ時に摩擦が起きやすい
- 相手選びを誤ると、顧客離脱やスタッフ退職などのリスクが起こりえる
外部後継者への承継が向いているケースは以下の通りです。
- 後継者が身内にも所内にもいない場合
- 引退時期が近く、早急に承継相手を見つけたい場合
- 顧問先や従業員を守りつつ、事業を資産化して終えたい意思がある場合
専門的な知識と交渉力が必要となるため、専門家のサポートを受けることが成功への近道となります。
クライアントや従業員にどのように伝えるか
事業承継の準備が整い、承継先が決まったら最後は、顧問先や従業員にどう伝えるかです。
事業承継をスムーズに受け入れてもらえるように、「いつ」「誰が」「どのように」説明するかを段階的に計画する必要があります。
また、単なる事業の「終了」ではなく、「バトンタッチ」であることを誠実に伝えましょう。
顧問先に対しては、事業承継の理由や新しい後継者の紹介、今後のサービス提供体制などを丁寧に説明し、安心感を与えられれば、承継後も良好な関係を維持できます。
従業員へは、承継後の雇用条件や待遇、キャリアパスなどを明確に伝え、不安を解消することが重要です。
誠実な対応を心がけて、スムーズな引き継ぎと事務所の安定的な運営を実現しましょう。
社会保険労務士事務所の事業承継の流れ

社会保険労務士事務所の事業承継の流れは、以下の通りです。
- STEP1:方向性の整理
- STEP2:現状の棚卸しと資料の整理
- STEP3:事業承継先の選定
- STEP4:引き継ぎ条件の協議・合意
- STEP5:顧問先・スタッフへの説明と同意
- STEP6:各種契約・登記・届け出手続き
- STEP7:承継完了とフォローアップ
以下からは、各ステップそれぞれを詳しく見ていきましょう。
STEP1:方向性の整理
事業承継の最初のステップは、「方向性の整理」です。
この段階では、内部承継(親族・職員)か、外部承継(第三者・M&A)かを大枠で決めておきます。
また、以下の方向性を決めておくことも必要。
- いつまでに引き継ぐか?
- 誰に引き継ぐか?
- どの範囲を承継するか?(顧問先、スタッフ、設備など)
- 自分はその後どう関わるか?(完全引退・残留など)
事業承継の目的をはっきりさせておき、具体的な目標設定を行いましょう。
STEP2:現状の棚卸しと資料の整理
次のステップは、「現状の棚卸しと資料の整理」です。
この工程は、「承継できる事務所」かどうかを左右する重要な作業です。
具体的な作業内容は以下の通りです。
- 顧問先の一覧・契約内容・売上状況の整理
- スタッフの勤務状況・雇用条件の把握
- 主要業務のマニュアル化・申請書類の保管場所の確認
- 契約書、会計帳簿、事務所設備、システム利用情報の整理
特に外部承継の場合は、買い手側が詳細調査を行う際に必要となるため、正確で網羅的な資料準備が必要となります。
STEP3:事業承継先の選定
方向性の整理と現状の棚卸しが終わったら、「事業承継先の選定」に進みます。
内部承継の場合は、後継者候補と意向をすり合わせ、経営意欲やスキルを確認してください。
外部承継の場合は、まずは以下の方法で、承継候補を探すことからはじめましょう。
- 士業M&A仲介会社(例:士業コンシェル、バトンズなど)
- 自力で探す(同業者への打診、士会つながり、顧問先から紹介など)
また、上記の候補以外にも、当事務所のような「M&Aや事業承継経験のある、ある程度の規模感の社労士事務所」に直接事業承継を打診する方法も検討してみてください。
社労士事務所への打診は、仲介手数料が不要で交渉がしやすい場合もあるため、有効な手段とされています。
STEP4:引き継ぎ条件の協議・合意
事業承継先が決定したら、「引き継ぎ条件の協議・合意」を行います。
協議する内容は主に、以下の通りです。
- 譲渡範囲(顧問契約、スタッフ、設備など)
- 金額の決定(有償/無償、分割払いなど)
- 引き継ぎ期間中の役割(残留の有無)
- 社労士会への登録や名義変更に関する手続きの分担
顧問先や従業員への影響を最小限にするため、細かく条件を詰めておきましょう。
特に外部承継の場合は、法務や税務の観点からも慎重に進めることが必要です。
STEP5:顧問先・スタッフへの説明と同意
契約の合意が得られたら、「顧問先・スタッフへの説明と同意」のステップです。
このステップが丁寧にできるかどうかで、顧客の継続率とスタッフの定着率が変わります。
説明の際には、事業承継に至った経緯、新たな体制、後継者の紹介、そして今後のサービス提供体制などを説明します。
顧問先には、書面に加え、面談や同席訪問などで丁寧に引き継ぎをし、スタッフにも、労働条件が変わるかどうかを明確に提示してください。
必要に応じて、「引き継ぎ同意書」などの書類を用意しましょう。
STEP6:各種契約・登記・届け出手続き
顧問先やスタッフへの説明と同意が得られたら、「各種契約・登記・届け出手続き」を行います。
主な法的手続きは以下の通りです。
- 顧問契約の名義変更や再契約(必要に応じて)
- 労働保険事務組合や士会への登録変更届出
- 法人の場合は法人代表変更、登記変更、電子申請システムの引き継ぎ
- リース契約や口座などの事務処理
STEP7:承継完了とフォローアップ
最終ステップは、「承継完了とフォローアップ」です。
事業が後継者に完全に引き継がれた後も、一定期間フォローアップを行い、承継後の事務所の安定をサポートしていくことがおすすめ。
実際に、引き継ぎ後数ヶ月〜半年間程度は、任意顧問や顧客フォローといった形で、旧代表がサポートするケースがあります。
顧問先からの問い合わせ対応や、スタッフ育成支援などで「見守り期間」を設けると、安心感が増します。
必要に応じて、新代表の紹介状送付や事務所案内の刷新、HP更新なども行いましょう。
最後まで責任を持って関わることで、社会保険労務士事務所の事業承継を成功に導きましょう。
社会保険労務士の事業承継によくある質問
ここからは、社会保険労務士事務所の事業承継について、よくある質問3つにお答えしていきます。
事業承継の時期はどう決めれば良い?
事業承継の時期は、経営者の年齢や健康状態、後継者の育成状況、そして業界の動向などを総合的に考慮して決めるのが良いでしょう。
理想は、「1〜2年かけて段階的に引き継げる時期」を設定するのがおすすめです。
急な引退や体調不良による承継は、後継者探しや引き継ぎ準備が不十分となり、顧問先やスタッフの不安につながりやすいからです。
特に外部承継では、候補者探しや条件交渉、信頼形成に時間がかかるため、できるだけ早く準備を始めることが大切です。
事業承継に失敗するケースはある?
事業承継に失敗するケースは残念ながら存在します。
特に以下のような場合は要注意です。
- 買い手が業務を理解していない:承継後に顧問先の離脱や業務ミスにつながる
- 顧問先への説明が不十分:これまでの信頼関係が崩れて、契約解除につながる
- 従業員が承継後の体制に不満を抱く:退職や業務混乱が発生する
- 引き継ぎ期間が短すぎる:十分なノウハウが引き継がれず、業務に支障が出る
失敗するリスクを少しでも減らすには、社会保険労務士のクライアントや従業員の引き継ぎ経験が豊富で、ある程度の規模感の社会保険労務士事務所に依頼することをおすすめします。
M&A仲介業者を使うべき?それとも直接探した方が良い?
M&A仲介業者を使うべきか、それとも直接承継先を探すべきかは、「自分に合う承継方法はどちらか」で判断しましょう。
仲介業者を使う場合、直接探す場合におけるメリットやデメリットは、以下の表の通りです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 仲介業者を使う場合 | ・多くの候補者と出会える/契約・交渉をサポートしてもらえる | ・手数料が発生する(成功報酬型が多い)・制約が多い・必ずしも相性の良い相手に変われるとは限らない |
| 直接探す場合 | ・仲介手数料が不要/理念や価値観の合う相手を見つけやすい | ・時間と労力がかかる/交渉はすべて自力対応になる |
直接交渉では契約内容が曖昧になりやすく、譲渡後に「言った言わない」のトラブルに発展するケースもあります。
特に、業務範囲や報酬の取り決めは文書で明文化しておくことが重要です。
また近年は、当事務所のようなM&A経験のある同業の社会保険労務士事務所へ直接打診する方法も注目されています。
仲介手数料を抑えつつ、お互いの理念や業務スタイルを直接確認できる利点があるからです。
信頼できる相手に、自分の納得のいく事業承継を行おう!
この記事では、社会保険労務士事務所の事業承継について解説してきました。
社会保険労務士事務所の事業承継は、経営者にとって大きな決断です。
これまで築き上げてきた顧問先との信頼関係を守るため、廃業よりも承継を検討しましょう。
「誰に、いつ、どのように」引き継ぐかを具体的に考えることで、最適な選択肢が見えてきます。
どのような事業承継の方法を選ぶかは、顧問先や従業員に安心してもらうためにも大切な経営判断です。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジ(https://www.wbridge129.com/)は、複数の社会保険労務士事務所の事業承継・M&A実績があり、顧問先や従業員の引き受けも行っています。
遠隔地であっても、既存の社員の方々が在宅勤務で入社できるため、安心してご相談ください。
